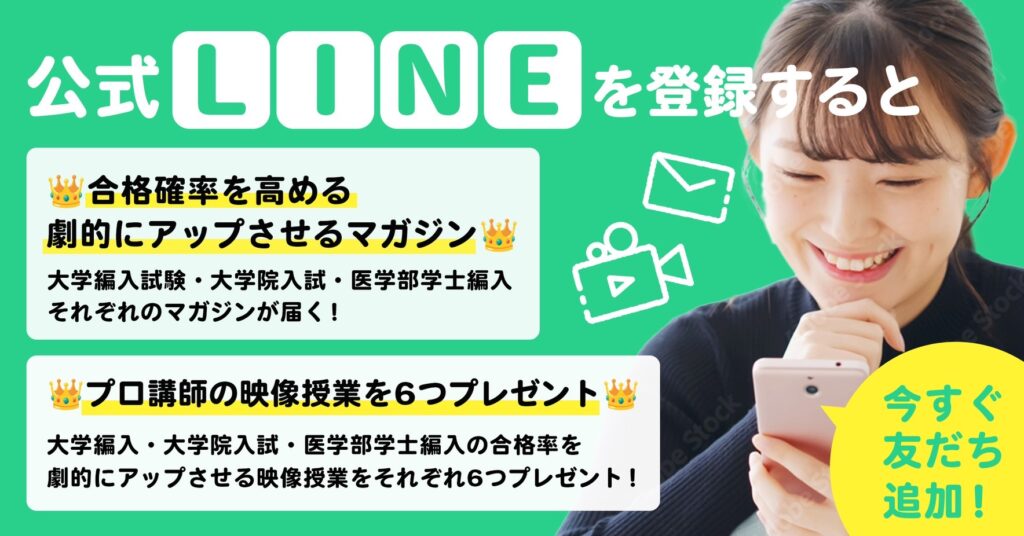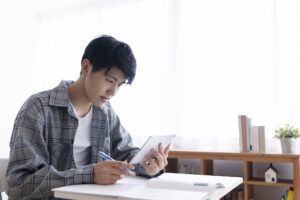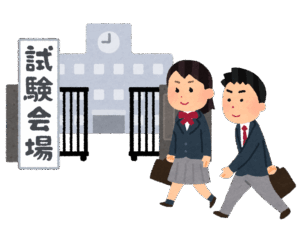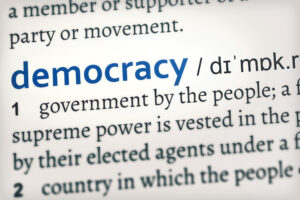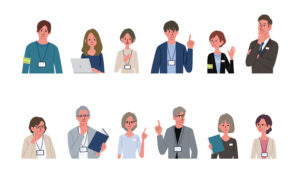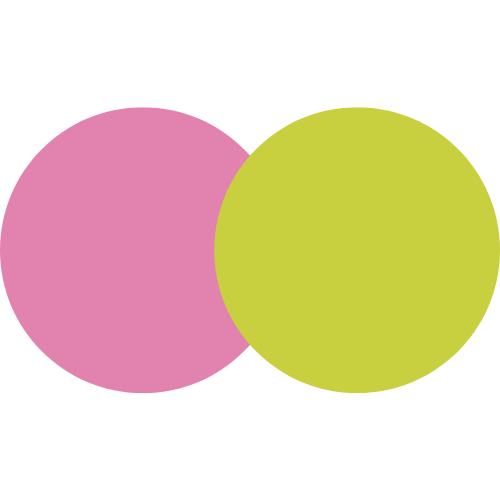ご質問やお問い合わせはお気軽に
【大学編入】これでわかる!北海道大学法学部(3年次)の傾向と対策

スプリング・オンライン家庭教師では大学編入試験のプロ講師による無料相談を実施中!
大学編入試験のプロ講師が、「あなただけの最適な受験プラン」をご提案いたします。無理な勧誘などはございませんので、お気軽にご予約ください。
大学概要
北海道大学法学部は以下のテーマを理念と特徴として掲げています。
北海道大学について
北海道大学は、北海道札幌市に本部を置く、日本を代表する国立大学の一つです。1876年に「札幌農学校」として設立され、以来、教育・研究を通じて多くの優秀な人材を輩出してきました。その広大なキャンパス、美しい自然環境、国際的な研究機関としての役割が特徴的です。この記事では、「北海道大学で何ができるのか」という疑問に答えるため、北海道大学の魅力と特徴を詳しくご紹介します。
北海道大学のキャンパスと施設
北海道大学のキャンパスは、札幌市の中心部に位置し、約1.77平方キロメートルという広大な敷地を誇ります。四季折々の自然が楽しめるキャンパス内には、ポプラ並木やイチョウ並木といった風景が広がり、学生だけでなく観光客も訪れるほどの人気スポットです。
また、北海道大学には充実した施設があります。たとえば、最新の研究設備を備えた「総合博物館」では、北海道大学の研究成果や北海道の自然について学ぶことができます。さらに、附属図書館は膨大な書籍やデジタルリソースを提供し、学生や研究者の学びを支えています。
学問分野の多様性
北海道大学は、10の学部と18の大学院研究科を有し、幅広い学問分野を網羅しています。農学、理学、工学、医学といった自然科学系だけでなく、文学、法学、経済学といった文系分野も充実しています。特に、創立当初から続く農学分野では、日本有数の研究成果を誇ります。
さらに、北海道大学は「学問の自由」という理念を重んじ、学生が主体的に興味を追求できる環境を整えています。たとえば、興味のある分野を横断的に学べる「総合教育プログラム」や、海外の大学との交換留学制度など、学びの幅を広げる多彩な選択肢があります。
研究と国際性
北海道大学は、国内外で高い評価を受ける研究機関として知られています。気候変動、環境保護、宇宙科学といったグローバルな課題に取り組む研究プロジェクトを多数展開しています。特に、北極圏研究では世界トップクラスの実績を持ち、国際的な連携のもとで先進的な研究を進めています。
また、北海道大学は国際化に力を入れており、世界140以上の大学と提携しています。英語で授業が受けられるプログラムや留学生向けの支援体制が整っており、多文化共生の場としても注目されています。
北海道大学での生活
北海道大学での生活は、学業だけでなく多彩な経験を通じて豊かなものとなります。キャンパス内には学生寮や食堂、スポーツ施設があり、快適な環境で学生生活を送ることができます。また、北海道大学祭や雪像を作る「雪氷彫刻イベント」など、学生が主体となって行うイベントも盛りだくさんです。
さらに、札幌という都市ならではの利便性も魅力の一つです。北海道大学の周辺には飲食店やショッピングスポットが充実しており、アクセスも良好です。一方で、少し足を延ばせば北海道ならではの大自然を楽しむことができ、勉強とリフレッシュのバランスを取りやすい環境です。
北海道大学法学部の概要
北海道大学法学部は、学生に幅広い法的知識と実践力を養うための学問の場を提供しています。この学部では、法学の基礎から応用まで多様な領域を学ぶことができ、卒業後は法律家としてだけでなく、さまざまな職業において活躍できる能力を養います。しかし、具体的にどのような学びができるのか、卒業後にはどのようなキャリアパスがあるのかを理解することは、進学を考えている人にとって非常に重要です。この記事では、北海道大学法学部について、その特徴、学べる内容、カリキュラム、卒業後の進路など、詳しく解説します。
1. 北海道大学法学部の概要
北海道大学法学部は、北海道大学の中でも長い歴史と伝統を誇る学部の一つです。北海道大学自体は、明治時代に設立され、その後、国内外から優秀な学生を迎え入れ、世界的にも高い評価を受ける学府となっています。法学部はその中心的な役割を果たしており、法学の基礎から専門的な分野に至るまで、幅広い学問を提供しています。
法学部では、法的思考を養うだけでなく、倫理的な判断力や社会的な責任感を持つ人材の育成にも力を入れています。現代社会では、法律の知識はもちろんのこと、問題解決能力や対話力、批判的思考が求められます。そのため、北海道大学法学部では、学生が多角的に物事を考える力を育む教育が行われています。
2. 学べる内容とカリキュラム
北海道大学法学部のカリキュラムは、法学の基礎から応用、さらには専門分野に至るまで、多岐にわたる内容を学べるように設計されています。以下に、主な学びの内容を紹介します。
2.1 法学の基礎
まず、法学部の初年次では、法学の基本的な概念や理論について学びます。ここでは、法とは何か、なぜ法が必要なのか、法と社会との関係など、法学の基礎的な理論が解説されます。この段階では、法律用語や基本的な法理論を理解することが重要です。
2.2 各分野の専門知識
法学部では、民法、刑法、商法、憲法、行政法など、さまざまな法的分野に分かれて学ぶことができます。それぞれの法律分野に特化した専門的な知識を深め、具体的な法的問題に対応できる能力を身につけます。例えば、民法では契約や不法行為に関する法理論を学び、刑法では犯罪とその処罰に関する法律を学びます。
2.3 国際法・比較法
現代の法学では、国際的な視点が重要です。北海道大学法学部では、国際法や比較法に関する授業も充実しています。これにより、学生は国際社会での法的な課題や、異なる国々の法制度の違いを理解し、国際的な問題に対応できる力を養うことができます。
2.4 法律実務と実習
法学部では、単なる学問的な知識だけでなく、実務的なスキルも重要視されています。そのため、法律実務に関する実習がカリキュラムの中に組み込まれています。模擬裁判やケーススタディを通じて、実際の法的問題にどう対処するかを学びます。
2.5 論理的思考と問題解決能力
法学部では、法律を学ぶだけでなく、論理的思考力や問題解決能力を養うことも重視されています。法律の解釈や適用においては、複雑な問題を整理し、適切な判断を下す能力が求められます。学生はディスカッションやグループワークを通じて、これらのスキルを磨くことができます。
3. 卒業後の進路とキャリアパス
北海道大学法学部を卒業した後の進路は、非常に多岐にわたります。法学部は、法律家を目指す学生だけでなく、さまざまな業界に進む学生を輩出しています。以下は、卒業後の主な進路例です。
3.1 弁護士・司法試験
法学部卒業生の中で最も一般的な進路の一つが弁護士です。北海道大学法学部では、司法試験に向けた準備をしっかりと行えるカリキュラムが整っています。卒業後に司法試験を受け、合格すれば、弁護士として法律実務に従事することができます。
3.2 公務員(裁判所職員、検察官、警察官など)
法学部を卒業した学生は、国家公務員や地方公務員としても活躍しています。特に、裁判所職員や検察官、警察官などの法曹系の職業に進む学生も多いです。これらの職業では、法的知識と社会的責任感が求められます。
3.3 企業の法務部門
企業でも、法学部を卒業した人材を求めています。企業の法務部門で働くことは、契約書の作成や労働法に関するアドバイスなど、企業の法的な問題を解決する仕事です。北海道大学法学部で得た知識を活かし、企業内で法的な問題に対応することができます。
3.4 国際機関・NGO・NPO
法学部を卒業後、国際機関や非政府組織(NGO)、非営利団体(NPO)などで働く道もあります。国際的な法的問題や人権問題、環境問題に関心を持つ学生にとっては、これらの団体でのキャリアが魅力的です。国際法や比較法を学んだ学生は、これらの機関で活躍するチャンスがあります。
3.5 その他の民間企業
法学部卒業生は、法律に直接関わる仕事以外にも、多くの民間企業で活躍しています。たとえば、コンサルティング会社、広告代理店、金融機関などでも、法的な知識や論理的な思考力を活かした仕事をすることができます。
北海道大学法学部は以下のテーマを理念と特徴として掲げています。
北海道大学は1876年に札幌農学校として設立されました。法学部の前身は1947年北海道帝国大学に作られた法文学部になります。法経学部の時代を経て、1953年に法学部となりました。北海道大学法学部では、主に法学と政治学を学ぶことができます。また、法学や政治学の他に、行政学、哲学・思想、法と経済の関わり、歴史、文化、外国事情など、北海道大学法学部で学べる学問は多岐にわたります。北海道大学は世界的に研究機関としての評価も高いことから、北海道大学法学部に編入学後も法学や政治学を深く学び、研究者としての道に進みたいと考える学生にもおすすめです。
入学後に、法学や政治学のみならず多様な分野の学習・研究を進めたい学生にはぴったりな大学と言えるでしょう
試験概要
※2024年度の入試概要になります。
募集要項は例年6月頃に公開されます。
詳しくは、北海道大学法学部3年次編入学生募集要項
試験科目
2024年度の大学募集要項には下記の記載があります。


試験科目の傾向と対策
英語
英文和訳が中心で、文意を理解しにくいような英文からの出題が少なくありません。また、法学や政治学以外の分野の英文が出題されることもあります。法学や政治学の英文に偏らないような学習をする必要があります。基礎的な英語力はもちろんのこと、難解な法学や政治学、その他自然科学や社会科学の英文を理解できるよう対策をする必要があるでしょう。
専門科目
専門科目は法学と政治学から出題がなされます。法学は基本的な問題がほとんどですが、受験生の対策が手薄な憲法の統治分野や財産権からの出題がなされております。他の受験生が落とさないような問題を確実に得点する必要があるでしょう。また、政治学も、政治学の基本概念を回答させるような問題が出題されています。特別な対策は必要なく、政治学を一通り勉強していれば、何を書けばいいかわからないということはないかと思われます。
合格者は毎年10名となっております。
試験科目の詳細
筆記試験
筆記試験では(1)英語(2)小論文の2科目という構成になっております。
英語
北海道大学の英語は他の難関大学同様、2000~3000wordの英文が1題出題されることが多く、下線部和訳や要約問題を課す年が多いです。文意を正確に理解しつつ、スピーディーに問題を処理する能力も試されます。文章のレベルも高く、正確な読解力が要求されます。
北海道大学法学部の編入試験では、英文和訳を中心とした問題が出題されることが特徴です。しかし、出題される英文は必ずしも文意を容易に理解できるものばかりではなく、難解な構造や専門的な内容を含む場合が多いです。さらに、試験では法学や政治学に限らず、自然科学や社会科学といった幅広い分野からの英文が出題されることもあります。このような試験の特性に対応するためには、特定の分野に偏らない総合的な英語力が求められます。本記事では、これらの傾向に適応するための学習方法や対策について解説します。
1. 基礎的な英語力を固める
試験対策の第一歩として、英語の基礎力を徹底的に強化することが必要です。基礎力が不十分なままでは、専門分野の難解な英文を正確に理解することが難しくなります。特に以下の点に注目しましょう。
- 単語力の強化
法学や政治学の専門用語に加えて、自然科学や社会科学で頻出する用語を覚えることが重要です。たとえば、法学で使われる「jurisdiction(管轄権)」や政治学の「sovereignty(主権)」、自然科学の「metabolism(代謝)」といった単語は瞬間的に回答できるに学習しましょう。市販の単語帳だけでなく、過去問や試験対策書から専門用語を抽出し、独自のリストを作成するのも効果的です。 - 文法力の向上
難解な文章ほど複雑な文法構造を含むため、文法知識の確認は欠かせません。特に、関係詞、仮定法、分詞構文、倒置など、長文読解で頻出する構造に慣れる必要があるのはもちろん、連鎖関係代名詞などの文法も完璧に理解する必要があります。
2. 多分野の英文を読む習慣をつける
編入試験では、法学や政治学だけでなく、自然科学や社会科学といった他分野の英文も出題されます。そのため、幅広いトピックに対応するための読解力を養うことが大切です。
- ニュース記事やアカデミックリソースを活用する
社会科学や自然科学に関連する記事を読める媒体として、「The New York Times」や「BBC」の国際ニュース、科学記事を扱う「National Geographic」や「Scientific American」などを利用しましょう。また、オンラインで無料公開されている学術論文やレビュー記事を読むのも良い訓練になります。 - 法学・政治学関連の資料を活用する
法学や政治学の基礎的な知識を日本語で学んだ後、英語の教科書や簡単な学術論文に触れることで、専門的なテーマに関する読解力を向上させることができます。たとえば、「Introduction to Law」や「Political Science: An Introduction」といった英語の入門書がおすすめです。
3. 効果的な読解力の向上法
難解な英文を読み解くスキルを身につけるためには、次のような練習方法を取り入れると良いでしょう。
- 段落ごとの要約練習
各段落の要点を簡潔にまとめることで、文章全体の論旨を正確に把握する力が養われます。特に、主題文や結論部分に注意を払いながら読み進める習慣をつけましょう。 - 構文解析の徹底
難解な文章を前にしたときには、一文一文の構造を分析することが重要です。例えば、「The government’s decision, which was made after months of deliberation, faced strong opposition from the public.」といった複雑な文を、関係代名詞や修飾句を分解しながら理解する練習を重ねましょう。 - 過去問を活用する
試験形式の問題に慣れるため、過去問やを時間を計って解く練習を行いましょう。これにより、出題傾向を把握しつつ、効率的に解答するスキルが身につきます。
4. 速読力を養う
限られた試験時間内で多くの文章を読み解くには、速読力を磨くことも必要です。速読力を向上させるためには、以下のポイントを意識しましょう。
- キーワードを見つける練習
文章全体を逐語的に読むのではなく、重要な単語やフレーズを素早く見つける訓練を行いましょう。特に、接続詞や指示語を手がかりに、文章の論理構造を素早くつかむ練習をすると効果的です。 - リーディングスピードを意識した練習
読むスピードを測りながら練習を行うことで、時間配分の感覚を身につけることができます。初めは内容理解を優先し、徐々にスピードを上げる練習をしてみましょう。
5. 試験特有の出題傾向に慣れる
北海道大学法学部編入試験では、英語だけでなく法学や政治学に関する基礎知識が問われる場合もあります。そのため、英語力の向上に加えて、関連分野の背景知識を深めておくことも重要です。
試験対策は一朝一夕には身につきませんが、日々の積み重ねによって確実に成果を上げることができます。基礎力を固め、幅広い分野に触れ、効率的な練習を取り入れることで、編入試験における成功への道が開けるでしょう。
専門科目
専門科目は、二つの大問から構成されており、一つは法学からであり、一つは政治学からの出題がなされます。
北海道大学法学部の編入試験では、出題の中心が実定法であることが特徴です。概念法学からの出題はほとんどなく、憲法・民法・刑法の3つが試験範囲の主要分野となります。一方で、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政法、商法といった分野は出題されないため、試験範囲は他の大学と同様に比較的限定的です。ただし、「二重の基準論」や「私人間効力」などの基本概念が問われる年もあれば、「法律上の争訟」や「財産権」の具体的なテーマに関する問題が出される年もあり、出題の難易度や傾向にばらつきがあることがこの試験の特徴といえます。
(1)法学
この記事では、北海道大学法学部編入試験に対応するための効果的な学習方法や対策を解説します。
1. 実定法の基本知識を徹底的に固める
試験範囲が憲法・民法・刑法に絞られているため、これらの分野における基礎的な知識を確実に身につけることが最優先です。以下の方法で学習を進めると良いでしょう。
憲法
- 重点分野
「二重の基準論」「私人間効力」「法律上の争訟」など、頻出する基本概念を中心に学習しましょう。特に人権保障や統治機構に関する判例は、憲法の試験対策において重要です。 - 参考書と判例
憲法の学習には『憲法判例百選』などの判例集が役立ちます。基本書としては、芦部信喜の『憲法』のような基本書を繰り返し読むことで、理論的な背景を理解できます。基本書が読みにくければ、資格試験対策の参考書などで対策することも可能です。
民法
- 重点分野
民法では民法総則の基本的な問題が出題されやすいです。特に「契約の成立」「意思表示」「所有権」などのテーマに注目しましょう。 - 学習の進め方
条文を繰り返し読み込み、事例問題を解くことで、民法の論理構造に慣れることが重要です。『民法総則』や『契約法』といった基本書に加え、事例集を活用して問題演習を行いましょう。
刑法
- 重点分野
「構成要件」「違法性阻却事由」「責任能力」など、刑法総論の基本事項を中心に学習しましょう。 - 参考書と問題集
刑法は条文の適用を意識した学習が重要です。『刑法総論の基礎』などの基本書を読みつつ、過去問や予備校の演習問題集を活用しましょう。
2. 判例を重視した学習を行う
北海道大学法学部の試験では、重要判例の理解が問われる問題が出題されることがあります。判例を学ぶ際は、事案の概要、裁判所の判断、そしてその理由付けを正確に把握することが重要です。
- 判例百選を活用する
憲法・民法・刑法それぞれにおいて、『判例百選』シリーズは初学者にもわかりやすい解説が含まれており、学習の基盤を作るために適しています。もっとも、判例も全てを読む必要はなく重要な判例さえ学習できれば十分です。 - 判例を条文と結びつける
判例の解釈は条文と密接に関係しています。条文と判例を関連付けて学ぶことで、試験で問われる法的な論理を身につけることができます。
3. 問題演習で実戦力を養う
基礎知識を習得した後は、問題演習を通じて実戦力を磨きましょう。
- 過去問分析
北海道大学法学部の過去問を入手し、出題傾向を把握します。特に、どの分野からどのようなレベルの問題が出題されているかを分析することが重要です。 - 基本問題を確実に解ける力をつける
北海道大学法学部の試験では、基本的な問題を確実に得点することが合格の鍵となります。複雑な問題を解くことに集中するのではなく、まずは基本的な問題を正確かつ迅速に解けるようにしましょう。
4. 学習計画を立てて効率的に学ぶ
出題範囲が絞られているとはいえ、憲法・民法・刑法それぞれに深い理解が求められます。効率的に学習を進めるためには、計画的な学習が重要です。
- 優先順位をつける
出題頻度の高いテーマや、過去問で多く取り上げられているトピックを優先的に学習しましょう。 - 短期目標と長期目標を設定する
「1週間で憲法の基本概念を整理する」「1か月で民法の事例問題に対応できるようにする」など、短期的な目標を設定し、進捗を確認しながら学習を進めると効果的です。
北海道大学法学部の編入試験では、基礎的な知識の確実な習得と、それを応用できる力が求められます。日々の学習を計画的に進めることで、憲法・民法・刑法の幅広い知識を身につけ、合格に向けた準備を万全に整えましょう。
(2)政治学
政治学の問題はオーソドックスな問題が出題される傾向にあります。政治学の基本概念を理解していれば解答に困る問題は多くないでし北海道大学法学部の編入試験において、政治学は比較的オーソドックスな問題が出題される傾向があります。高度に専門的な知識を問われることは少なく、政治学の基本的な概念や理論を正確に理解していれば解答に困る問題は多くないでしょう。そのため、基礎的な学習を徹底し、標準的な問題に対応できる力を養うことが重要です。
また、有斐閣から出版されている『政治学』に収録されている章末問題と出題内容が類似しているため、これを繰り返し解くことが有効な試験対策となります。本記事では、政治学の効果的な学習方法と、北海道大学法学部の試験に向けた準備のポイントを詳しく解説します。
1. 政治学の基礎概念を徹底的に理解する
政治学の問題では、基本概念や理論を問う問題が中心となります。そのため、まずは政治学の基礎をしっかりと固めることが重要です。
- 基礎的なテキストを活用する
学習の出発点として、『政治学(有斐閣)』や『政治学入門』といった標準的なテキストを繰り返し読むことをおすすめします。これらのテキストは、政治学の基本概念や主要な理論を網羅的に扱っており、試験対策として非常に有効です。 - 重点分野を理解する
以下のような分野が出題されやすいため、重点的に学習を進めましょう。- 権力(Power)とその類型
- 政治制度(Presidential vs. Parliamentary Systems)
- 政治思想(リベラリズム、社会主義、保守主義など)
- 民主主義とその課題(Direct vs. Representative Democracy)
- 国際関係論(リアリズム、リベラリズム、構造主義など)
2. 章末問題を活用したアウトプット学習
有斐閣の『政治学』に収録されている章末問題は、北海道大学法学部の試験対策に非常に有効です。以下の方法で活用しましょう。
- 繰り返し解く
章末問題を一度解いたら終わりにせず、繰り返し復習し、間違えた問題や曖昧な部分を徹底的に潰していきます。特に、解答に必要なキーワードや理論的なフレームワークを正確に把握することを心がけましょう。 - 問題を分析する
各問題がどの分野の知識を問うているかを分析することで、自分の理解が不足している領域を特定し、重点的に学習を進めることができます。 - 記述式の練習をする
選択肢問題だけでなく、記述式問題の対策として、章末問題のテーマを自分の言葉で要約する練習を行いましょう。簡潔かつ論理的に説明する力が試験でも役立ちます。
3. 政治学の理論を実例と結びつける
政治学の理論や概念を学ぶ際は、抽象的な知識に留めるのではなく、実例を通じて理解を深めることが重要です。
- 現代政治のニュースを活用する
日々のニュースや政治情勢を学習に取り入れることで、理論と現実の結びつきを理解できます。例えば、権力分立の議論をアメリカやフランスの制度に照らし合わせて考えると、理解が深まります。 - 歴史的な事例を参照する
政治思想や制度の背景を理解するために、歴史的な事例も参考にしましょう。たとえば、リベラリズムの台頭や社会主義の発展は、それぞれの思想が形成された背景を理解するうえで重要です。
4. 問題演習を通じて実戦力を磨く
試験本番に向けて、問題演習を通じて実戦的なスキルを身につけることが必要です。
- 過去問の分析
北海道大学法学部の過去問が入手できる場合は、まずそれを解き、出題傾向を把握しましょう。特に、どの分野が頻出なのか、問題形式はどのようなものかを確認します。 - 予備校や市販の問題集を活用
政治学の基礎知識を問う問題が収録された問題集を使い、日々演習を繰り返しましょう。問題を解くことで、知識の定着だけでなく、試験における時間配分や効率的な解答方法を身につけることができます。
5. 計画的な学習を進める
試験範囲が広い政治学を効率よく学ぶためには、計画的な学習が不可欠です。
- 学習スケジュールを立てる
試験日から逆算して、各テーマごとに学習期間を設定します。たとえば、「1週間で政治思想の基本概念を理解する」「1か月で章末問題を全問解く」などの具体的な目標を設定すると良いでしょう。 - 定期的に復習する
一度学んだ内容も、定期的に復習することで記憶の定着を図ります。過去に解いた問題やノートを見直す習慣をつけましょう。
北海道大学法学部編入試験の政治学の問題は、基礎知識を確実に身につけていれば十分に対応可能です。試験範囲は広すぎるわけではないため、計画的な学習と章末問題の徹底した活用によって、合格に必要な力を効率よく身につけましょう。ょう。有斐閣から出版されている『政治学』の章末問題と主題が類似しているため、『政治学』の章末問題を繰り返し解き添削を受けることも有効な試験対策になるでしょう。
合格者のスケジュール

合格者の傾向
北海道大学法学部の編入試験では、英語と専門科目(政治学・法学)が出題されますが、合格者にはいくつかの共通した傾向が見られます。それは、英語で基礎的な問題の点数を落とさず、政治学で安定的に高得点を獲得していることです。また、法学の問題では、他の受験生が得点できる基本的な問題を確実に解き、難易度の高い問題では最低限の答案を作成している点が特徴です。
1. 英語:基礎を徹底し、正確な読解力を身につける
英語は基礎的な問題を確実に得点することが合格への第一歩です。そのため、文法、単語、読解力の強化が欠かせません。
- 文法力を磨く
文構造を正確に理解する力は、英文読解の基盤となります。関係代名詞、分詞構文、仮定法といった試験で頻出の文法項目を徹底的に復習しましょう。 - 語彙力を向上させる
一般的な英単語の他に、法学や政治学でよく使用される専門用語も学んでおくことが重要です。例えば、「sovereignty(主権)」や「jurisdiction(管轄)」など、専門科目での理解にもつながる単語を優先的に覚えましょう。 - 読解練習を重ねる
過去問やアカデミックな英文を活用して読解力を鍛えましょう。特に、段落ごとに要点を整理し、論理構造を正確に把握する練習を繰り返すことが効果的です。
2. 政治学:高得点を目指す安定した学習
政治学は、基本的な問題を中心に高得点を狙いやすい科目です。合格者の多くは、ここで得点を稼ぐことで全体の合格ラインを上回っています。
- 基本概念を徹底的に理解する
政治学の問題はオーソドックスな出題が多く、基本概念を正確に理解していれば得点可能です。「権力」「民主主義」「政治制度」といったテーマについて、教科書や入門書を繰り返し読み、基礎を固めましょう。 - 参考書と演習問題の活用
有斐閣の『政治学』や『政治学入門』など、標準的な参考書を活用してください。また、これらの章末問題を繰り返し解くことで、試験の出題傾向に合った学習ができます。 - 理論と現実の結びつきを理解する
抽象的な理論だけでなく、現代の政治や歴史的な事例と結びつけて考えることで、深い理解が得られます。ニュースや国際政治の動向も参考にすると良いでしょう。
3. 法学:基本問題を確実に得点する
法学の問題では、他の受験生が解ける基本的な問題を落とさないことが最重要です。一方で、難易度の高い問題では、最低限の答案を作成するスキルが求められます。
- 憲法・民法・刑法の基礎を固める
試験範囲は憲法、民法、刑法が中心です。それぞれの基本概念や条文、判例を理解することが必要です。特に、頻出テーマである「基本的人権」「所有権」「違法性阻却事由」などに注目しましょう。 - 条文と判例の学習
法学の学習では条文と判例を結びつけることが重要です。『判例百選』などを活用し、基本的な判例の概要と裁判所の判断理由を押さえておきましょう。 - 最低限の答案作成練習
難易度の高い問題に直面した場合でも、白紙で終わらせるのではなく、関連する条文や知識を使って最低限の答案を作成する練習を行いましょう。
4. 効率的な試験対策のポイント
- 時間配分を意識した演習
過去問を活用して、時間配分を意識しながら解答練習を行いましょう。試験時間内に全問を解き切るための練習が必要です。 - 学習スケジュールの作成
試験日から逆算して、英語、政治学、法学それぞれに十分な時間を確保した学習スケジュールを立てましょう。特に、自分の苦手分野に多くの時間を割くように心がけます。 - 基礎重視の学習
合格者の多くは、基本的な問題を正確に解ける力を持っています。複雑な問題にこだわりすぎず、まずは基礎力を徹底的に磨くことが合格への最短ルートです。
北海道大学法学部編入試験は、基礎的な問題を正確に解き、政治学で高得点を稼ぎつつ、法学の難問には最低限の対応をするバランスが重要です。計画的かつ効率的な学習を進めることで、合格に必要な力を着実に身につけましょう。
北海道大学法学部の編入学試験に合格するなら
北海道大学法学部編入学試験では、英語、法学・政治学、志望理由書の作成が必要となります。どの分野も丁寧に答案を作成する必要があるため、入念な準備が必要です。
北海道大学法学部のみならず、難関国公立大学への編入合格者の場合、1年生の秋ごろから勉強を進めている場合が多いです。。
おわりに
いかがだったでしょうか。
スプリング・オンライン家庭教師には北海道大学法学部の編入学試験で受験生を合格に導いた講師も多数在籍しています。受験生一人ひとりに合った最適な講師の指導で最短の合格を導きます。
大学編入は大学を変える最後の機会です。北海道大学法学部をはじめとした難関大学の合格を目指すなら、ぜひ一度無料相談ください。
★無料相談はいつでも受付中!
★お問い合わせは公式HPもしくは公式LINEよりご連絡ください。
【公式HP】https://spring-online.jp
【公式LINE】https://lin.ee/hIY76pU
全国の受験生と繋がれる完全無料の匿名サロンはこちら:【大学編入】経済・経営・商学部
◎過去問解説動画や映像授業はこちら!(スプリングオンライン編入予備校)
https://elearning.spring-online.jp/
スプリング・オンライン家庭教師HP:https://spring-online.jp/
スプリング・オンライン編入予備校HP:https://elearning.spring-online.jp/
YouTubeホーム:https://www.youtube.com/channel/UC50UbsiY7HNGAyxVbz0mLiw
\公式LINEで豪華6大特典をプレゼント中!/