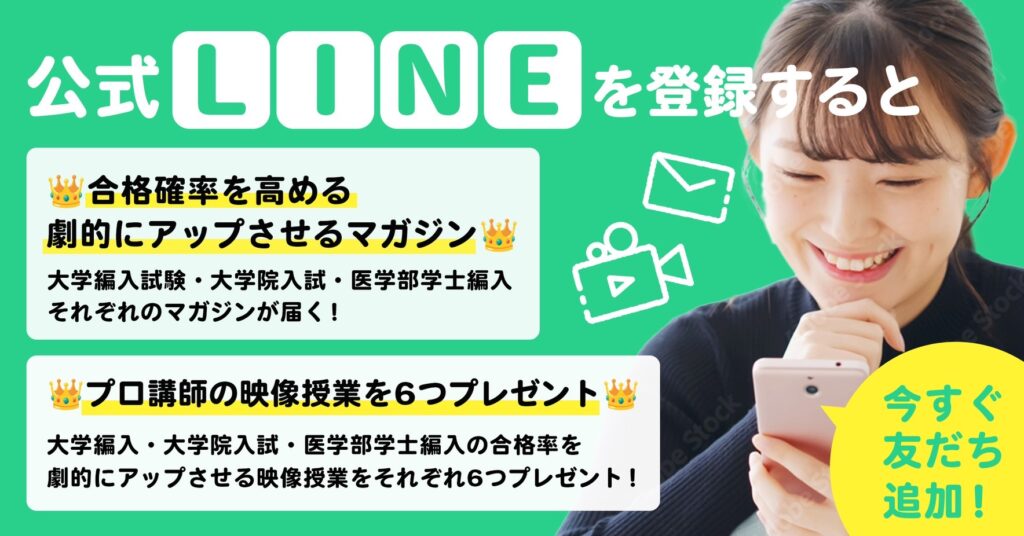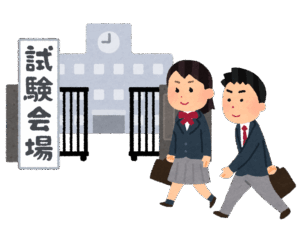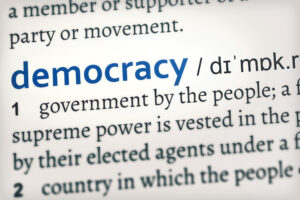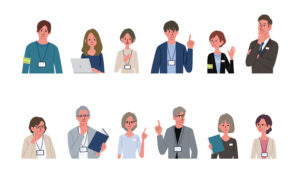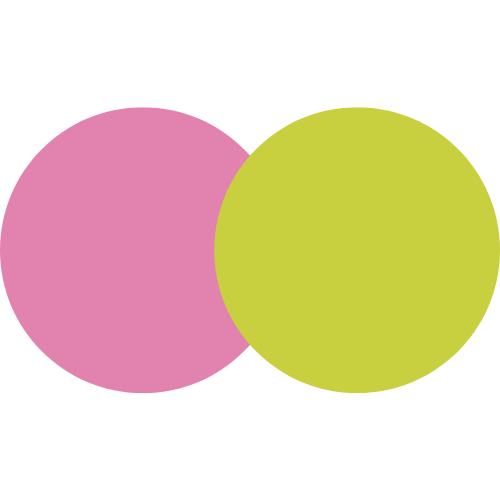ご質問やお問い合わせはお気軽に
【2025年度最新版】これでわかる!法政大学の編入試験!

1. はじめに:法政大学の編入試験とは
大学編入制度は、短期大学・専門学校・他大学の在学生や卒業生が、新たに4年制大学の学部2年次または3年次へ編入するための仕組みです。特に「法政大学の編入試験」は、首都圏の私立大学でも人気が高く、難易度も相応に高いことで知られています。
なぜ多くの受験生が法政大学を志望するのか――その理由としては、MARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)の一角であるという知名度やブランド力、幅広い学部・学科構成、そして卒業後の就職活動や社会的評価などが挙げられます。さらに、キャンパスライフの多様性や学生生活の充実度も大きな魅力です。
一方で、編入試験を行う大学は少なくないため、「法政大学に編入するメリットは何か」「どの学部で募集があるのか」「受験科目や対策方法はどうすればいいのか」など、疑問や不安を抱く方も多いでしょう。本記事では、2025年度版の最新要項を踏まえながら、これらの疑問に答えつつ、編入に必要な具体的な対策や心構えを総合的に解説していきます。
2. 2025年度 法政大学の編入試験要項のポイント
本章では、法政大学が公開している最新の2025年度版「法政大学 編入試験要項」(以下「要項」)の重要事項を中心にまとめます。出願の際に確認すべきスケジュールや試験日程、募集学部・学科、そして出願資格などをしっかり把握しておくことは、合否以前に受験の権利を確実に確保するためにも非常に重要です。
2.1 出願スケジュールと試験日程
2025年度の法政大学編入試験では、多くの学部で秋頃(9〜10月)に出願を受け付け、10〜11月に筆記試験や面接試験を実施するスケジュールが主流となっています。学部によって具体的な日程が若干異なるため、要項の「学部別日程一覧」を必ずチェックしてください。
- オンライン出願期間
例:2025年9月上旬〜9月中旬
(出願登録と受験料支払いをオンラインで行い、その後必要書類を郵送) - 試験日
例:2025年10月〜11月初旬
(学部・学科によって1日完結の場合もあれば、筆記と面接が別日で実施されるケースもある) - 合格発表日
例:2025年11月中旬〜下旬
(Web上での発表が主ですが、合格通知書が郵送される場合も)
※上記はあくまで例示であり、実際には各学部ごとに詳細が異なります。とくに「社会学部」と「経営学部」などは出願期間や試験日が数日だけずれていることもあるので注意が必要です。必ず要項で最新の情報を確認しましょう。
2.2 募集学部・学科・募集人員
法政大学は13学部を擁する大規模総合大学です。ただし、編入試験を実施しない学部・学科や、2年次編入のみを募集する学科、3年次編入のみを募集する学科など、さまざまなパターンが存在します。
2.2.1 主な募集学部例
- 法学部:法律学科、政治学科
- 文学部:日本文学科、英文学科、史学科、地理学科、哲学科など
- 経済学部:経済学科、国際経済学科
- 社会学部:社会学科、メディア社会学科、社会政策科学科 ほか
- 経営学部:経営学科、市場経営学科
- 国際文化学部:国際文化学科
- 人間環境学部:人間環境学科
- 現代福祉学部(多摩キャンパス)
- デザイン工学部(市ケ谷キャンパス)
- 情報科学部(小金井キャンパス)
- 生命科学部(小金井キャンパス)
- スポーツ健康学部(多摩キャンパス)
- キャリアデザイン学部(市ケ谷キャンパス)
ただし各学部・学科が毎年必ず募集を行うとは限らない点には注意してください。年度によっては募集が停止されることがあります。2025年度版要項を確認したうえで、自分が希望する学部・学科に募集があるかどうか必ずチェックしましょう。
2.2.2 募集人員の目安
学部・学科ごとに具体的な募集人員が記載されていますが、定員数はさほど多くなく、若干名〜数名程度というケースもしばしばです。たとえば、ある学科では2年次編入で「若干名」、3年次編入で「10名程度」など、学科間で大きく差がある場合もあります。
少人数募集の場合には、倍率が高くなることが予想されるため、受験生としては対策に抜かりなく挑む必要があるでしょう。
2.3 出願資格・要件の詳細
法政大学の編入試験に出願できる主な資格・要件は、次のように定められています。以下は一般的な例であり、学部・学科によって微妙な差異があるため、必ず要項で自分が該当する区分を確認しましょう。
- 大学在学(休学中も含む)または大学を中途退学した者で、一定単位を修得している
- 例:4年制大学に1年以上在学し、所定の単位数を修得見込み
- 短期大学を卒業(卒業見込み)または2年以上在学し一定単位を修得している
- 2年制短期大学卒業者、または3年制短期大学で2年次を修了している者など
- 専門学校(専修学校専門課程)を修了(修了見込み)している
- 修業年限2年以上かつ総授業時間数1,700時間以上の課程 など
- 高等専門学校を3年以上修了、または卒業した(卒業見込み)
- とくに理工系学部への編入で要件を満たすケースが多い
- 外国の大学に在学・卒業(見込み)で、所定の単位を修得
- 日本国内外の教育課程との互換性などを判断
このように、編入出願の要件は複数ありますが、最も重要なのは「既にどれくらいの単位を取得しているか」です。年度や学部により「○○単位以上」という具体的数値が変わるので、自分が要件に合致しているかを必ず要項で確認してください。
2.4 試験科目の構成と配点
法政大学の編入試験では、多くの場合英語・小論文・専門科目・面接のうち複数の試験が課されます。学部によって配点や実施の有無が異なり、一部学部では筆記試験として「英語+専門科目」、面接試験として「個人面接」だけというケースもあります。
たとえば、ある学部では下記のような例があります。
- 筆記試験:英語(100点)+専門科目(100点)
- 小論文:特定の学部のみ実施(60分〜90分程度で1題)
- 面接試験:個別面接、プレゼン形式、口頭試問などバリエーションがある
配点のバランスを見ても、英語と専門科目が合否を大きく左右するケースが多いです。ただし小論文や面接では、志望動機や学習意欲、論理的思考力が重視されるため、学部によっては小論文・面接の比重が大きい場合もあります。
2.5 その他の重要事項(注意点など)
- 事前にシラバス提出が必要な場合
一部の学部・学科では、これまでに在籍している大学(短大・専門学校)で学んだ科目のシラバス(授業内容記載)を提出させるケースがあります。単位互換を判断するための資料となるため、早めに準備しましょう。 - インターネット出願後の書類郵送
近年はオンライン出願が主流となっています。登録を終えた後に、紙の書類(成績証明書や写真票など)を郵送する必要があるので、締切に遅れないように注意します。 - 学部間併願の可否
法政大学の編入試験では、原則として複数学部の併願は認められていない場合が多いです。要項で明記されているか確認しましょう。 - 過去問題の入手
法政大学公式サイトや、大学生協を通じて過去問が入手できる学部もあります。入手手段がない場合には、予備校や先輩の情報を頼ることも検討しましょう。
3. 法政大学の編入試験の難易度
3.1 MARCH編入全般の位置づけ
法政大学はMARCHの一角として、首都圏の私立大学では早慶に次ぐレベルと認識されることが多いです。編入試験も例外ではなく、単に「大学受験の難易度が下がるわけではない」という点に注意が必要です。一般入試よりも枠が小さい分、競争率が高くなる傾向がある学部も珍しくありません。
3.2 編入試験における合格率の目安
編入試験の合格率や競争率は公開されている学部・学科が限られますが、5倍前後〜10倍超となることもあります。募集人員が「若干名」の場合は、単純に考えても定員数名に対して何十人もの応募があるため、ハードルは低くありません。
ただし、一般入試と異なり編入試験を受験する人数は限られているため、「本気で対策をしている受験生」と「なんとなく受験を決めた受験生」の間で大きな差がつきやすいのも事実です。しっかりとした勉強計画を立て、過去問や対策本を活用することで、十分に合格を目指せるレベルともいえます。
3.3 学部別の傾向と競争率
- 文系学部(法学部・文学部・社会学部・経営学部など)
一般に人気が高く、合格倍率が高くなる傾向。英語+小論文、専門試験(法律・経済など)で点数を稼ぐ必要があり、面接重視の学部も多い。 - 理系学部(情報科学部・生命科学部など)
理系専門科目の難易度が鍵となる。数学や物理、化学、生物など学科ごとの専門試験がある場合は、大学1・2年次レベルの内容が中心となるため、基礎固めが重要。 - 国際文化学部・人間環境学部・現代福祉学部など
比較的新しい学部や専門性の高い学部もあり、試験科目や求められる適性が学部ごとに大きく異なる。小論文や英語力、面接での志望動機がポイント。
4. 法政大学の編入試験のメリット・デメリット
編入制度を利用して法政大学に移ることは、多くの受験生にとって大きなメリットがある一方で、当然ながら考慮すべきリスクやデメリットも存在します。本章では、編入を決断する前に抑えておきたいポイントを整理します。
4.1 編入のメリット(学び直し・キャリア形成・ブランド力など)
- 学びたい分野に再チャレンジできる
現在在籍している大学・学部が自分の興味や将来目標と合っていない場合、編入によって新たな専門分野を学ぶことができます。 - MARCHレベルの大学ブランドを得られる
法政大学の卒業資格を得られるため、就職活動や社会的評価の面で有利になるケースがあります。特に地方から首都圏への進学を考える学生にとっては、大きなステップアップとなる可能性があります。 - 卒業に要する年数が大幅に増えない
一般的に3年次編入の場合、2年で卒業が可能(必要単位が認定された場合)です。学費の面でも4年通い直すより負担が少なくなることが多いです。 - 新しい環境や人脈を築ける
サークルやゼミ活動、アルバイトなどを通じて、法政大学でのネットワークが広がります。特に大規模大学なので、学内外で多様な出会いが期待できます。
4.2 編入のデメリット・リスク
- 受験対策に時間と労力が必要
現在の在籍校の単位を取得しつつ、編入試験対策を進めなければならないため、スケジュール管理が難しくなります。アルバイトなどとの両立も大変です。 - 単位の互換がうまくいかない場合も
編入後に思った以上に認定される単位が少なく、卒業までに余計な時間がかかるケースがあります。特に理系学部や特殊な専門科目が多い学部だと要注意です。 - 経済的負担
もともと在籍していた学校の学費と、編入後の学費が重複する時期があるかもしれません。奨学金や家計の状況などを事前にしっかり確認しましょう。 - 交友関係のリセット
今の大学・学部で築いた人間関係を途中で離れることになるため、新しい環境に馴染むまで孤立感を覚えることがあります。ただし積極的に動けば、逆に多くの友人ができるチャンスでもあります。
5. 編入試験の科目別対策(英語・小論文・専門科目・面接)
法政大学の編入試験では、多くの学部が英語・小論文・専門科目・面接などを中心に試験を実施します。本章では、これら主要科目の特徴と具体的な対策法を詳しく解説します。
5.1 英語対策:長文読解・英作文・語彙強化
5.1.1 出題傾向
- 長文読解問題:1000語程度の長文を読んで内容一致や語句補充、英文和訳などが出題される傾向があります。
- 英作文:段落形式の自由英作文や、日本文を英語に翻訳する形式など。
- 文法・語彙問題:配点はそこまで大きくない場合もありますが、基礎力を問うために出題されるケースも。
5.1.2 対策ポイント
- 単語力・熟語力の強化
大学受験レベル(共通テスト〜難関私大レベル)の単語帳をしっかりマスターしましょう。語彙力が不足していると、長文読解に時間がかかり内容理解も曖昧になります。 - 長文読解の練習
過去問や類似レベルの私立大学編入・一般入試の長文問題を解くことで、スピードと正確性を高めます。英文を和訳する訓練も積極的に行い、構文把握の力を養いましょう。 - 英作文の添削を受ける
独学で英作文を練習しても、誤りに気づきづらい面があります。予備校の先生やオンライン添削サービスを利用するなどして、定期的にフィードバックをもらうことが大切です。 - タイムマネジメント
試験時間内で長文読解と英作文をこなすには、ある程度の速読力と効率的な問題攻略が必要です。過去問を時間を計って解く練習を重ね、本番を想定したペース配分を身につけましょう。
5.2 小論文対策:論理的思考と時事問題への知識
5.2.1 出題傾向
- 時事的テーマや学部に関連する社会問題
社会学部であればメディア論や社会問題、経営学部であれば企業経営やマーケティング、法学部であれば憲法や法律に絡むテーマなど。 - 与えられた資料やデータの読み取り
資料から読み取れる事実をまとめ、それに対する自分の意見を論述させる形式も見られます。
5.2.2 対策ポイント
- アウトライン(構成)の型を身につける
小論文では「序論・本論・結論」の流れが基本です。書き始める前にキーワードを箇条書きで整理し、どの段落にどの内容を配置するか決めておくとスムーズです。 - 時事問題へのアンテナ
新聞やニュースサイトを常にチェックし、自分なりの意見をもつよう意識しましょう。学部関連の用語や専門用語を適度に使うことで、論に説得力を持たせられます。 - 過去問や予想問題での演習
過去問がある場合は必ず入手し、時間を計って実際に書いてみることが最も効果的です。書いた後は添削し、表現の改善や内容の論理性をチェックしてください。 - 文字数・時間配分の把握
小論文の制限字数が800字〜1200字、あるいはそれ以上のこともあります。時間内で書き終わる練習を繰り返すことで本番に焦らず対応できます。
5.3 専門科目対策:学部別の勉強方法
5.3.1 法学部(法律学科・政治学科)の例
- 憲法・民法・刑法などの基礎知識
過去問や編入対策用の問題集で頻出論点を重点的に学習します。判例や条文を正確に理解することが重要。 - 政治学科
政治理論や国際関係論などが中心になります。時事問題とリンクしている場合が多いため、ニュースや政治経済誌も活用。
5.3.2 経済学部
- ミクロ経済学・マクロ経済学
大学1・2年次レベルの問題が出題されるため、教科書の演習問題や基本的なグラフの読み取り方・計算方法を再確認しましょう。 - 国際経済学科
国際貿易論や国際金融論の基礎も抑えておくと有利です。
5.3.3 経営学部
- 経営学・会計学・マーケティング
基本的な理論や用語を理解するとともに、最近の企業事例や業界動向を知っておくと小論文や面接で活かせる場合があります。
5.3.4 理系学部(情報科学部・生命科学部・デザイン工学部など)
- 数学・物理・化学・生物などの基礎
高校レベルではなく、大学初年次レベルの内容までカバー。教養科目テキストや編入対策用問題集を活用しましょう。 - 専門分野の基礎実験やプログラミング
学科によっては実験レポートやコードを理解しているか確認する問題が出るケースもあるので、過去問やシラバスにある到達目標を参考にします。
5.4 面接対策:志望理由・自己PR・将来像の明確化
5.4.1 面接の重要性
法政大学の編入試験では、多くの学部で面接試験が行われます。筆記と同等、あるいはそれ以上に面接を重視する学部もあるため、面接対策は合否を左右する重要要素となります。
5.4.2 よく聞かれる質問例
- 「なぜ法政大学(この学部・学科)を志望したのか?」
- 自分の興味・将来ビジョンを絡めて、具体的かつ論理的に答えられるようにしましょう。
- 「これまで在籍していた大学(短大・専門学校)で学んだことや活動経験」
- 専攻科目やサークル、アルバイトを通じて得たスキル・学びを簡潔にアピールします。
- 「入学後に何を学び、将来どう活かしたいのか?」
- キャリアプランや学問の探求目標を明確にしておくと良い印象を与えます。
5.4.3 対策ポイント
- 事前に自己分析
自分の強み・弱み、興味分野、将来像をあらためて言語化し、面接官に伝えられるように準備しましょう。 - 学部・学科の特徴をリサーチ
志望先が力を入れている研究領域やプログラムを調べ、それに絡めた志望理由を述べると説得力が増します。 - 模擬面接の実施
友人や予備校の講師、オンライン面接練習サービスなどを活用し、本番さながらの緊張感で練習しておくことが大切です。 - 礼儀・身だしなみ・言葉遣い
面接では第一印象が非常に重要です。挨拶の姿勢、言葉遣い、身だしなみなど、基本を徹底しましょう。
6. 学習計画の立て方と勉強スケジュールの具体例
編入試験は一般入試と比べて受験者数が限定的であり、参考書や情報源もやや少ないという特徴があります。そのため、自分の状況に合わせた長期的な学習スケジュールを立てることが合格への鍵となります。
6.1 半年〜1年かけた準備のススメ
理想的には編入試験の半年前〜1年前から本格的な対策を始めるのが望ましいです。とくに専門科目や英語で苦手分野がある場合、半年程度では補強しきれない恐れがあります。
- 1年前
大学のカリキュラムをこなしながら、英語や専門科目の基礎力を再確認する。編入に関する情報収集を始める。 - 半年前
過去問や問題集で具体的な演習を開始。小論文や面接対策もこの時期から強化。 - 3ヶ月前
本試験を想定した模試的な演習(時間を計って解く)を繰り返し、弱点の最終補強を行う。 - 1ヶ月前〜直前
出願書類の最終確認、面接対策の仕上げ、過去問の復習を重点的に。
6.2 日々の学習ルーティン
例えば1日3時間程度を編入対策に充てるとすると、下記のように割り振る方法があります。
- 英語(1時間)
- 単語・熟語の暗記(15分〜30分)
- 長文読解1題(解答・解説読み込み含め30分〜45分)
- 週1回は英作文の練習
- 専門科目(1時間〜1時間半)
- 基礎理論のテキスト読みと問題演習
- 大学1・2年次レベルの教科書やシラバスを活用して効率的に
- 小論文(30分〜1時間)
- 時事ニュースの要点整理
- 週に1〜2回は実際に小論文を書いて添削を受ける
- 面接・志望理由の整理(適宜)
- 実際に声に出して自己PRや志望動機を練習
- 模擬面接の機会があれば参加する
※もちろん人によって状況は異なるので、自分の得意・不得意科目やスケジュールに合わせて柔軟に調整してください。
6.3 模試や過去問を活用するタイミング
- 過去問は早めにチェック
過去問が入手できる学部なら、試験の形式や難易度を早めに把握するためにまず一度解いてみるのがおすすめ。 - 実力判定の模試は夏頃〜秋口
編入試験専門の模試は数が少ないですが、近いレベルの大学入試模試やTOEIC・TOEFLなどを利用して英語力を測る手段もあります。 - 直前期には時間を計って本番シミュレーション
必ず制限時間内に解く練習をし、答え合わせと解説読み込み、復習を徹底する。面接の練習も同時並行で行う。
6.4 忙しい在学生・社会人の時間管理術
- スキマ時間の活用
通学・通勤中に英単語アプリで学習したり、昼休みに小論文のテーマを考えたりといった「短いが継続的な学習時間」を作る。 - 休日にまとまった勉強時間を確保
平日は忙しくても、土日には4〜5時間程度の集中勉強を行い、週間計画との整合性をとる。 - タスク管理ツールやカレンダーの活用
細かい勉強タスクをリストアップし、進捗を見える化することでモチベーションを保つ。
7. 出願書類・提出書類の注意点
編入試験で合否を分けるのは筆記試験や面接だけではありません。出願書類に不備があると、最悪の場合受験資格を失う恐れすらあります。本章では、出願時に提出すべき主な書類と、その注意点を解説します。
7.1 成績証明書・シラバスの取得方法
- 成績証明書
在籍校または卒業校の事務局で発行を依頼します。発行までに数日〜1週間以上かかる場合もあるので、締切の2〜3週間前には手配するのが安全です。 - シラバス(授業概要)
ある学部では、編入後の単位認定の審査を行うために、シラバスのコピーや概要資料を提出させることがあります。大学公式サイトに掲載されている場合もありますが、ない場合は教授や事務局に相談して用意してもらいましょう。
7.2 志望理由書・活動報告書の書き方
- 志望理由書
法政大学の編入試験では、多くの学部で志望理由書の提出を求めます。ここでは「なぜ編入するのか」、「現在の学びとのつながり」、「将来のビジョン」が重要視されます。単に「有名大学だから」ではなく、自分の興味・経験・社会的意義などを組み合わせて書くと説得力が増します。 - 活動報告書・自己PR書
サークル活動やボランティア、アルバイトなどの経験を通じて学んだことを具体的にアピールしましょう。「リーダーシップを発揮した」「チームワークの大切さを学んだ」など、成果や学びを数値や具体例で示すと評価が高まりやすいです。
7.3 受験票・写真票などの不備を防ぐコツ
- オンライン出願システムの入力ミスに注意
名前や住所、メールアドレスなどを誤入力すると、受験票が届かない可能性があります。 - 写真のサイズ・背景色
指定された寸法、背景色などを厳守。証明写真機や写真館で撮影し、最新のものを使用しましょう。 - 郵送方法
簡易書留など追跡可能な方法を利用し、期日必着で提出。郵便局の営業時間も考慮して、ギリギリにならないよう計画します。
8. 試験当日の流れと注意事項
8.1 会場へのアクセス・持ち物チェック
- 会場へのアクセス
市ケ谷キャンパス、多摩キャンパス、小金井キャンパスなど、学部によって試験会場が異なります。当日迷わないよう、事前に下見しておくか、Googleマップ等で経路を確認しておきましょう。 - 持ち物
- 受験票・身分証明書(学生証・運転免許証など)
- 筆記用具(複数本の鉛筆やシャープペンシル、消しゴム、時計)
- 必要に応じて上着や飲み物、軽食
8.2 試験会場での心構え
- 早めに到着し、落ち着いて準備
試験開始の1時間前には現地に到着できるようにする。心に余裕ができ、リラックスした状態で受験に臨めます。 - 周囲に流されない
試験直前までノートを見返している人が多いかもしれませんが、焦って新しいことを詰め込むより、これまで積み重ねた知識を信じることが大切です。 - 案内放送や指示を確実に聞き取る
科目ごとの教室移動や休憩時間について、アナウンスがある場合があります。聞き逃さないよう注意しましょう。
8.3 試験後の面接や追加試験について
- 筆記試験後に面接を行う学部
同日中に面接が行われる場合は、筆記での疲れを引きずらないよう、短時間で頭を切り替えるのがポイントです。 - 追加試験・再試験は原則なし
病気や遅刻などで受験できなかった場合でも、基本的に再試験は行われません。緊急事態に備えて早めの行動を心がけましょう。
9. 合格後の手続きとキャンパスライフ
9.1 入学手続き・学費納入の流れ
- 合格発表後の手続き
合格通知書に記載の期限内に、入学金や前学期の学費を納付し、必要な書類を提出します。大学生協や課外活動にも加入を希望する場合は、別途手続きが必要です。 - 単位認定の手続き
編入後、どの単位が認定されるかは学部・学科ごとの審査によります。認定されなかった科目は改めて履修し、修得し直す必要があります。
9.2 法政大学のキャンパス(市ケ谷・多摩・小金井)の特色
- 市ケ谷キャンパス
都心に位置し、法学部や文学部、経済学部、キャリアデザイン学部などが集結。ビル型の校舎が多く、アクセスも抜群です。 - 多摩キャンパス
緑豊かな丘陵地にあり、社会学部や経営学部、現代福祉学部、スポーツ健康学部などが所在。広々としたキャンパスライフを楽しめます。 - 小金井キャンパス
理系学部がメイン(理工系・情報系・生命科学系など)。最先端の研究施設や実験設備が整い、専門分野の研究を深められます。
9.3 編入生でも楽しめるサークル・ゼミ活動
編入生だからといってサークル活動やゼミへの参加に制限があるわけではありません。むしろ、編入生同士のコミュニティや、既存の学生との交流を通じて視野を広げる絶好のチャンスです。
- サークル・学生団体
法政大学には運動部から文化系サークル、ボランティア団体まで数えきれないほどの団体があります。積極的に説明会や新歓イベントに参加してみましょう。 - ゼミ活動
学部ごとに特色あるゼミが存在します。研究テーマや教授の指導方針をよく調べ、自分の興味や将来像に合ったゼミを選ぶと充実度が高まります。
10. 法政大学に編入した先輩たちの声(OB・OGの体験談)
10.1 編入してよかったこと、苦労したこと
- 「やりたい分野の勉強をやり直せた」
短大出身者が「もっと深く学問を追求したい」と思い立ち、法政大学の文学部に編入。専門分野での学びに集中でき、ゼミ活動で学会発表の機会まで得たという体験談があります。 - 「単位があまり認められず、思ったより忙しい」
一方で、大学の専門科目が想定より認定されず、3年次編入でも卒業に3年近くかかったというケースも。シラバスの整合性や履修計画を慎重に立てる必要があります。
10.2 就職活動やキャリア形成への影響
- 「OB・OGネットワークとキャリアセンターが充実」
法政大学は卒業生が多いため、業界や企業とのつながりが広いと評価されています。編入生でもキャリアセンターのサポートを受けやすく、大手企業からの求人情報やOB訪問の機会を得やすいという声も。 - 「大学名の効果は一定あるが、結局は個人次第」
「MARCHだから就職が保証される」というわけではなく、面接や自己PRなどの本人の努力も必要、という厳しい現実的な意見も。ただし大学ブランドが面接機会を広げる要因になることは事実です。
11. 法政大学の編入試験を受けるか迷っている方へのアドバイス
11.1 他大学との比較検討
編入を検討する際は、法政大学だけでなく明治・青山学院・立教・中央大学など他のMARCHや、早慶、上智などの大学編入制度も比較することで、より自分に合った選択が見えてきます。学費や募集人員、試験科目など、大学によって特徴が異なります。
11.2 経済面・奨学金制度の確認
- 奨学金や学費減免制度
法政大学独自の給付奨学金や、日本学生支援機構の貸与型・給付型奨学金など、編入生でも利用できる制度があります。申し込み時期や条件をよく調べましょう。 - アルバイトとの両立
都心や近郊にキャンパスがあるため、アルバイトの選択肢は豊富です。とはいえ、学業とのバランスを取るために、無理のない範囲で働ける環境を選ぶ工夫が必要です。
11.3 “なぜ編入するのか”を再確認しよう
- 「今の大学に不満があるから」だけでは浅い
不満を解消したい気持ちも大切ですが、ポジティブな動機――「法政大学で学びたい具体的なテーマや目標」を明確にすることで、面接や小論文でも説得力が増します。 - 将来のキャリア設計にどう活きるか
編入は通過点に過ぎず、その先の卒業や就職、大学院進学なども見据えて考えると後悔の少ない選択ができます。
12. まとめ:法政大学の編入試験で新たな未来を切り開く
「法政大学の編入試験」は、MARCHの一角というブランド力に加え、専門分野を深められる多様な学部・学科が魅力であり、卒業後のキャリアにも大きな可能性を広げてくれます。募集定員が限られるため、一見ハードルが高そうに思えますが、受験生が比較的少ない分、適切な対策を積んだ人にチャンスがあるのも事実です。
- 最新の要項の熟読とスケジュール管理
まずは2025年度の要項を確認し、出願資格や試験日程、必要書類を把握すること。特に単位互換や出願資格については早めにチェックしておかないと手遅れになる可能性があります。 - 英語・小論文・専門科目・面接の重点対策
編入試験で重要となるこれら4領域をバランスよく学習することが合格への近道です。英語は長文読解と英作文、小論文は時事知識と論理構成、専門科目は大学1〜2年次レベル、面接では志望理由と自己分析を磨く。 - 過去問やシラバスの活用
過去問が入手できる場合は最優先で取り組み、試験傾向をつかむ。単位認定審査に備えてシラバスも整理しておく。 - モチベーションの維持と計画的な学習
在学中や仕事をしながらの受験では時間が限られますが、スマホアプリやオンライン添削サービスなどを使って効率を高めましょう。休日や長期休暇を活用し、集中的に対策するのも効果的です。 - 合格後は新しいキャンパスライフを満喫
法政大学の大規模なキャンパスと多種多様な学生との交流は、人生の大きな財産となります。学問だけでなく、サークル活動や留学、インターンなど多方面に挑戦するチャンスを得られるでしょう。
最後に、「本当に編入してよいのだろうか」「合格できるか不安…」と悩んでいる方も多いかもしれません。しかし、編入という選択肢は自分の人生を大きく変えうる可能性を秘めています。もし「やり直したい」「もっと学びたい」という強い意志があるなら、その気持ちを行動に移してみる価値は十分にあります。
 スプリング・オンライン
スプリング・オンライン本記事が、皆さんの「法政大学の編入試験」に対する疑問や不安を少しでも解消し、前向きに受験勉強に取り組むきっかけになれば幸いです。あなたの挑戦が実りあるものとなるよう、心から応援しています。