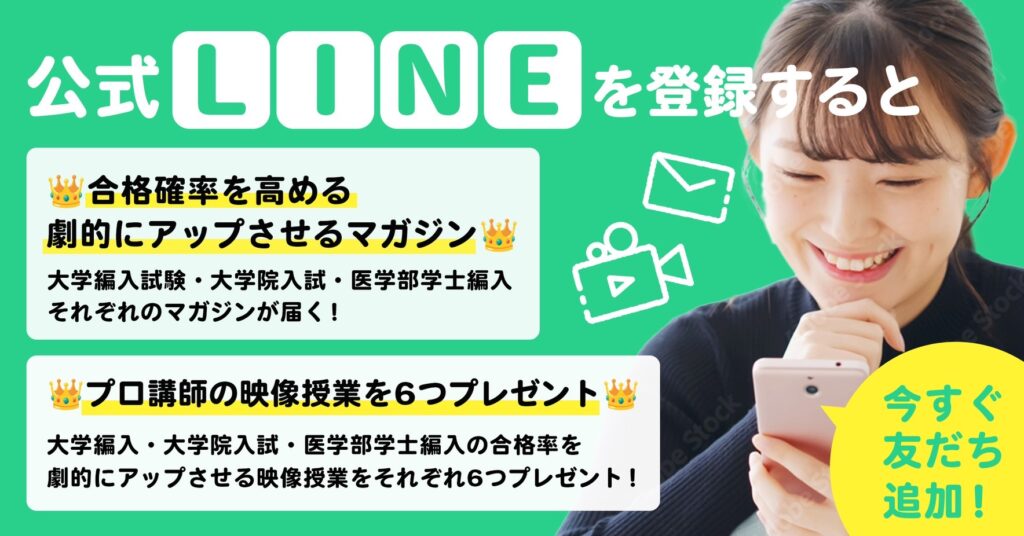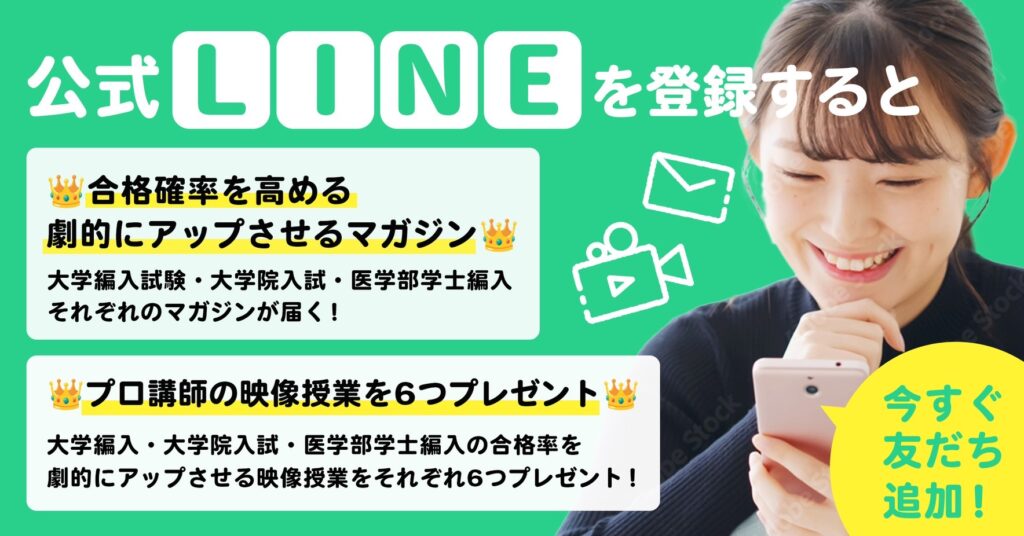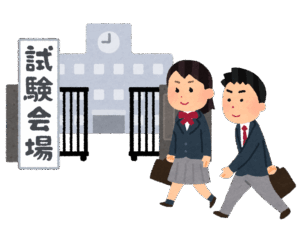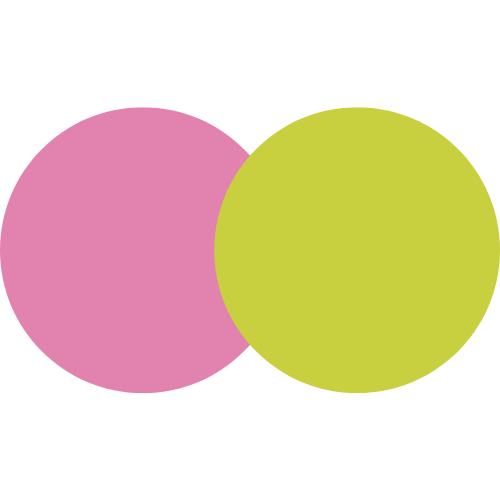ご質問やお問い合わせはお気軽に
医学部学士編入対策大全|実施大学一覧・難易度・ 倍率・TOEIC

スプリング・オンライン家庭教師 監修【最終更新日:2025年10月8日】
「社会人としてキャリアを積んだけれど、医師になる夢を諦めきれない」「今の専門知識を、医療の世界で直接人のために役立てたい」
このように考えているあなたにとって、 医学部学士編入 は、再び医師への扉を開くための最も現実的な道です。
しかし、いざ情報を集めようとすると、「情報が断片的で全体像がつかめない」「合格者はどんな対策をしたんだろう?」「自分の経歴でも合格できるのだろうか?」といった壁に突き当たっていませんか?
私立文系大学から合格した先輩も、こう語っています。
学士編入ってどんな制度? 試験科目って…? ネットで検索してもほとんど情報がないし、大学受験ではあるあるの赤本もない… じゃあ、どうやって対策をすればいいの? このページに辿りついた方は、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。 私自身、編入を考え始めたときは暗中模索な状態で、ほんとにほんとに不安でした…(引用:https://spring-online.jp/column/2895/)
この記事は、そんなあなたのための 医学部学士編入の完全ガイド です。
医学部学士編入を専門とする「スプリング・オンライン家庭教師」が、2026年度(2025年実施)の医学部学士編入試験の実施大学一覧や難易度、日程、倍率といった情報を網羅的に解説。さらに、 実際に合格を勝ち取った先輩たちのリアルな声 を、体験記から直接引用する形で交えながら、あなたの疑問に全て答えます。
この記事を最後まで読めば、医学部学士編入の全体像から、あなたに合った大学選び、そして合格までの最短ルートまで、全てを理解できます。
今すぐにあなたのバックグラウンドに合わせた専門的な学習戦略や、志望理由書の作成、面接対策など、よりパーソナルなサポートを受けたい場合は、ぜひ 「スプリング・オンライン家庭教師」の無料相談 をご利用ください。
大阪大学 や 東京科学大学(旧・東京医科歯科大学) 、 北海道大学 などをはじめ数々の医学部学士編入試験で合格者を輩出してきたプロ講師陣が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、合格までの最短ルートを一緒に考えます。現在、 公式LINE にご登録いただいた方限定で「 医学部学士編入の合格率を劇的にアップさせる映像授業 」計6本をプレゼント中です。ぜひこの機会にご登録ください。
第1章 医学部学士編入とは?
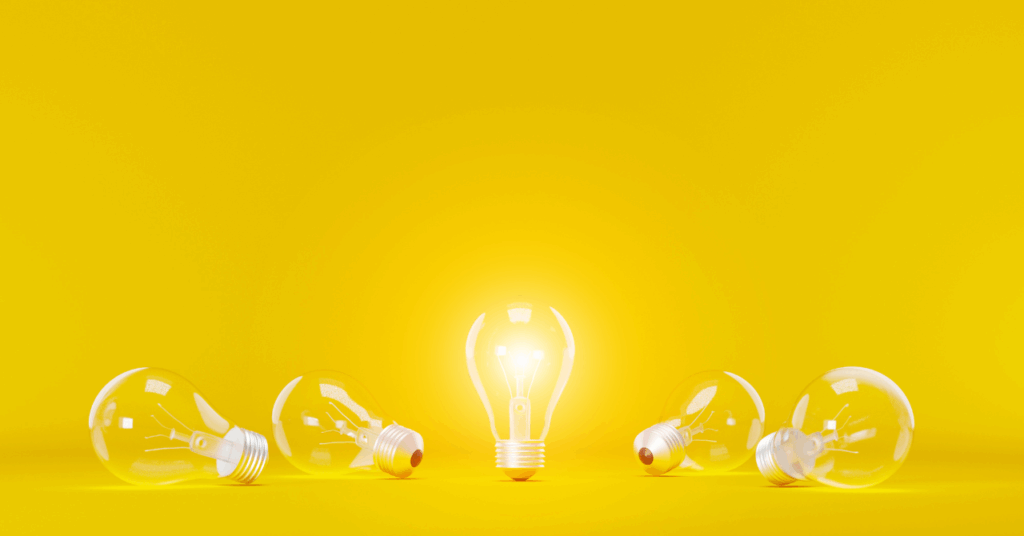
まず、医学部学士編入制度の全体像を正確につかみましょう。この章では、「そもそも学士編入とは何か?」という基本的な疑問から、一般入試との違い、そして多くの受験生が実感するメリット・デメリットまで、制度の根幹となる知識を分かりやすく解説します。
1-1. 医学部学士編入制度は4年制大学卒業者向けの医学部入学ルートのこと
医学部学士編入制度とは、 4年制大学を卒業した者(または卒業見込みの者)が、医学部の主に2年次(一部3年次)に入学するための試験制度 です。
一般的な高校生が大学入学共通テストを経て1年次から入学するルートとは全く異なる、別の入学経路が用意されているのです。
この制度の大きな目的は、多様なバックグラウンドを持つ人材を医療界に迎え入れることにあります。例えば、社会人経験で培ったコミュニケーション能力は、患者さんとの信頼関係構築に直接役立ちます。医学以外の専門知識や社会経験を持つ人材が、医療の質の向上と発展に大きく貢献できると期待されているのです。
1-2. 一般入試との最大の違いは「受験科目の少なさ」です
医学部学士編入が多くの社会人や再受験生にとって魅力的な選択肢となる最大の理由は、一般入試との 「受験科目」 の違いにあります。
- 一般入試 : 大学入学共通テストで 5教科7科目 という広範な学力が求められます。これに加え、大学独自の二次試験も課され、非常に多くの科目を長期間にわたって勉強する必要があります。
- 学士編入 : 試験科目は大学によって異なりますが、多くの場合 「英語」「生命科学」「物理・化学などの理系科目」「小論文」 などに絞り込まれます。
対策すべき範囲が明確になるため、働きながらでも、より深く集中した学習が可能です。
1-3. 知っておくべきメリットとデメリット
どんな制度にも良い面と厳しい面があります。ここでは、学士編入のメリットとデメリットを、実際に受験した先輩たちの声も交えながら客観的に整理します。あなたにとって最適な道かを見極める判断材料にしてください。
メリットは「少ない科目」「複数回のチャンス」「年齢不問」なこと
- 受験科目が少なく、対策に集中しやすいこれが最大のメリットです。特に、多くの大学で課される最重要科目「生命科学」に学習時間を集中投下できます。文系出身で合格した先輩も、この点について次のように述べています。一般入試の場合は、共通テストも含めると7教科ほど学習する必要があり、受験勉強と学業・仕事の両立を考えると時間や体力面でかなり厳しいものがあります。一方で編入は2科目型の場合、生命科学と英語のみなので、かなりハードルが下がるように思いませんか?(引用: https://spring-online.jp/column/2895/ )
- 1年に複数回の受験機会がある一般入試の国公立大学は前期・後期日程が基本ですが、学士編入は大学ごとに試験日程が全く異なります。早い大学では4月に出願が始まり、遅い大学では翌年の2月に試験が行われます。これにより、1年間に複数の国公立大学・私立大学を受験する「併願戦略」を立てることが可能です。一般入試の場合は、最大でも前・後期の2回しか受験できません。また、共通テストにおいて、かなりの高得点を求められます。どこかでミスしてしまうとその時点で、また来年という結果が待ち受けています。一方、編入は日程が重複しなければ、十数校の受験が可能です。(引用: https://spring-online.jp/column/2895/ )
- 年齢制限がなく、何歳からでも挑戦できるこの制度には基本的に年齢の上限がありません。実際に、30代、40代、50代、さらには60代で合格を掴み、医師として新たなキャリアをスタートさせた方もいます。社会人経験は、面接試験などにおいてむしろ高く評価される傾向にあります。私の体感では、メインの受験者層は20代後半~30代前半の方だと思います。数年の社会人経験の後、何らかのきっかけで医師として活躍したいと思うようになったという話はよく聞きます。 その一方で、40代、50代、それ以上の方でも少数にはなりますが、合格者はいらっしゃいます。「そういう合格者は東大や海外の有名大学出身の超ハイスペックな人じゃないの?」とツッコミを入れたくなりますが、必ずしもそうではありません。(引用: https://spring-online.jp/column/2895/ )
デメリットは「熾烈な競争」「専門知識が必要」「情報が少ない」こと
- 募集人数が少なく競争が熾烈である学士編入の募集定員は、多くの大学で わずか5名程度 です。弘前大学の20名といった例は非常に稀で、この狭き門に、高い意欲と学力を持つ受験生が全国から集まります。その結果、倍率は数十倍、時には100倍を超えることもあり、極めて高い競争率となります。
- 要求される知識の専門性と深度科目数は少ないものの、特に生命科学で問われる知識のレベルは、大学教養レベルを遥かに超え、大学院レベルに匹敵します。最新の研究論文を題材にした問題が出題されることもあり、表面的な理解では全く歯が立ちません。
- 対策に関する情報が少ない一般入試に比べて受験者数が少ないため、対策に関する情報が限られています。過去問が非公開の大学も多く、独学で対策を進めることには困難が伴います。この点については、多くの合格者が苦労した点として挙げています。秋田大学に合格した櫻井さんは、インタビューで次のように語っています。
多くの人が思うことであると思うのですが、情報が手に入りにくいことが特有の悩みでした… 自分は予備校など使わずに独学で編入試験の勉強を行っていたので、情報収集にかなり多くの時間を取られてしまいました。(引用: https://spring-online.jp/column/2886/ )
第2章 【2026年度入試】医学部学士編入 実施大学一覧

この章では、あなたの受験戦略の基盤となる、最新かつ網羅的な大学データベースを提供します。
多くの受験生が直面する課題は、志望校選びの煩雑さです。各大学で異なる試験日や科目を一つひとつ確認し、比較検討するのは簡単なことではありません。
この課題を解決するため、以下の表では各大学の情報を一覧にまとめ、比較しやすい形式で整理しました。
この表を活用し、あなたの強みや学習状況に合わせた、あなただけの併願戦略を構築してください。
【重要】
以下の情報は2025年8月29日時点で判明している2026年度(主に2025年実施)の入試情報です。出願期間や試験日は変更される可能性があります。 出願にあたっては、必ず各大学の公式ウェブサイトに掲載されている最新の募集要項を直接確認してください。
| 大学名 | 区分 | 募集人数 | 出願期間 | 筆記試験日 | 面接試験日 | 試験科目 |
| 北海道大学 | 国立 | 5名 | 2025/7/15~7/23 | 8/17 | 10/5 | 生命科学総合問題(1次)、課題論文・面接(2次) |
| 旭川医科大学 | 国立 | 10名 | 2025/9/1~9/5 | 10/25 | 11/22 | 生命科学, 英語(1次)、個人面接(2次) |
| 秋田大学 | 国立 | 5名 | 2025/9/4~9/12 | 11/6 | 11/7 | 書類審査(1次)、小論文, 生命科学, 面接(2次) |
| 弘前大学 | 国立 | 20名 | 2025/10/21~10/27 | 11/16 | 12/14 | 書類, TOEFL, 基礎自然科学, 数学(1次)、面接(2次) |
| 群馬大学 | 国立 | 15名 | 2025/7/23~7/28 | 9/7 | 10/12 | 小論文(英語・自然科学含む)(1次)、面接(2次) |
| 筑波大学 | 国立 | 5名 | 2025/6/2~6/6 | 7/12 | 7/13 | 学力試験(英語, 数学, 化学, 生物), 適性試験(筆記試験, 面接) |
| 東京科学大学(旧・東京医科歯科大学) | 国立 | 5名 | 2025/5/12~5/16 | 6/11 | 7/9 | 自然科学総合, 書類(1次)、面接(2次) |
| 浜松医科大学 | 国立 | 5名 | 2025/7/28~8/6 | 8/30 | 10/5 | 生命科学, 英語(1次)、小論文・面接(2次) |
| 金沢大学 | 国立 | 5名 | 2025/8/18~8/22 | 9/19 | 10/17 | 書類(1次)、生命科学(2次)、口述試験(3次) |
| 富山大学 | 国立 | 5名 | 2025/7/28~8/1 | 9/7 | 11/16 | 総合試験, 課題作文(1次)、口頭発表・面接(2次) |
| 福井大学 | 国立 | 5名 | 2025/7/7~7/11 | 8/30 | 11/1 | 自然科学総合(1次)、面接(2次) |
| 名古屋大学 | 国立 | 4名 | 2025/5/1~5/9 | 6/5 | 7/3 | 筆記試験(生命科学中心), 英語(外部試験)(1次)、小論文・面接(2次) |
| 滋賀医科大学 | 国立 | 15名 | 2025/8/25~8/29 | 9/20 | 10/21 | 総合問題, 英語(1次)、小論文, 面接(2次) |
| 大阪大学 | 国立 | 10名 | 2025/6/2~6/6 | 7/5 | 7/26 | 英語, 生命科学, 物理, 化学(1次)、小論文・面接(2次) |
| 神戸大学 | 国立 | 5名 | 2025/7/3~7/9 | 8/5 | 9/5 | 総合問題(生命科学・英語)、書類審査(1次)、口述試験(2次) |
| 岡山大学 | 国立 | 5名 | 2025/4/9~4/18 | 書類審査 | 6/28 | 生物学, 小論文, 面接 |
| 島根大学 | 国立 | 2年次:5名 3年次:5名 | 2025/7/15~7/18 | 8/23 | “9/20,21” | 英語, 自然科学(1次)、面接(2次) |
| 鳥取大学 | 国立 | 5名 | 2025/8/4~8/8 | 9/6 | – | 書類、基礎科学、英語、面接 |
| 山口大学 | 国立 | 10名 | 2025/7/28~7/31 | 9/28 | 11/16 | 学科試験, 小論文(1次)、面接(2次) |
| 愛媛大学 | 国立 | 5名 | 2025/6/23~6/27 | 7/19 | “8/25,26” | 自然科学総合(1次)、面接(2次) |
| 香川大学 | 国立 | 5名 | 2025/5/7~5/16 | 6/7 | 7/6 | 自然科学総合, TOEIC(1次)、面接(2次) |
| 高知大学 | 国立 | 5名 | 2025/6/9~6/12 | 7/5 | “8/21,22” | 総合問題(1次)、面接, グループワーク(2次) |
| 長崎大学 | 国立 | 5名 | 2025/7/11~7/18 | 8/22 | 10/3 | 生命科学, 小論文(1次)、面接(2次) |
| 大分大学 | 国立 | 10名 | 2025/4/21~4/25 | 6/17 | 7/29 | 書類(1次), 生命科学総合, 英語(2次), 面接, ディスカッション(3次) |
| 鹿児島大学 | 国立 | 10名 | 2025/5/2~5/9 | 6/7 | 7/5 | 学力試験(生命科学), 面接 |
| 琉球大学 | 国立 | 5名 | 2025/7/31~8/7 | 9/9 | 10/16 | 生命科学総合(1次)、小論文・面接(2次) |
| 奈良県立医科大学 | 公立 | 1名 | 2024/12/2~12/6 | 2025/2/1 | 2025/2/15 | 英語, 数学, 理科(1次), 面接(2次) |
| 岩手医科大学 | 私立 | 若干名(3年次) | 2025/1/20~2/6 | 2/17(1次) | 3/3(2次) | 生命科学全般・小論文(1次)、面接(2次) |
| 東海大学 | 私立 | 10名(1年次) | 2024/10/11~10/23 | 11/10(1次) | 11/24(2次) | 書類審査・英語・小論文(1次)、個人面接(2次) |
| 北里大学 | 私立 | 若干名(1年次) | 2024/11/1~11/7 | 11/17(1次) | 12/8(2次) | 基礎学力検査、論文(1次)、面接(2次) |
| 金沢医科大学 | 私立 | 15名(1年次) | 2024/11/16〜11/22 | 11/30(1次) | 12/8(2次) | 基礎学力テスト・自己推薦書(1次)、個人面接(2次) |
| 金沢医科大学(研究医枠) | 私立 | 1名(1年次) | 2024/11/16〜11/22 | 11/30(1次) | 12/8(2次) | 基礎学力テスト(1次)、個人面接・志望理由書(2次) |
| 獨協医科大学 | 私立 | 3名以内(1年次) | 2024/9/2~9/13 | 9/28(1次) | 10/12(2次) | 適性試験・小論文・書類審査(1次)、プレゼン・面接(2次) |
| 久留米大学 | 私立 | 約2名(1年次) | 2024/11/1~11/7 | 11/16 | 同左 | 基礎学力テスト・小論文・面接 |
| 東京医科大学 | 私立 | 2名以内 | 2024/10/21~11/1 | 11/30 | 同左 | 基礎学力検査・小論文(日本語・英語)・面接 |
第3章 医学部学士編入の「倍率」は?

「医学部学士編入の難易度はどのくらいですか?」これは、受験を考えるすべての人が抱く疑問でしょう。この章では、その「難易度」を感覚的な言葉ではなく、客観的なデータ、特に 「倍率」 という指標を用いて具体的に解き明かしていきます。
3-1. 難易度は「募集人数の少なさ」と「受験者層の質の高さ」で決まる
医学部学士編入の難易度は、主に2つの要素の掛け算で決まります。
- 募集人数の少なさ : 多くの大学で定員は5名、多くても10~15名という「絶対的な枠の少なさ」。
- 受験者層の質の高さ : 様々な分野で高い専門性を身につけ、医師になるという強い意志を持った優秀な人材が全国から集まること。
この構造が、必然的に高い競争率、すなわち「高倍率」を生み出します。倍率は、その年の受験者数によって変動しますが、試験の相対的な難しさを示す最も直接的な指標と言えます。
筑波大学の合格者である佐々木さんも、試験会場で人の多さを見て次のように感じたと語っています。
やっぱり合格できる人数が少ないので、自分は本当に合格できるんだろうかといった不安が常にあって、どうせ無駄になるんだったらやめてしまおうかなと思う時がけっこうありました。(引用:https://spring-online.jp/column/2764/)
3-2. 各大学の倍率推移から見る競争の現実
単年度の倍率だけを見て「この大学は狙い目だ」と判断するのは危険です。大学の人気や試験内容の変更によって、倍率は年々変動するため、過去数年間のトレンドを把握することが重要です。
以下の表は、各大学の過去の倍率推移を示したものです。これにより、常に高い競争レベルを維持している大学や、比較的変動が大きい大学の傾向を読み取ることができます。
このデータから分かるように、どの大学も一貫して 10倍を超える高い倍率 であり、合格することがいかに困難であるかが客観的に理解できます。「10人から20人に1人しか合格できない」という厳しい現実を直視し、覚悟を持って対策に臨む必要があります。
| 大学名 | 令和6年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
| 北海道大学 | 14.4 | 17.2 | 12.6 |
| 旭川医科大学 | 14.3 | 12.9 | 11 |
| 弘前大学 | 7.9 | 11.6 | 10.3 |
| 群馬大学 | 14.1 | 14.1 | 14 |
| 筑波大学 | 14.7 | 12.6 | 18.2 |
| 東京医科歯科大学 | 12.8 | 8.7 | 11.6 |
| 金沢大学 | 9.6 | 14.2 | 37.8 |
| 富山大学 | 15.1 | 26.1 | 44 |
| 福井大学 | 18.6 | 34.5 | 39.8 |
| 名古屋大学 | 35 | 17.5 | 22.2 |
| 浜松医科大学 | 18 | 22 | 22.3 |
| 滋賀医科大学 | 14.8 | 18.7 | 21.4 |
| 大阪大学 | 8.7 | 8.8 | 16 |
| 神戸大学 | 12.7 | 14 | 21.5 |
| 島根大学 | 5.4 | 9.4 | 5.3 |
| 山口大学 | 21.6 | 24.7 | 25.6 |
| 香川大学 | 14.6 | 7 | 17.6 |
| 高知大学 | 5.7 | 14.3 | 38.5 |
| 愛媛大学 | 8.6 | 22 | 22 |
| 鹿児島大学 | 22.8 | 16.3 | 18.7 |
| 大分大学 | 21.8 | 22.2 | 24.4 |
| 長崎大学 | 27.6 | 34.8 | 34 |
| 琉球大学 | 27.6 | 19.1 | 32.8 |
| 東海大学 | 23 | 21.3 | 16.8 |
| 北里大学 | 11.3 | 1.7 | – |
| 金沢医科大学 | 15.4 | 10.5 | – |
| 岩手医科大学 | 4.3 | 4 | 5.8 |
参照: https://www.seiko-lab.com/courses/transfer/medicine/results/
第4章 先輩たちはどうやって合格した?

学士編入試験は、受験者のバックグラウンドが多岐にわたるのが大きな特徴です。画一的な対策法が存在しないからこそ、自分と境遇が近い先輩の経験は、何よりも価値のある道しるべとなります。
ここでは、実際に合格を掴んだ先輩たちが、どのような経歴を持ち、どのように試験を乗り越えたのか、そのリアルな声と戦略を具体的に紹介します。
4-1. 理系(物理・工学)出身者の合格戦略
生命科学とは異なる分野の理系出身者は、専門外の科目をどうキャッチアップし、自身の強みをどう活かしたのでしょうか。
ケース1:秋田大学医学部合格 櫻井さん(地方国立大学 工学部 物理学専攻)
櫻井さんは、就職活動の自己分析を通じて医師という道を志し、医学部編入を決意しました。
自分のやりたいことは医者と医師として患者さんの治療を行うことだと気づき、医学部に入ってからも使える知識で受験ができる学士編入が最適だと思い、目指しました。(引用:https://spring-online.jp/column/2886/)
工学部で物理学を専攻していたため、生命科学はほぼ初学の状態からのスタートでした。就職活動と並行しながら、 約10ヶ月間 、予備校などは利用せず独学で勉強を進め、見事合格を掴みました。櫻井さんの合格の鍵は、ストイックな時間管理にありました。
自分の時間の使い方をかなりストイックに管理しておりまして、メモに何時に何をして、勉強はどのくらい行ったのを記録して、この時間勉強できたなっていう風に気づきを得ることで、無駄な時間を減らすように意識しておりました。
ケース2:筑波大学・高知大学医学部合格 にゅーとんさん(物理学科専攻)
にゅーとんさんも物理学科に在籍しながら、 約1年間の勉強 で2つの国公立大学から合格を得ました。彼は、医学部編入で最も重要視されるのは「決意の固さ」だと語ります。
なんだかんだで編入試験で一番重要なものは、この時の決意の固さだと思います。僕には3日坊主ぐせがあるので、この決意が最後まで続くか非常に不安でした。なので、後戻りできないようにいろいろ手を打ちました。1年間勉強して何が何でも受験だけはすると決めました。(引用:https://spring-online.jp/column/59/)
理系出身者にとって、大学の授業や研究との両立も大きな課題です。にゅーとんさんは、大学院入試の対策と並行しながら、独自の学習スタイルを確立していました。
授業もバイトもあったうえ、朝早く起きて勉強することが苦手だったため、友達と馴れ合うのを極力避けるようにしました。具体的には、食堂、教室、放課後のあらゆるところでぼっちを極めました。
4-2. 生命科学系(薬学・製薬)出身者の合格戦略
生命科学系のバックグラウンドを持つ受験生は、その知識を大きなアドバンテージとして活かすことができます。
ケース3:神戸大学医学部合格 Aさん(薬学部→修士→製薬企業研究職)
Aさんは、薬学部、修士課程を経て、製薬企業で3年間研究職として勤務していました。その経歴は、編入試験において強力な武器となりました。
自分は薬学系出身、かつ大学4年生から研究室配属となり、医学系の英語論文を日頃から読んでいましたし、会社でも生命科学系の研究に従事していたため、受験を決めた当初から英語と自然科学系の分野でかなりのアドバンテテージがあったように思います。(引用:https://spring-online.jp/column/2701/)
このアドバンテージを活かし、Aさんは受験を決意してから 約半年という短期間 で合格を手にしました。彼の戦略は、自身のバックグラウンドが最も評価される大学に絞って受験することでした。
受験校選定に関しても、研究業績が使用できる+製薬企業研究職というキャリアが有利に働くのがこの2校(名古屋大学、神戸大学)だったためです。
4-3. 文系・社会人出身者の合格戦略
文系出身者にとって、生命科学をはじめとする理系科目は非常に大きな壁となります。そのハンデを、彼らはどのように乗り越えたのでしょうか。
ケース4:金沢大学医学部合格 島貫さん(経済学部→製薬会社MR)
島貫さんは経済学部を卒業後、製薬会社でMR(医薬情報担当者)として勤務していました。MRとして臨床医とディスカッションする中で、より深く医学を学びたいという思いが強くなり、受験を決意します。
医学部受験を決意してからは、一般受験(所謂再受験)と学士編入受験で悩みました。(中略)勉強のスタートラインにおける数学・物理・化学・生物の完成度が低すぎたため、より短い期間で合格する可能性のある学士編入受験に切り替えました。(引用:https://spring-online.jp/column/2890/)
彼は会社を退職し、 1年間勉強に専念 。物理・化学の経験がなかったため、 試験科目に物理・化学を必要としない大学群(2科目受験校)に志望校を絞る という明確な戦略を取りました。そして、理系科目のハンデを克服するため、河合塾KALSの通信講座を受講し、計画的に学習を進めました。
勉強を始めるにあたりまずは合格までの道筋のオリエンテーションをつけることだと感じ、有識者(KALSの講師・チューター)にカウンセリングを申し込み、私のバックグラウンドに対して適切な志望校を選定しました。
ケース5:国公立大学医学部合格 Bさん(私立文系大学出身)
Bさんは、文系の大学での課外活動をきっかけに医療への関心を深め、医学部編入という道を選びました。
私が医療に興味を持つようになったのは、課外活動での経験からです。もともと医療とは無縁の生活でしたが、自分の将来を考える中で、“医療現場での課題を知り、それを何とかしたい!!”と思うようになりました。(引用:https://spring-online.jp/column/2916/)
文系出身であることに加え、周囲の友人が就職活動を進める中での孤独な戦いでしたが、強い意志を持って挑戦し、見事合格を果たしました。Bさんの体験談は、バックグラウンドに関わらず、強い動機があれば道は開けることを示しています。
第5章 【科目別】医学部学士編入対策ロードマップ

ここからは、合格を掴むための具体的な「対策」について、先輩たちが実践した勉強法や使用した教材を交えながら、科目別に詳しく解説していきます。
5-1. 最重要科目「生命科学」は頻出分野の深い理解が合格の鍵
医学部学士編入の合否は、生命科学の出来で決まると言っても過言ではありません。全ての受験生が最も時間をかけて対策するこの科目を、いかに効率よく、かつ深く学習するかが合格への鍵となります。
出題傾向は「分子生物学」「細胞生物学」「生化学」に偏っている
まず、敵を知ることが重要です。生命科学の出題範囲は広大ですが、編入試験においては明確な傾向が存在します。
- 頻出分野 : 出題は 「分子生物学」「細胞生物学」「生化学」 の3分野に大きく偏っています。これらの分野は、現代医学の根幹をなすため、特に重点的に問われます。
- 非頻出分野 : 逆に、同じ生物学でも「植物学」や「生態学」「分類学」といった分野からの出題はほとんどありません。限りある学習時間を、これらの分野に割くのは非効率的です。
- 問題形式 : 基礎的な知識を問う問題が中心ですが、大阪大学や東京科学大学のようなトップレベルの大学では、 最新の研究論文を題材とした長文の実験考察問題 が出題される傾向にあります。これは単なる暗記では対応できず、実験のロジックを読み解き、論理的に考察する能力が求められます。
合格者が実践した勉強法と推奨リソース
多くの合格者が実際に使用してきた信頼性の高い教材と、具体的な勉強法を紹介します。
【初学者・文系出身者向け】
まずは高校生物の範囲を完璧にすることが全ての土台となります。
- YouTube講義「Try it(トライイTット)」神戸大学の合格者は、「高校生物の教材としては、Try itの映像授業をYouTubeで観ていました (2倍速で植物、進化以外の範囲)。わかりやすくて無料なので、とりあえずどうしようという方にお勧めです」と語っています。筑波大学合格のにゅーとんさんも、この動画をスマホで見て勉強をスタートさせました。
- 『はじめの一歩の生化学・分子生物学』(羊土社)複雑な生命現象をイラストや図を多用して分かりやすく解説しており、最初の1冊として最適です。
【中核テキスト・問題集】
多くの受験生が学習の軸として利用しているのが、医学部編入予備校である河合塾KALSの教材です。
- 河合塾KALSのテキスト・問題集(要項集、テストバンクなど)独学で合格した受験生の中にも、「KALSのテキスト一式をメルカリで購入しました。10万円くらいでした」「模試とテストバンク以外KALSは利用しませんでした。1年目落ちたら行こうと思ってました」という声があり、その質の高さがうかがえます。金沢大学に合格した島貫さんは、「まずはKALSの動画講義を視聴し、テキストの問題演習をこなしました。受験する年の1月から勉強を開始したため、動画を視聴する際は1.5倍速で視聴してタイムパフォーマンスを重視しました」と、具体的な活用法を語っています。
- 『医学部編入への生命科学演習』(講談社)KALSの講師陣が執筆しており、編入試験のレベルに合った良質な演習問題を数多く収録しています。アウトプットの練習に必須の1冊です。
- 『プログレッシブ生命科学』(南山堂)ある国公立大学の合格者は、「生命科学に関する成書としては、『プログレッシブ生命科学 南山堂』も、理解を深めるために読み勧めておりました」と、補助教材としての有用性を述べています。
5-2. 「英語」はTOEIC/TOEFLの戦略的選択が重要
英語は、生命科学と並ぶもう一つの重要な柱です。単なる語学力だけでなく、受験戦略そのものが問われます。
スコアは「足切り」か「点数換算」のどちらかに使われる
大学側がTOEICやTOEFLのスコアを利用する方法は、大きく分けて2つあります。
- 足切り(出願資格) : 特定のスコア(例:TOEIC 750点以上)を出願の最低条件として設定するケース。この基準をクリアしない限り、どれだけ生命科学の成績が良くても出願すらできません。
- 点数換算 : 取得したスコアを大学独自の基準で点数化し、他の科目(生命科学や面接)の点数と合算して総合評価の一部とするケース。この場合、スコアは高ければ高いほど有利になります。
どちらの方式を採用しているかは大学によって異なるため、志望校の募集要項を熟読することが不可欠です。
志望校に応じてTOEICかTOEFLかを選ぶ必要がある
この選択は、あなたの志望校リストを事実上、事前にフィルタリングする行為に他なりません。
- TOEFLが必須の大学 : 東京科学大学(旧医科歯科大)や岡山大学といったトップレベルの大学は、TOEFLのスコア提出を義務付けています。
- TOEICが利用可能な大学 : 一方で、香川大学や島根大学などはTOEICスコアを要求します。
- 一般的な傾向 : 日本の受験生の多くは、リスニングとリーディングのみで構成されるTOEICの方が、スピーキングとライティングが加わるTOEFLよりも高スコアを取りやすいと感じています。
文系出身の合格者は、自身の英語戦略について次のように語っています。
TOEICは700点台前半、TOEFLは持っていません。(受験料が高すぎる!!のと、純ジャパがSpeaking と Writingである程度戦える点数を取得するには、膨大な学習時間がかかると判断して、TOEFLの学習は諦めました)(引用:https://spring-online.jp/column/2916/)
最初に決めるべきは「暫定的な志望校リスト」です
ここでの最も重要なアドバイスは、 「英語の勉強を本格的に始める前に、まず暫定的な志望校リストを作成すること」 です。
もしあなたの第一志望がTOEFL必須の東京科学大学なのであれば、迷わずTOEFLの対策に全力を注ぐべきです。逆に、TOEFLが必須ではない大学群を主なターゲットとするのであれば、より高スコアを狙いやすいTOEICに集中し、点数換算で有利な状況を作り出す戦略が有効かもしれません。
筑波大学に合格したにゅーとんさんは、KALSの説明会で得た情報が自信につながったと語ります。
一番の収穫はKALSの掲示物をチラ見したときに「最終合格者のTOEIC平均が850点」だと知ったことです。(中略)たまたま自分がこの点数を超えていたこともあり、自信が持てるようになりました。(引用:https://spring-online.jp/column/59/)
主要大学の英語試験一覧表
| 大学 | TOEFL | TOEIC | 出願要件 |
| 北海道大学 | ○ | ○ | TOEFL: 71点, TOEIC: 680点 |
| 弘前大学 | ○ | × | – |
| 東京科学大学 | ○ | × | TOEFL: 80点 |
| 群馬大学 | × | × | – |
| 筑波大学 | ○ | ○ | – |
| 名古屋大学 | ○ | ○ | – |
| 富山大学 | ○ | ○ | – |
| 金沢大学 | ○ | × | – |
| 大阪大学 | ○ | ○ | – |
| 島根大学 | × | ○ | TOEIC: 600点 |
| 岡山大学 | ○ | × | TOEFL: 60点 |
| 香川大学 | × | ○ | TOEIC: 600点 |
| 愛媛大学 | × | ○ | TOEIC: 600点 |
| 高知大学 | ○ | ○ | – |
| 長崎大学 | ○ | ○ | TOEFL: 42点, TOEIC: 1150点(S&W含む) |
| 鹿児島大学 | ○ | ○ | TOEFL: 64点, TOEIC: 720点 |
| 琉球大学 | ○ | ○ | TOEFL: 61点, TOEIC: 600点 |
第6章 小論文・面接の対策

筆記試験を突破した先に待ち受けるのが、小論文と面接です。これらの試験では、単なる知識量ではなく、あなたの思考力、倫理観、コミュニケーション能力、そして医師としての適性といった、 「人間性」 が総合的に評価されます。
6-1. 小論文は頻出テーマの自分なりの意見を準備しておくこと
小論文では、現代医療が抱える様々な課題について、あなた自身の考えを論理的に記述する能力が求められます。付け焼き刃の知識では対応できないため、日頃から医療関連のニュースに関心を持ち、自分なりの意見を構築しておく訓練が必要です。
金沢大学に合格した島貫さんは、小論文対策について次のように述べています。
小論文はある程度書き方の型を押さえて、医学部小論文で頻出のトピックについてKALSの動画講義で学習しました。勉強時間としては多くないです。息抜きがてら、生命科学や英語の勉強の合間に小論文の勉強をするようにしていました。いかに尖った意見を書きすぎないようにしつつも自分の意見を主張していくかというバランス感覚が問われます。(引用:https://spring-online.jp/column/2890/)
頻出テーマは「生命倫理」「医療制度」「医療の未来」
過去の出題傾向から、テーマは大きく3つに分類できます。
- 生命倫理 : 終末期医療(尊厳死、安楽死)、生殖補助医療(体外受精、代理出産)、インフォームド・コンセントなど。
- 医療制度・社会問題 : 医師の地域偏在、医療費増大、少子高齢化、パンデミックなど。
- 医療の未来 : AI(人工知能)の活用、ゲノム編集などの先端技術の倫理的課題、遠隔医療など。
これらのテーマについて、賛成・反対の両方の立場から論点を整理し、800字~1200字程度で自分の意見をまとめる練習を繰り返しましょう。
6-2. 面接は「なぜ今、医師を目指すのか」を明確に語れることが重要
面接は、あなたが提出した書類だけでは分からない「人となり」を評価する場です。特に、多様なバックグラウンドを持つ学士編入受験生に対しては、 「なぜ、今、医師を目指すのか?」 という動機が最も深く問われます。
志望動機作成で意識すべき3つのポイント
神戸大学に合格した社会人の方は、大学に提出する志望動機書を作成する上で、以下の3点を強く意識したと語っています。
① とにかく自分の経歴や経験を志望動機と紐づけること
② やりたいことが明確で、それが医者でなければできないことである
③ 大学が臨床医を望んでいるのか研究医を望んでいるのか見極めること
そして、「よく聞かれる質問として、『それをやるのはあなたじゃないといけないの?』、『それは医師じゃないと出来ないの?』があります。この2つに答えるためにしっかり①、②の内容は志望理由に盛り込んでください」とアドバイスしています。
面接のリアルな体験談
実際の面接はどのような雰囲気で、何が聞かれるのでしょうか。筑波大学に合格したにゅーとんさんの体験談は、面接の臨場感を伝えてくれます。
2日目の面接は、けっこう対策していったので、特に何もなく終わることができました。って書こうとしてたんですけど嘘でした。面接試験の直前に自分の志望理由書を確認している時のこと、、筑波大学と書くべき場所が高知大学になっていることに気付いてました。手抜き志望理由書がばれてしまわないか内心ハラハラでしたが、幸い突ッ込まれることが無かったので良かったです!
面接官は確か、分子生物学を研究している方と救急救命医をやっていらっしゃる方でした。(中略)将来臨床医を目指していると伝えると、医師となる時にどんなことに気を付けたいかを聞かれたので、「科学が当たり前の医師と違って患者さんにとって医療がえたいのしれない不安なものである事も少なくないと思うので、そのことを十分に考慮しつつ、患者さんによりそった医療を実践していきたいです」と答えました。自分の卒業研究についても詳しく聞かれました。(引用:https://spring-online.jp/column/63/)
この体験談からは、志望理由書の細かなチェックの重要性と、自身の研究内容や医師像について深く掘り下げて質問されることが分かります。
第7章 受験生の悩みと乗り越え方
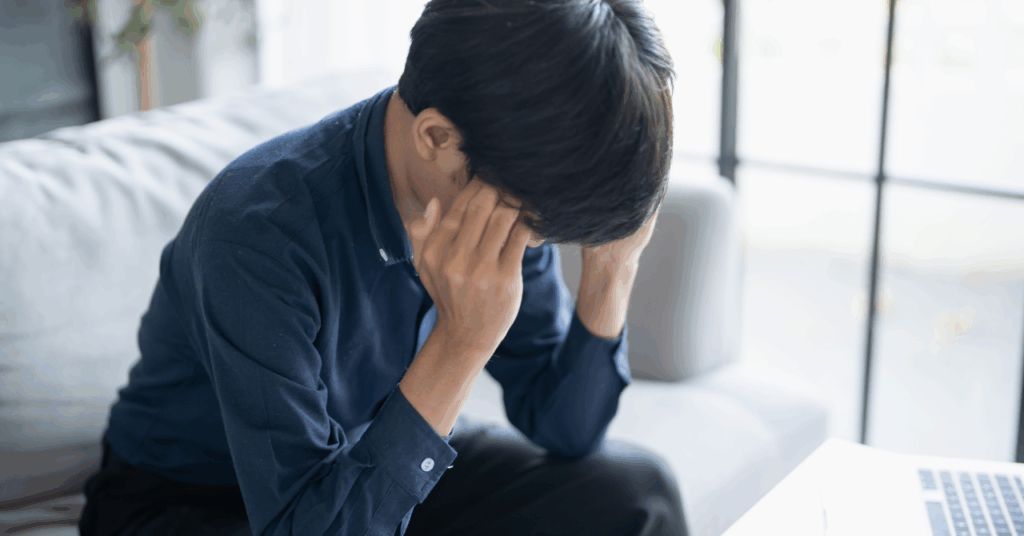
医学部学士編入への道は、学力だけでなく、精神力も問われる孤独な戦いです。ここでは、先輩たちが実際に直面した悩みと、それをどう乗り越えたのか、具体的なエピソードと共に紹介します。
7-1. 「情報が少ない」問題とどう向き合ったか
学士編入試験は情報戦です。しかし、その情報は非常に限られています。
ネットで「医学部学士編入」と調べても予備校の一つであるKALSのホームページや合格体験記、学習法を書いた有料noteが上段に来るぐらいでしょうか、、、本当にどれだけ探しても情報が見つかりません。過去問も大学が公表しているところはほぼ皆無に等しく、フリマサイトで売られているのを見かけるぐらいです。(引用:https://spring-online.jp/column/2916/)
このように、多くの受験生が情報の海で途方に暮れるところからスタートします。合格者たちは、予備校が開催する無料説明会に足を運んだり、合格者のブログを隅々まで読み込んだり、SNSを活用したりして、必死に情報をかき集めています。
なお、スプリング・オンライン家庭教師では、医学部学士編入を専門とする医学部学士編入経験者や医学部生で構成されるプロ講師陣が、豊富に蓄積された情報をもとに受験生のサポートにあたっています。
7-2. 「本当に合格できる?」という不安との戦い
合格者数が極端に少ないため、「本当に自分は合格できるのだろうか」という不安は、受験期間中ずっとつきまといます。
どんな受験でもこの不安と戦いながら、勉強を進めることにはなりますが、学士編入試験があまりにブラックボックスすぎるが故に、より一層この不安が強くありました。(中略)この不安に打ち勝つには、当たり前のような回答にはなりますが、とにかく正しいやり方で勉強し続けるのが一番です。筆記試験に初めて合格した時に、もしかしたら、合格できるかもしれない… とようやくそこで一縷の望みが生まれました。(引用:https://spring-online.jp/column/2899/)
この不安を乗り越えるため、多くの合格者が「期限を設ける」という方法を取っていました。
やる気次第で何年でも続けられる試験です。だからこそ、だらだらと続けてしまうリスクもあります。そこで私は受験を始めて2年で決着がつかなければ、医師の道は諦めると覚悟していました。そうした期限を設けたことによって、締め切り効果で頑張れたようにも思います。
筑波大学に合格した佐々木さんも、「2年は受験をやり切ることを意識していました」と語っており、期間を決めて集中することが重要であると分かります。
7-3. 学歴や経歴は合否にどれくらい関係するのか
「合格者は東大、京大、早慶などの高学歴な人ばかりなのでは?」という不安を抱く方は少なくありません。しかし、この点について、 複数の合格者が「学歴は重要なファクターではない」と断言しています 。
私自身、国立大学出身ではないですし、確かに東大生、京大生、早慶生も多数いますが、他の大学出身の方もそれなりにいます。これは私の主観にはなりますが、学歴は学士編入において重要なファクターではないと考えています。 なので、学歴を気にされる方は、その分、筆記試験でしっかり点数を取り、医学部の勉強についていけることをしっかりアピールできると良いと思います。(引用:https://spring-online.jp/column/2899/)
大学の成績(GPA)や留年歴についても同様です。
大学のGPAについてですが、これも低くかろうが、留年歴があろうが、関係ないと考えています。(中略)実際に、2回の留年を経験している方も合格されているので、本当に心配無用です。
大切なのは過去の経歴そのものではなく、その経験から何を学び、将来医師としてどう活かしていきたいのかを、自分の言葉で論理的に語れることです。
7-4. 仕事や学業との両立、そして莫大な費用
社会人や学生にとって、勉強時間の確保は最大の課題です。
- タイムマネジメント秋田大学の合格者、櫻井さんは、「自分の時間の使い方をかなりストイックに管理しておりまして、メモに何時に何をして、勉強はどのくらい行ったのを記録して(中略)無駄な時間を減らすように意識しておりました」と、徹底した自己管理で勉強時間を捻出しました。(引用: https://spring-online.jp/column/2886/ )
また、見過ごせないのが 金銭的な負担 です。
- 受験費用
編入試験は膨大なお金がかかります。どのぐらいお金を費やせるのか、あらかじめ計算しておいて損はありません。現在、1大学あたり受験料は一律3万円です。3~10校ぐらいを受ける方が多いので、仮に10校受けたとするとそれだけで30万円の出費となります。多くの方は交通費+前泊費用がかさむことになります。(引用: https://spring-online.jp/column/2916/ ) - 生活費
金沢大学に合格した島貫さんは、退職して受験に専念しましたが、その厳しさをこう語っています。「私の場合は貯金の300万円を切り崩して受験生活をしていましたが、たいぶカツカツで余裕がありませんでした。なるべく退職はせずに受験勉強することができればベストです。」(引用: https://spring-online.jp/column/2890/ )
7-5. 長期戦を乗り切るための息抜き方法
受験は長期戦です。心身の健康を維持し、モチベーションを保つための息抜きは不可欠です。先輩たちは、自分なりの方法でリフレッシュしていました。
- ① よく寝る、② たまには遊ぶ
「私の受験期間はトータルで1年8ヶ月ほどでしたが、その期間ずっと勉強に猛進していたわけではありません。(中略)1ヶ月に1回ぐらいは、家族や友達と遊ぶ約束をして全く勉強しない日をあえて作り、そこでしっかり息抜きをすることで、また次の日から頑張ろうと意気込んでいました。」(引用: https://spring-online.jp/column/2899/ ) - ③ 医療系ドラマを視聴して、自分を鼓舞する
「医学部を目指されているのであれば、一度は医療系ドラマを見て、かっこいい!! と思ったことがあるのではないでしょうか。私は『コードブルー-ドクターヘリ緊急救命-』が一番好きで、(中略)勉強のやる気が出ないときに医療系ドラマを見ると、なぜ医師になりたいと考えるようになったのか、自然と思い出されるので、そこから再び勉強に励むことができました。」 - ④ 泣いてストレス発散、⑤ ランニング
「泣くとストレスが解消されるというのはよく言われていますが、私もそれを大いに活用していた一人でした。(中略)ずっと座ったままで勉強していると、腰や肩、首周りが凝ってしまうので、夕方以降涼しくなってから、週2程度でランニングをしていました。」
医学部学士編入合格をより確実なものに

この記事では、医学部学士編入という、険しくも価値ある道を目指すすべての方々のために、最新の入試情報と、実際にその道を乗り越えてきた先輩たちのリアルな声をお届けしました。
医学部学士編入は、募集人数の少なさと受験者層のレベルの高さから、極めて 難易度 の高い試験であることは間違いありません。しかし、 日程 を上手く組み合わせることで複数の大学に挑戦でき、 TOEIC などの英語試験で戦略的にアドバンテージを築き、過去の 倍率 データから現実的な志望校選定を行うことで、合格の可能性は着実に高まっていきます。
この長いガイドを最後までお読みいただいたあなたは、医学部学士編入の全体像を深く理解し、合格に向けた具体的な第一歩を踏み出す準備が整ったはずです。
この情報が、あなたの「医師になる」という夢を実現するための一助となることを、心から願っています。
もし、あなただけのバックグラウンドに合わせた専門的な学習戦略や、志望理由書の作成、面接対策など、よりパーソナルなサポートが必要だと感じた場合は、ぜひ一度 「スプリング・オンライン家庭教師」の無料相談 をご利用ください。
大阪大学 や 東京科学大学(旧・東京医科歯科大学) 、 北海道大学 などをはじめ数々の医学部学士編入試験で合格者を輩出してきたプロ講師陣が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、合格までの最短ルートを一緒に考えます。現在、 公式LINE にご登録いただいた方限定で「 医学部学士編入の合格率を劇的にアップさせる映像授業 」計6本をプレゼント中です。ぜひこの機会にご登録ください。