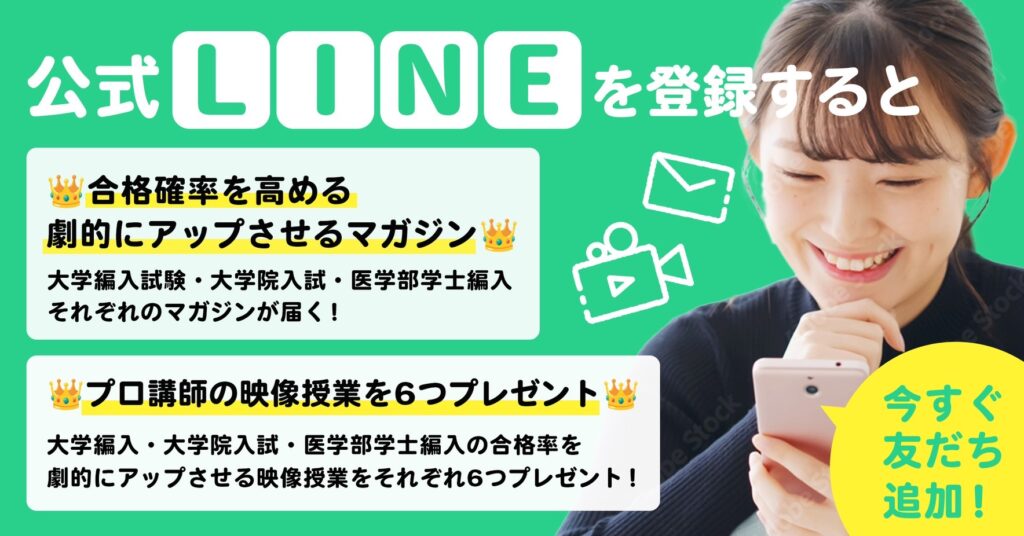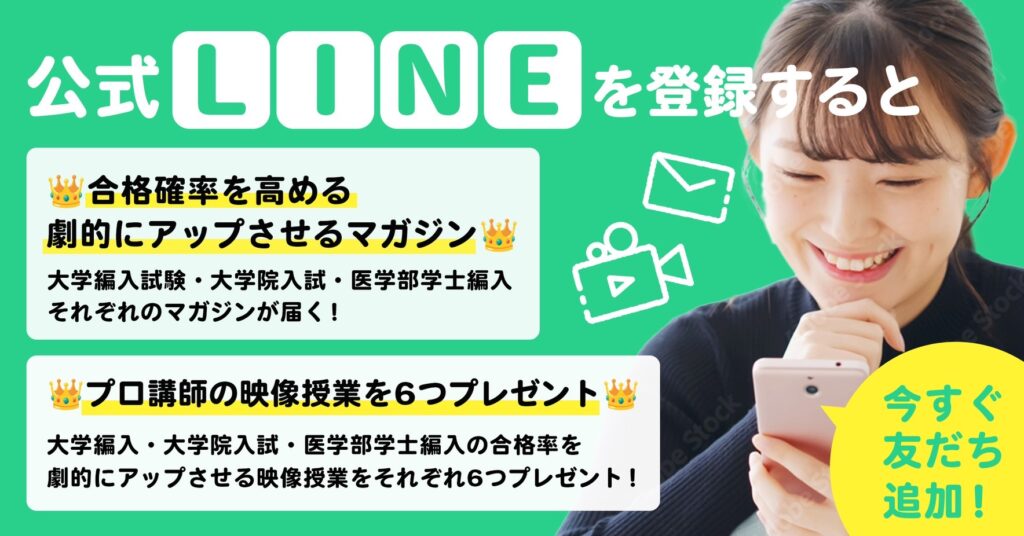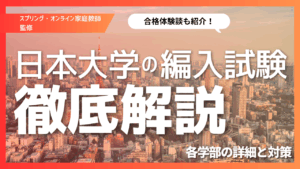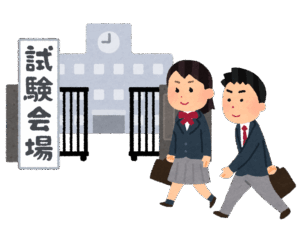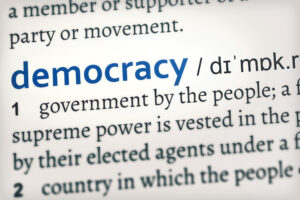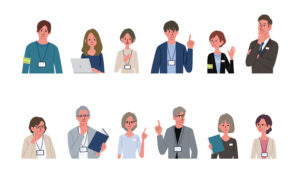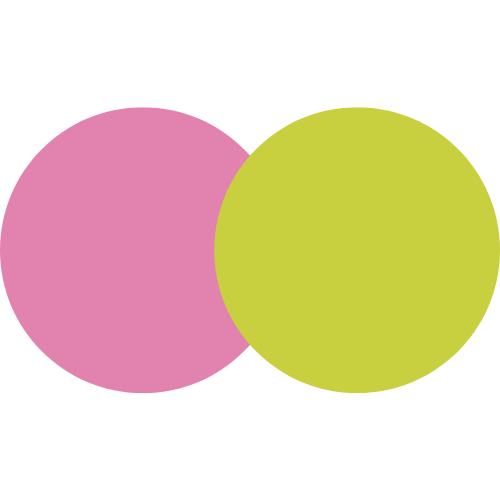ご質問やお問い合わせはお気軽に
日本大学文理学部の編入試験を徹底解説|概要から具体的な対策まで

「日本大学文理学部への編入を考えているけれど、情報が少なく、何から手をつければいいか分からない」
「合格者数や倍率が非公開で、試験の難易度が掴みにくい」
「専門科目の対策は、どのレベルまで必要なのだろうか」
日本大学文理学部の編入試験を目指す方にとって、こうした悩みは共通のものかもしれません。編入試験は一般入試と比べて情報が限られているため、対策の第一歩でつまずきやすいのも事実です。
この記事では、最新年度の募集要項に基づき、試験の全体像から、各学科の試験科目、そして気になる専門科目や面接の対策のポイントまで、受験生の方が知りたい情報を整理して解説します。
日本大学文理学部の編入試験について、具体的な相談をしたい方や状況に合わせた受験戦略を検討したい方は、編入試験のプロに相談することがおすすめです。日本大学の編入試験の合格実績が豊富なスプリング・オンライン家庭教師のプロ講師があなたに最適な受験プランをご提案します。
\公式LINEで豪華6大特典をプレゼント中!/
日本大学文理学部 編入試験の概要(試験日程・募集学科)
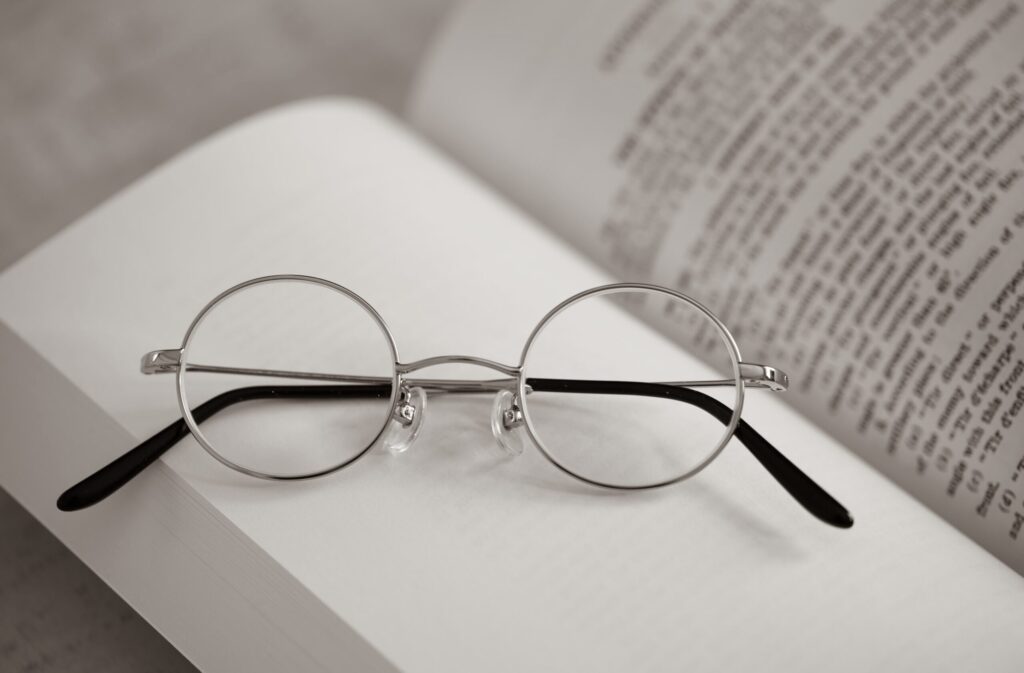
まずは、試験の全体像を把握することから始めましょう。ここでは、2026年度の募集要項を参考に、基本的なスケジュールや募集内容を確認します。
日本大学文理学部 編入試験のスケジュール
編入試験の準備は、スケジュール管理が重要です。最新の募集要項を参考に、ご自身の計画を立ててみてください。
| イベント | 日程(2026年度入試) |
|---|---|
| 資格審査受付期間(※対象者のみ) | 2025年9月8日(月)~9月12日(金) 【必着】 |
| 出願期間 | 2025年10月14日(火)~10月24日(金) 【必着】 |
| 試験日 | 2025年11月8日(土) |
| 合格発表日 | 2025年12月1日(月) (本人宛に発送) |
(注:上記は2026年度募集要項の参考情報です。受験される年度の最新情報を必ず公式サイトでご確認ください。)
編入できる学科と年次は?
文理学部では、多くの学科で編入の門戸が開かれていますが、学科によって募集年次(2年次・3年次)が異なる点に注意が必要です。
- 2年次編入: 全18学科で募集があります。
- 3年次編入: 一部の学科(社会学科、社会福祉学科、体育学科、地球科学科)では募集が行われていません。
ご自身が希望する学科が、希望する年次で募集を行っているか、必ず確認しましょう。
出願資格をチェック
基本的な出願資格は以下の通りです。
- 2年次編入:
- 大学に1年以上在学し、34単位以上を修得(見込み)の者。
- 短期大学、高等専門学校を卒業(見込み)の者。 など
- 3年次編入:
- 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得(見込み)の者。
- 短期大学、高等専門学校を卒業(見込み)の者。 など
(※詳細は必ず最新の募集要項でご確認ください。)
全18学科の試験科目を比較
文理学部の編入試験は、基本的に「外国語」「学科指定科目」「口頭試問」の3つで評価されます。学科ごとに「募集年次」と「試験科目」が異なりますので、ここで一目で比較できるように整理しました。
【日本大学文理学部 編入学試験科目一覧】
| 学科名 | 募集年次 | 外国語科目 | 学科指定科目 | 口頭試問 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学科 | 2・3年 | 選択 | 哲学・倫理学・美学・宗教学から1科目選択 | あり |
| 史学科 | 2・3年 | 選択 | 歴史学 | あり |
| 国文学科 | 2・3年 | 選択 | 日本語学・日本文学 | あり |
| 中国語中国文化学科 | 2・3年 | 中国語必須 | 中国文化一般 | あり |
| 英文学科 | 2・3年 | 英語必須 | 英語学・英米文学の基礎知識 | あり(英語含む) |
| ドイツ文学科 | 2・3年 | 選択 | ドイツ語・ドイツ事情(日本語) | あり |
| 社会学科 | 2年のみ | 選択 | 社会学 | あり |
| 社会福祉学科 | 2年のみ | 選択 | 社会福祉学 | あり |
| 教育学科 | 2・3年 | 選択 | 教育学(基礎知識) | あり |
| 体育学科 | 2年のみ | 選択 | 保健体育一般 | あり |
| 心理学科 | 2・3年 | 選択 | 心理学(英語による出題を含む) | あり |
| 地理学科 | 2・3年 | 英語必須 | 地理学の基礎知識 | あり |
| 地球科学科 | 2年のみ | 英語必須 | 地学 | あり |
| 数学科 | 2・3年 | 英語必須 | 2年次:数学(微分・積分, 線形代数, 論理・命題) 3年次:上記に学科専門科目を追加 | あり |
| 情報科学科 | 2・3年 | 英語必須 | 2年次:数学(微分・積分, 線形代数)、プログラミング(Processing) 3年次:数学(微分・積分, 線形代数)、プログラミング(C言語) | あり |
| 物理学科 | 2・3年 | 英語必須 | 数学(微分・積分, 線形代数) | あり |
| 生命科学科 | 2・3年 | 英語必須 | 生物 | あり |
| 化学科 | 2・3年 | 英語必須 | 化学 | あり |
- 外国語科目の「選択」について: 哲学科、史学科、国文学科、ドイツ文学科、社会学科、社会福祉学科、教育学科、体育学科、心理学科は、「英語・ドイツ語・中国語のうち1か国語選択」です。(詳細は募集要項をご確認ください)
- 出典: 2026年度日本大学文理学部編入学試験募集要項
日本大学文理学部 編入試験の難易度と傾向

「結局のところ、合格するのはどれくらい難しいのか?」 これは、受験生の方が最も知りたい点の一つでしょう。
日本大学文理学部の倍率は非公開
日本大学文理学部は、編入試験の倍率や合格者数を公式には発表していません。これは、編入試験の特性と関係しています。
一般入試が主に学力試験の点数で合否を決めるのに対し、編入試験は、受験生一人ひとりの「学習意欲」や「専門分野への適合性」を多角的に評価する場です。大学側は、単にテストの点数が高い学生ではなく、「なぜ本学のこの学科で学びたいのか」「入学後、研究や学習に意欲的に取り組めるか」といった、個々のポテンシャルを見ています。
そのため、単純な倍率という数字では「合格の難しさ」を測ることができず、また大学側もその数字を重視していないため、公表されていないと考えられます。
過去問の傾向から読み解く「学科別の難易度」
難易度は学科ごとに異なります。試験問題の傾向を分析することで、各学科が受験生に求めているレベルが見えてきます。
- 英文学科・心理学科: これらの学科は、外国語の試験(あるいは専門科目内)で、専門分野に関連する長文が出題される傾向があります。特に心理学科は「英語による出題を含む」と明記されており、単なる語学力だけでなく、専門分野の基礎知識を英語で理解できるかどうかが問われます。対策の専門性は高いと言えるでしょう。
- 史学科・哲学科: 史学科では歴史学全般、哲学科では哲学・倫理学など、広範な知識が問われます。過去の出題傾向を見ると、基本的な用語の理解に留まらず、それらの知識を再構成し、特定のテーマについて論理的に説明する力が求められます。
- 数学科・情報科学科: 試験問題は、大学教養レベルの微分積分・線形代数が中心です。特に情報科学科では指定言語によるプログラミングの実装が求められることがあり、知識の正確さと論理的思考力が合否に直結します。
あなたの現在地を確認する5つのチェックリスト
合格の可能性を測るために、ご自身の状況を客観的に振り返ってみましょう。
- 現在の大学での成績(GPA)は、自信を持って提出できますか?
- 編入試験では出身大学の成績証明書が重視されます。学習への真摯な姿勢を示す重要な指標です。
- 志望する学科の専門分野について、基礎的な用語や概念を自分の言葉で説明できますか?
- 例えば、社会学科志望なら「アノミー」「フランクフルト学派」といった基礎的な用語を正確に説明できるでしょうか。
- なぜ今の大学ではダメで、日本大学文理学部の「その学科」でなければならないのか、明確な理由を語れますか?
- これは面接で最も深く問われる核心的な質問です。「なんとなく」では、教授を納得させることはできません。
- 英語力について、大学教養レベルの長文を読む準備はできていますか?
- 特に理系学科や英文・心理学科では、英語で書かれた専門的な文章を読む力が直接的に求められます。
- 志望学科のカリキュラムや、在籍する教授の研究分野について調べたことがありますか?
- 大学への関心の高さ、すなわち「本気度」を示す最も分かりやすい行動です。
もし、現時点で自信を持って「はい」と答えられない項目がある場合には、これらの課題を克服して日本大学文理学部への合格可能性を最大化する必要があります。具体的な懸念や不安がある方はぜひプロ講師に相談して、懸念や不安を解消し、編入試験合格に向けた一歩を踏み出しましょう。
\プロ講師との無料相談会と豪華特典で編入試験を攻略したい方はこちら/
日本大学文理学部 編入試験合格に向けた学習計画と併願戦略

編入試験は、長期的な計画に基づいた準備が鍵となります。
合格から逆算する学習スケジュール例
試験本番の11月をゴールとした場合、どのようなスケジュールで学習を進めればよいか、一例をご紹介します。
| 時期 | フェーズ | 学習のポイント |
|---|---|---|
| 12~9ヶ月前 | 基礎固め期 | 英語:大学受験レベルの単語・文法を完璧に復習する。 専門:概論書・入門書を1冊通読し、全体像を把握する。 その他:情報収集を開始。併願校についても検討を始める。 |
| 8~5ヶ月前 | 応用力養成期 | 英語:専門分野に関連する英文記事や、やや平易な学術文を読み始める。 専門:入門書を完璧にする。 その他:過去問の入手・分析。出題傾向を肌で感じる。 |
| 4~2ヶ月前 | アウトプット・出願準備期 | 英語:長文読解の演習量を増やし、時間配分を意識する。 専門:やや専門書に近い入門書に取り組みつつ、論述問題に着手。答案作成の練習を本格化する。 その他:志望理由書の作成と推敲。面接の準備を開始。 |
| 1ヶ月前~直前 | 最終調整期 | 英語:過去問や類似問題の演習。弱点分野の最終確認。 専門:暗記項目の総復習。複数のテーマで論述練習。 その他:体調管理。本番と同じ時間サイクルで生活する。 |
併願はするべきか?戦略的な大学の選び方
体力的・経済的に可能であれば、戦略的な併願は合格の可能性を高める上で有効な選択肢となります。
併願のメリット:
- 試験本番の独特な緊張感に慣れることができる(場慣れ)。
- 「ここがダメでも次がある」という精神的な余裕が生まれる。
- 合格のチャンスそのものが増える。
併願の注意点:
- 対策の分散: 最も注意すべき点です。試験科目が全く異なる大学を併願すると、準備が中途半端になり、共倒れになる危険性があります。
- スケジュール管理: 出願期間や試験日が重ならないか、常に注意を払う必要があります。
戦略的な併願の考え方: 成功する併願戦略の鍵は、「試験科目に共通性のある大学・学部を選ぶ」ことです。
例えば、日大文理学部の社会学科を目指すのであれば、類似した形式の試験が課される法政大学社会学部や、東洋大学などの日東駒専の学部を併願先に選ぶのが一つの方法です。 数学科や情報科学科であれば、同じく微分積分・線形代数が課される他大学の理系学部が候補になります。
第1章の「試験科目一覧」を参考に、ご自身の得意科目や専門分野を軸に、どのような併願の組み合わせが考えられるか、検討してみてください。
東洋大学の編入試験についても知りたい方はこちら↓

日本大学文理学部 編入試験 科目別(外国語・専門科目・口頭試問)対策ポイント

ここからは、各試験の具体的な対策法を掘り下げていきます。
1. 外国語(英語)の対策
多くの学科で必須となる英語は、専門科目の出来が横並びになった際の、合否を分ける重要な科目となり得ます。
編入試験の英語は、文法知識の正誤を細かく問う問題よりも、専門分野に関連した長文を、制限時間内にどれだけ正確に読み解けるかという、総合的な読解力が重視される傾向にあります。
これは、大学側が「入学後の英語での授業や論文購読についてこられるか」という、実践的な能力を測ろうとしていることの表れです。
学習ステップ:
- 語彙力増強: まずは大学受験レベルの単語帳(例:『ターゲット1900』『システム英単語』など)を完璧に復習します。その上で、より学術的な単語も掲載されている参考書(例:TOEFL対策の単語帳など)に進むと、専門的な文章への対応力が上がります。
- 英文解釈: 複雑な一文を正確に訳す練習を繰り返しましょう。構文を素早く把握する力が、速読・精読の土台となります。
- 長文読解: 基礎が固まったら、多様なテーマの評論文や解説文で演習を積みます。特に、ご自身の志望する学科のテーマ(例:社会学、心理学、物理学)に近い英文を意識的に選んで読むと、背景知識も同時に身につき効果的です。
2. 専門科目の対策
専門科目は、あなたのその学科への「本気度」と「適性」が最も直接的に問われる試験です。過去の出題傾向や募集要項の科目名から、対策のポイントを探ります。
【学科別:専門科目の対策ポイント】
- 社会学科(「社会学」): 過去の傾向では、試験時間60分で大問2題(いずれも論述形式)が出題されています。
- 問1(基礎知識): 「社会学とは何か」を、指定された複数の基本概念(例:ハビトゥス、アノミー、社会的行為など)を用いて説明させる問題。主要な社会学者の理論や基本用語を、正確に理解し、自分の言葉で説明できるかが問われます。
- 問2(応用論述): 「現代日本の社会問題」を一つ取り上げ、社会学の理論を用いて分析・論述させる問題。日頃から社会問題に関心を持ち、「この問題は、社会学的にどう説明できるか」を考える習慣が重要です。
- 対策: 社会学の入門書で基礎を固めると同時に、実際に「書く」練習が不可欠です。
- 情報科学科(「数学」「プログラミング」): 過去の傾向では、試験時間60分で大問3題(数学2題、プログラミング1題)が出題されています。
- 数学(微積分): n回微分、数学的帰納法、 $x^2 \log x$ の微分など、大学教養レベルの計算力が求められます。
- 数学(線形代数): 行列の基本変形、階数(Rank)の計算、連立一次方程式の解法など、基本的な計算問題が中心です。
- プログラミング: 2年次は「Processing」、3年次は「C言語」が指定されています(2026年度入試)。過去には、条件分岐、配列操作、再帰処理など、アルゴリズムの基礎的な実装能力を問う問題が出題されています。
- 対策: 大学1〜2年レベルの微積分・線形代数の教科書や問題集を確実に解けるようにしておくこと。また、指定された言語(特にProcessingは情報系以外では触れる機会が少ないため注意)の基本的な文法とアルゴリズムを習得する必要があります。
- 史学科(「歴史学」): 特定の時代や地域に偏らず、日本史・世界史の広範な知識と、それらを「歴史学」という学問の視点から論理的に再構成する力が求められます。単なる出来事の暗記ではなく、「なぜそれが起こったのか(背景)」「それが後世にどのような影響を与えたのか(意義)」まで含めて論述できるかが評価の分かれ目です。
- 数学科(「数学」): 情報科学科と同様に微分・積分、線形代数が基礎となりますが、さらに「論理・命題」も範囲に含まれます。3年次では専門科目(代数, 幾何, 解析など)が加わり、計算力だけでなく、定理の「証明」レベルまでの深い理解が求められるのが特徴です。
- 心理学科(「心理学(英語含む)」): 心理学の基礎知識(知覚、学習、社会、臨床など)が問われますが、最大の特徴は「英語による出題を含む」点です。心理学の専門用語を英語で理解し、英語で書かれた設問や文章に対応できる準備が必須です。
- その他の学科: 国文学科(日本語学・日本文学)、哲学科(哲学・倫理学)、化学科(化学)、生命科学科(生物)など、各学科の基礎となる科目が指定されています。いずれも大学1〜2年で学ぶ教養レベルの知識を土台に、専門分野の基礎をどれだけ理解しているかが問われます。
専門科目の学習は、一人では「何が正解か」「どのレベルまでやればいいか」が分かりにくいものです。特に論述問題は、書いた答案を客観的に評価してもらうことが上達の近道です。
3. 口頭試問(面接)の準備
筆記試験の点数だけでは測れない、あなたの人間性や学習意欲、将来性といった部分を評価するのが、最終関門である口頭試問(面接)です。
面接官(教授)が見ているポイント:
- 志望動機の本気度: なぜ他の大学・学科ではなく、日本大学文理学部の「この学科」でなければならないのか。
- 学問への適性: 入学後、授業にスムーズについてこられるだけの基礎学力と、自ら学ぶ意欲があるか。
- 将来のビジョン: 編入後の学びを、将来どのように活かしていきたいと考えているか。
【面接質問リスト】頻出の質問
面接での回答に「唯一の正解」はありませんが、準備しておくべき典型的な質問をご紹介します。
- 志望動機について
- なぜ本学の文理学部、そしてこの学科を志望したのですか?
- なぜ現在の大学を辞めてまで、編入したいのですか?
- 学習・研究について
- 入学後に学びたいことは何ですか?具体的に教えてください。
- 興味のある先生や研究室(ゼミ)はありますか?
- 現在の大学では、どのようなことを学んでいますか?(一番興味深かった授業は?)
- 筆記試験について
- 今日の筆記試験の出来はどうでしたか?
- (筆記試験の答案を見ながら)この問題について、もう少し詳しく説明してください。
- 将来について
- 編入後の学習計画を教えてください。
- 卒業後の進路はどのように考えていますか?
- その他
- あなたの長所と短所を教えてください。
- 最近気になったニュースは何ですか?
- 何か質問はありますか?(逆質問)
一人での面接対策には限界があります。特に、志望理由の掘り下げや、論理的な回答の組み立てに不安がある場合は、編入試験に精通したプロ講師による模擬面接などで、客観的な視点を取り入れるのも一つの方法です。
\面接試験の具体的な攻略法はこちら/
面接対策の方法についてはこちらの記事もチェック↓

日本大学文理学部 編入試験の出願手続きと注意点(事前連絡・資格審査)

どんなに試験対策をしても、出願手続きで不備があれば、スタートラインにすら立てません。事務的な手続きも見落とさないよう、注意深く進めましょう。
出願までの流れ
- 募集要項の入手: 日本大学文理学部の公式サイトで最新の「編入学試験募集要項」をダウンロードし、熟読します。
- 事前連絡・資格審査: 対象となる学科・年次の志願者は、指定された期間内に必ず手続きを行います。(詳細は下記)
- 出願書類の準備: 志望理由書、成績証明書、卒業(見込)証明書など、募集要項で指定された書類を漏れなく準備します。
- 検定料の支払い: 指定された方法で検定料を納入します。
- 出願: 書類一式を揃え、出願期間内に必ず「簡易書留・速達」で郵送します。
出願前の手続きが必要な学科について
学科や出願年次によっては、出願期間の前に「事前連絡」や「資格審査」が必須とされています。
これらの手続きは、受験生のこれまでの履修科目が、編入後の学習についてこられるレベルにあるかを大学側が事前に確認するためのものです。この手続きを怠ると、出願そのものが認められない可能性があります。
【2026年度入試の例】
- 事前連絡が必要な学科(2・3年次):
- 心理学科
- 数学科
- 化学科
- 事前の問い合わせが必要な学科:
- 史学科
- 資格審査が必要な学科・年次:
- 2年次:地球科学科、情報科学科、化学科 の志願者
- 3年次:全学科の志願者
- (その他、海外の大学出身者など)
対象となる学科・年次は年度によって変更される可能性もあります。ご自身が該当するかどうか、必ず最新の募集要項の「2 出願資格・資格審査」の項目を確認してください。
日本大学文理学部への編入に向けた準備を始めよう

ここまで、日本大学文理学部の編入試験について、その概要から具体的な対策ポイントまで解説してきました。
日本大学文理学部への編入は、決して楽な道のりではありません。しかし、その分、やり遂げた先には、より深く学びたいと願った専門分野の世界と、新しい環境での充実した学生生活が待っています。
合格への鍵は、
- 募集要項を正確に読み解き、試験の全体像を把握すること。
- 志望学科の専門科目の出題傾向を知り、基礎から着実に知識を積み上げること。
- 「なぜ、ここで学びたいのか」という明確な意志を、志望理由書と面接で伝えられるよう準備すること。
にあります。
日本大学文理学部への合格に向けて具体的な合格戦略を策定したい方や実際の対策の進め方について疑問がある方は、ぜひ編入試験のプロとの無料相談会にお越しください。
\公式LINEで豪華6大特典をプレゼント中!/