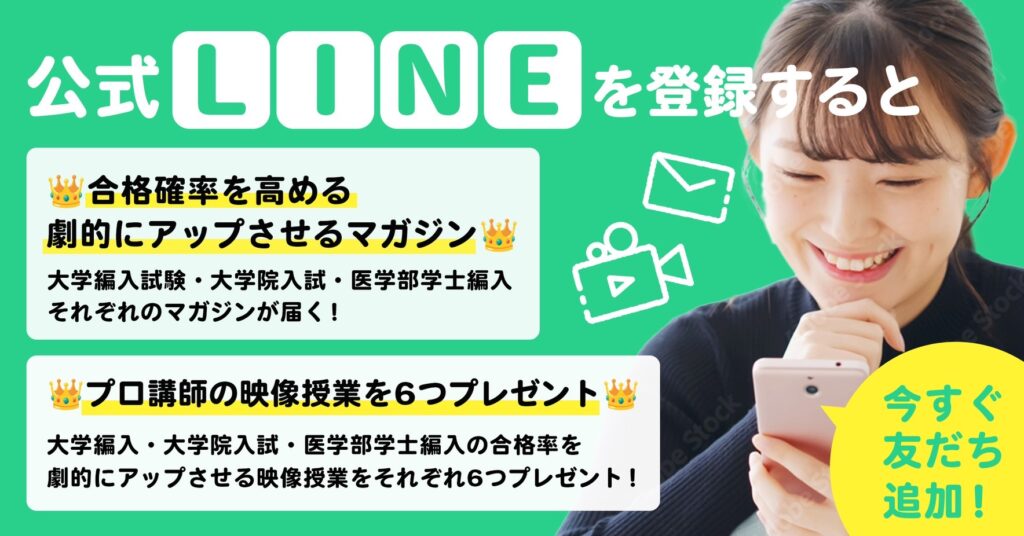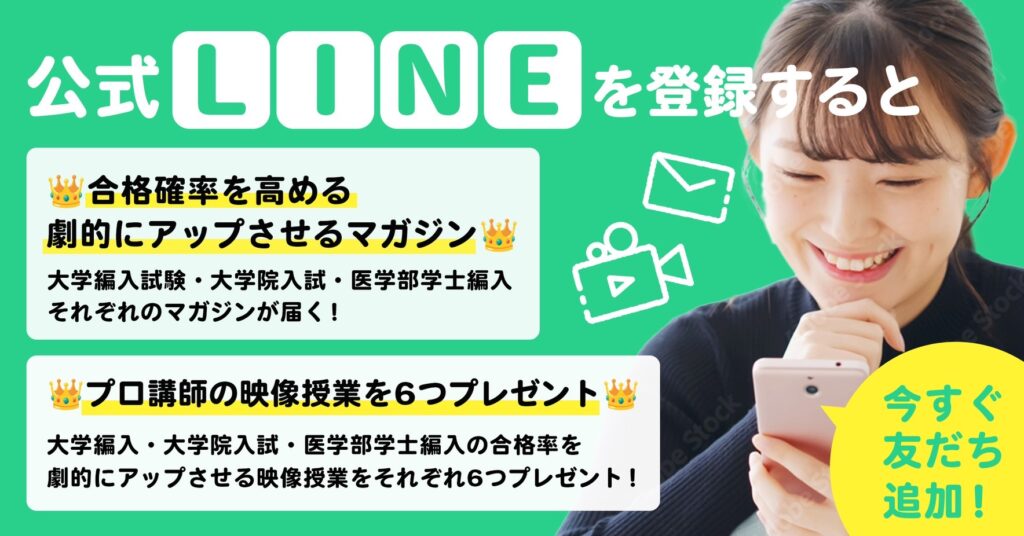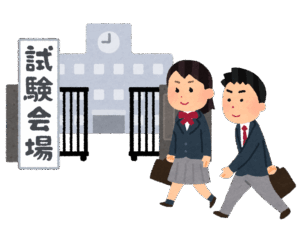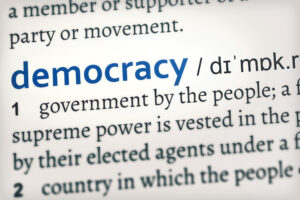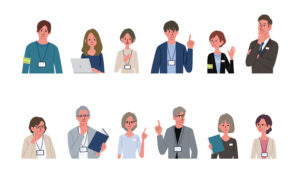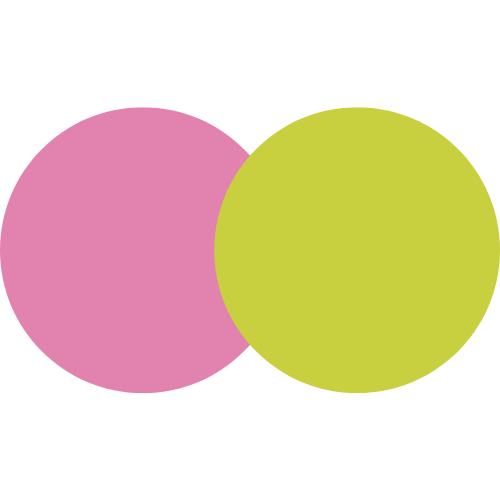ご質問やお問い合わせはお気軽に
【2026年度】日本大学の編入試験を徹底解説! 各学部の詳細と対策
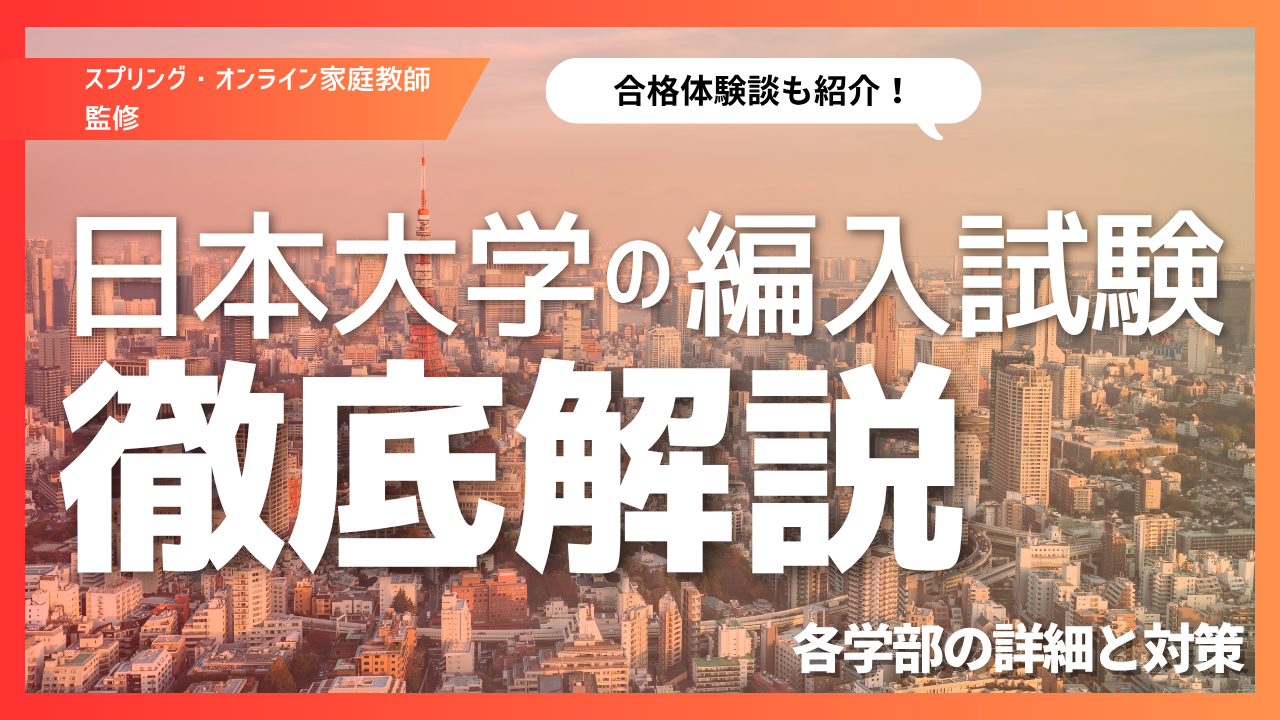
はじめに
「今の大学に入学したけれど、どこか物足りなさを感じている…」
「本当は日本大学に行きたかった。でも、仮面浪人は大変そう…」
「日本大学に興味のある学科があるけど、再受験は難しい…」
そんな悩みを抱えている方にとって、日本大学への編入試験は魅力的な制度です。しかし、編入試験は一般的な大学受験とは異なり、情報が少なく、対策方法も確立されていないため、多くの方が「何から手をつければいいのか分からない」という壁にぶつかってしまいます。それは決して能力が足りないからではありません。 正しい戦略と情報があれば、日本大学への編入は、十分に現実的な目標です。
この記事では、日本大学の募集要項などを基に、学部ごとの詳細な試験内容から、具体的な対策法、そして合格までの道のりを、一歩ずつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたは自分のやるべきことを明確に理解し、合格への確かな一歩を踏み出せるはずです。
もし、記事を読むよりも先に、編入試験のプロに直接相談したいという方は、スプリング・オンライン家庭教師の公式LINEから無料相談にお申し込みください。ご自身のご状況について直接ご相談いただくほうが、文字情報を集めるよりも効率的な場合も多くあります。
\日本大学の編入試験についてのご相談はこちら/
\公式LINEで豪華6大特典をプレゼント中!/
第1章:そもそも日本大学の編入制度とは?全体像を掴もう

「編入って、具体的に何が良いの?」「日本大学は、なぜ編入生を募集しているの?」
本格的な対策を始める前に、まずは日本大学の編入制度そのものについて理解を深めていきましょう。ここを理解することで、あなたの志望動機はより確固たるものになります。
編入試験は、人生の軌道修正を可能にする「再チャレンジ制度」
編入試験の最大のメリットは、 大学を中退することなく、現在の大学で学んだ成果を生かしながら、別の大学の2年次や3年次に移籍できる 点にあります。再度、一般入試を受けるとなると、現在の大学での経験を生かせないばかりか、入試のために現在の大学の学びを継続しにくくなる場合も多いです。さらに、入学した後も大学一年生からやりなおすことになり、時間も労力もかかってしまいます。一方で編入試験では現在の大学での学びを生かすことが可能です。
また、現役時代の受験で満足のいく結果が得られなかった方や、大学で学ぶ中で新たな目標が見つかった方にとって、人生の軌道修正を可能にする非常に合理的な制度と言えるでしょう。
特に、総合大学である日本大学は、非常に多くの学部で編入の門戸を開いており、多様なバックグラウンドを持つ学生を積極的に受け入れています。これは、大学側にとっても、異なる環境で学んできた意欲の高い学生を受け入れることで、学内の活性化に繋がるという大きなメリットがあるからです。
日本大学の編入試験を実施している学部・学科一覧
(※注意:以下の表は、令和8年度(2026年度)の募集要項に基づいています。受験年度の最新の大学公式募集要項を必ずご確認ください。)
| 学部 | 学科 | 募集年次 | 試験科目 |
| 法学部 | <第一部> ・法律学科 (総合法コースのみ) ・政治経済学科 ・新聞学科 ・経営法学科 ・公共政策学科 <第二部> ・法律学科 | 2年次 | ・英語 ※1 ・小論文 (社会・人文に関する問題) ・口頭試問及び面接 |
| 同上 | 3年次 | ・英語 ※1 ・学科選択科目 ※2 ・口頭試問及び面接 | |
| 文理学部 | ・哲学科 ・史学科 ・国文学科 ・中国語中国文化学科 ・英文学科 ・ドイツ文学科 ・社会学科 ・社会福祉学科 ・教育学科 ・体育学科 ・心理学科 ・地理学科 ・地球科学科 ・数学科 ・情報科学科 ・物理学科 ・生命科学科 ・化学科 | 2年次 | ・外国語科目 ※3 ・学科指定科目 ※4 ・口頭試問 |
| ・哲学科 ・史学科 ・国文学科 ・中国語中国文化学科 ・英文学科 ・ドイツ文学科 ・教育学科 ・心理学科 ・地理学科 ・数学科 ・情報科学科 ・物理学科 ・生命科学科 ・化学科 (※社会、社会福祉、体育、地球科学科の3年次募集はなし) | 3年次 | ・外国語科目 ※3 ・学科指定科目 ※4 ・口頭試問 | |
| 経済学部 | ・経済学科 (国際コースを除く) ・産業経営学科 ・金融公共経済学科 | 2年次・3年次 | ・学習計画書審査 ・英語 ・論文 ※5 |
| 商学部 | ・商業学科 ・経営学科 ・会計学科 | 2年次・3年次 | ・書類審査 ・資格・検定試験等の成績 (TOEIC L&R 又は TOEFL iBT) ・小論文 ・口頭試問 |
| 芸術学部 | ・写真学科 ・映画学科 ・美術学科 ・音楽学科 ・文芸学科 ・演劇学科 ・放送学科 ・デザイン学科 | 2年次 | 【学科・コースにより異なる】 ・書類選考 ・小論文、作文、実技、口頭試問、面接のいずれかの組み合わせ(詳細は募集要項参照) |
| ・美術学科 ・音楽学科 ・デザイン学科 (※写真、映画、文芸、演劇、放送学科の3年次募集はなし) | 3年次 | 【学科・コースにより異なる】 ・書類選考 ・小論文、実技、口頭試問、面接のいずれかの組み合わせ(詳細は募集要項参照) | |
| 国際関係学部 | ・国際総合政策学科 ・国際教養学科 | 2年次 | ・小論文 ・外国語(英語) ・面接 (※合否は書類選考を含む総合判定) |
| 同上 | 3年次 | ・小論文 ・外国語(英語) ・面接 (※合否は書類選考を含む総合判定) | |
| 危機管理学部 | ・危機管理学科 | 2年次 | ・書類審査 ・語学試験(英語) ・専門試験(論述) ・口頭試問及び面接 |
| スポーツ科学部 | ・競技スポーツ学科 | 2年次 | ・語学試験(英語) ・専門試験(論述) ・口頭試問及び面接 |
| 工学部 | ・土木工学科 ・建築学科 ・機械工学科 ・電気電子工学科 ・生命応用化学科 ・情報工学科 | 2年次又は3年次 ※6 | ・筆記試験 (英語, 数学) ・面接 (口頭試問を含む) |
| 薬学部 | ・薬学科 | 2年次(原則) | ・書類選考 ・学力試験 (理科 ※7, 外国語:英語) ・面接 |
| 歯学部 | ・歯学科 | 2年次 | ・学科試験 (理科: 生物学, 外国語: 英語) ・小論文 ・面接 |
| 松戸歯学部 | ・歯学科 | 2年次 | ・理解力の確認 (マークシート方式) ・小論文 ・面接 |
| 同上 | 3年次 | ・理解力の確認 (マークシート方式) ・小論文 ・面接 |
【注】
- ※1(法学部:英語): 実用英語技能検定(英検)2級以上など、指定の英語資格スコアを有する者は英語試験が免除されます。
- ※2(法学部:3年次学科選択科目): 以下の通りです。
- 法律学科: 法学
- 政治経済学科: 政治学 又は 経済学
- 新聞学科: マス・コミュニケーション論
- 経営法学科: 法学 又は 経営学
- 公共政策学科: 政治学、経済学 又は 行政学
- ※3(文理学部:外国語科目): 学科により受験科目が異なります。
- 英語・ドイツ語・中国語から1科目選択: 哲、史、国文、ドイツ文、社会、社会福祉、教育、体育、心理
- 英語のみ: 英文、地理、地球科、数、情報科、物理、生命科、化
- 中国語のみ: 中国語中国文化
- ※4(文理学部:学科指定科目): 学科ごとに専門科目が指定されています(例:社会学科は「社会学」、情報科学科は「数学・プログラミング」など)。数学科や情報科学科は2年次と3年次で出題内容が一部異なります。
- ※5(経済学部:論文): 経済学検定試験(ERE)の「EREミクロ・マクロ」がランクB以上の者は、論文試験が免除されます。
- ※6(工学部:募集年次): 認定単位数に応じて2年次もしくは3年次への編入学が決定されます。
- ※7(薬学部:理科): 「基礎化学(有機化学を含む) 又は 基礎生物学(生化学を含む)」から選択。
日本大学は各学部・学科により出題形式が異なるため、志望学部・学科に合わせた対策が不可欠です。具体的な対策法や今後の学習の進め方についてクリアにしたい方はぜひ一度無料相談会にお越しください。LINE友達限定で大学編入試験の対策に役立つ豪華特典もプレゼント中です!
\日本大学の編入試験について具体的な対策を立てたい方はこちら/
第2章:【学部別】日本大学 編入試験の難易度・倍率と対策

さて、ここからは学部別に編入試験の難易度と対策を見ていきます。あなたが目指す学部では、具体的にどのような試験が行われ、どのような対策が必要なのでしょうか。
まずは、多くの受験生が志望する経済学部から見ていきましょう。
2-1. 経済学部:求められるのは「基礎知識」と「応用力」
「日大経済学部の編入、英語と専門論文って聞くだけで難しそう…」 「経済学部なんて今まで学んだことがないけれど、今から対策して間に合うんだろうか?」
経済学部の試験内容は、確かに専門性が高く見えます。しかし、過去の出題傾向を分析すると、決して奇をてらった難問が出題されているわけではないことが分かります。問われているのは、経済学の基本的な知識を、現実の社会問題に当てはめて考える「応用力」なのです。
試験科目①:英語(長文読解+文法・語彙)
経済学部の英語は、単なる語学力だけでなく、社会問題に対する読解力が求められるのが特徴です。
- 出題形式とレベル感 過去の試験を見てみると、主に長文読解と、文法・語彙力を問う空所補充問題で構成されています。特に長文では、社会的なテーマを扱った英文が多く採用されています。例えば、過去には子どもの貧困問題をテーマにした英文(「子ども食堂」の取り組みなど)が題材となりました。文章自体の難易度は標準的ですが、テーマに関する背景知識があると、よりスムーズに読み解くことができるでしょう。設問は、内容の真偽を問うものが中心で、英文の正確な理解が求められます。
- 合格のための学習戦略
- 語彙力強化: まずは標準的な大学受験レベルの単語帳(例:ターゲット1900、システム英単語など)をしっかり復習しましょう。その上で、経済や社会問題に関する英字ニュース(Japan Times、NHK Worldなど)に触れ、”poverty”(貧困)、”relative poverty”(相対的貧困)といったテーマに関連する語彙にも慣れておくことをお勧めします。
- 長文読解演習: 1日1題でも良いので、500〜700語程度の英文を読む習慣をつけましょう。ただ読むだけでなく、「段落ごとの要旨を掴む」「筆者の主張は何かを考える」といった意識を持つことが重要です。社会問題系のテーマを扱った英文記事を読むことは、英語の対策だけでなく、後述の小論文対策にも繋がります。
- 文法・語法: 空所補充問題は、文法・語法の基礎知識を問うものがほとんどです。基本的な文法書を繰り返し復習し、知識の穴をなくしておきましょう。特に時制、関係詞、仮定法などは、長文読解の精度にも関わるため、重点的に確認してください。
試験科目②:論文(経済学の専門知識)
経済学部の合否に大きく影響するのが、この論文試験です。800字程度で、経済学の知識を用いて特定のテーマについて論述する力が試されます。
- 出題形式と頻出テーマ 過去の出題傾向を分析すると、テーマは大きく2つに分類できます。
- 経済学の基本理論を問う問題 例:「需要と供給曲線を用いて、均衡価格と均衡取引量がどのように決定されるかを図示して説明する」といった、ミクロ・マクロ経済学の基本的な概念の理解を問う問題です。
- 時事問題と経済学を結びつける問題 例:「新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、日本経済と世界経済にどのような影響を与えたか、また今後どのような影響が考えられるか。経済学の知識や考え方と結びつけながら論じる」といった、現実の社会問題を経済理論で分析する応用力が試される問題です。
- 合格のための学習戦略
- 基本書を丁寧に理解する: まずは、大学教養レベルのミクロ・マクロ経済学の教科書を1冊選び、繰り返し読んで内容をしっかり理解しましょう。特に重要な図やグラフ(需要供給曲線、IS-LM曲線など)は、なぜその形になるのか、何を意味しているのかを自分の言葉で説明できるようになるのが目標です。
- 時事問題に関心を持つ: 日経新聞やニュースサイトなどで、日頃から社会の動きに関心を持ちましょう。そして、「この問題は、経済学のあの理論で説明できるかもしれない」と考える癖をつけることが、応用力を鍛えるトレーニングになります。例えば、「物価上昇」というニュースを見たら、デマンドプル・インフレなのか、コストプッシュ・インフレなのかを考える習慣をつけましょう。
- 実際に書いてみる: 知識をインプットするだけでなく、800字で文章を構成する練習をしましょう。自分の考えを制限時間内に論理的にまとめる力は、すぐに身につくものではありません。構成案(序論・本論・結論)を作る練習から始め、徐々に全文を書き上げる練習に移行するのがお勧めです。
- 第三者による添削: 独学で最も難しいのが、自分の答案の客観的な評価です。可能であれば、編入試験に精通したプロ講師など、第三者に添削してもらい、論理の飛躍がないか、専門用語の使い方が正しいかをチェックしてもらうのが理想的です。
経済学部の対策は、一見すると大変そうに思えるかもしれません。しかし、求められているのはあくまで基礎力とその応用力です。地道な努力を続ければ、必ず道は開けます。
\日本大学経済学部の編入試験についてはこちら/

2-2. 法学部:問われるのは「法律知識」よりも「思考力」と「読解力」
「法律なんて学んだことがないのに、法学部の小論文なんて書けるわけがない…」 「やっぱり、事前に法律の専門書を読み込んで、知識を暗記しないと合格は無理なのだろうか?」
法学部への編入と聞いて、多くの受験生がこのような不安を抱きます。しかし、結論から言うと、その心配はほとんどの場合、必要ありません。日本大学法学部の編入試験で問われているのは、 あなたがどれだけ法律を知っているかではなく、提示された文章を正確に読み解き、それに対して自分の考えを論理的に展開できるか という、より本質的な力です。
試験科目:小論文(課題文読解型)
その証拠に、実際の出題傾向を見てみましょう。
- 出題形式とレベル感 法学部の小論文は、あるテーマに関する長めの文章(課題文)をその場で読み、それに基づいて設定された問いに答える「課題文読解型」です。 例えば、過去には「プライヴァシーの確保が、なぜ、そしてどのように個人の尊厳にとって重要なのか」について書かれた文章を読み、その内容を踏まえた上で、 自分自身の具体的な経験 に言及しながら論述する、といった形式の問題が出題されています。このように、法律の専門知識を暗記しているか(例:憲法第何条に何が書かれているか)を問うのではなく、課題文の筆者の主張を正確に理解し、それを自分自身の経験や考えと結びつけて論理的に再構成する力が求められています。
- 合格のための学習戦略
- 現代文の評論文・新聞の社説を読む: 課題文を素早く正確に読み解くトレーニングとして、大学受験用の現代文の評論文問題集や、新聞の社説を読むことをお勧めします。その際、「筆者の主張は何か」「その根拠はどこか」「具体例はどこか」を常に意識し、文章を構造的に捉える練習をしましょう。要約ノートを作るのも良い訓練になります。
- 自分の「経験の引き出し」を整理する: 「プライヴァシー」「自由」「平等」「ルール」「監視社会」といった、小論文で扱われやすいテーマについて、日頃から自分自身の経験と結びつけて考えてみましょう。「監視されていると感じて、発言をためらった経験」や「一人になれる空間があったからこそ、新しいアイデアが生まれた経験」など、具体的なエピソードをいくつかストックしておくと、本番で大いに役立ちます。
- 800字で文章を構成する練習: 知識や経験があっても、それを制限時間内にまとめるのは別の技術が必要です。「結論→理由→具体例→再結論」といった基本的な型(PREP法)を意識し、実際に800字で書く練習を繰り返しましょう。
- 第三者の視点を取り入れる: 書いた文章は、必ず第三者に読んでもらい、論理的に分かりやすいか、説得力があるかをチェックしてもらうことが非常に重要です。自分では気づかない論理の穴や、より伝わりやすい表現をアドバイスしてもらうことで、答案の質は格段に向上します。
法学部への道は、決して法律知識の暗記から始まるわけではありません。まずは目の前の文章と真摯に向き合い、自分自身の言葉で思考を深めていくこと。それが、合格への最も確実な一歩となるはずです。
\日本大学法学部の編入試験についてはこちら/

2-3. 文理学部:問われる専門性は学科次第!自分の「得意」を活かせる学部選びが鍵
「文理学部って、なんだか掴みどころがなくて、どう対策したらいいか分からない…」
このように感じる方も多いかもしれません。それもそのはず、日本大学文理学部は、 所属する学科によって編入試験の内容が全く異なる 、非常に専門分化された学部だからです。
しかし、これは見方を変えれば大きなチャンスでもあります。自分の得意分野や、これまで大学で学んできたことを直接活かせる「穴場」の学科が見つかる可能性があるのです。
ここでは、その多様性を理解していただくために、対照的な「社会学科」と「情報科学科」の傾向を分析していきましょう。
ケース① 社会学科:社会学の「基礎知識」がストレートに問われる
社会学科の試験は、一般的な小論文とは一線を画し、明確に 社会学の専門知識 が問われます。対策が比較的立てやすい、知識量が結果に直結する試験と言えるでしょう。
- 出題形式とレベル感 過去の傾向を見ると、大きく分けて2つの形式で構成されているようです。
- 専門用語の説明能力を問う問題 例:「社会学とはどのような学問か」という問いに対し、「アノミー」「ハビトゥス」「社会構造」といった指定された複数の専門用語を用いて説明する問題。各用語の正確な理解が求められます。
- 社会学の理論を用いた論述問題 例:「現代の日本社会が抱える社会問題を一つあげて、その問題を社会学の理論を用いながら論じる」といった問題。単なる問題点の指摘ではなく、特定の社会学理論(例:ブルデューの資本理論、デュルケームの社会分業論など)の枠組みで分析する力が必要です。
- 合格のための学習戦略 対策は比較的シンプルです。まずは大学教養レベルの社会学の教科書や用語集を1冊用意し、基本的な専門用語(アノミー、ハビトゥス、官僚制、ゲマインシャフトとゲゼルシャフト等)を、その提唱者とセットで確実に暗記・理解しましょう。その上で、関心のある社会問題(例:格差問題、ジェンダー、家族の変容など)を、覚えた用語や理論を使って説明する練習を繰り返すことが、合格への近道です。
ケース② 情報科学科:大学レベルの「数学」と「プログラミング」能力が必須
一方、情報科学科の試験内容は、社会学科とは全く異なります。こちらは明確に理系、特に 数学とプログラミングの素養 が問われる専門試験です。
- 合格のための学習戦略 理系の学生や、独学で数学・プログラミングを学んできた方にとっては、非常に有利な試験と言えるでしょう。対策としては、大学教養レベルの微分積分・線形代数の教科書・問題集をしっかり復習することが不可欠です。プログラミングに関しても、特定の言語(過去にはProcessingなど)が指定されることもありますが、大切なのはif文(条件分岐)やfor文(ループ処理)、配列といった基本構造の理解です。何らかの言語(PythonやC言語など)でこれらの基本構造を理解しておきましょう。
このように、同じ文理学部でも、学科によって求められる能力は全く異なります。大切なのは、「文理学部」とひとくくりに考えるのではなく、 あなたのこれまでの学びや興味、そして得意分野に最もマッチした「学科」を見つけ出し、的を絞って対策を始めること です。それが、合格の可能性を最大限に高める鍵となるでしょう。
\日本大学文理学部の編入試験についてはこちら/

2-4. 商学部:「ビジネスへの知的好奇心」が問われる現代的テーマ
「商学部って、経営とか会計とか、専門知識がないと太刀打ちできないんじゃ…?」 「なんだか意識が高いテーマばかりで、自分に書けるか不安…」
日本大学商学部の編入試験は、 現代社会とビジネスの関わり に対する鋭い視点と知的好奇心を問う、非常に現代的な小論文試験です。しかし、これも法学部と同様、難解な専門知識を問うものではありません。求められているのは、社会の動きにアンテナを張り、自分なりの考えを論理的に構築する力です。
試験科目:小論文(600字〜800字)
商学部の小論文の特徴は、その時代ごとのビジネストレンドや社会課題を色濃く反映している点にあります。過去のテーマの変遷を見てみると、大学側がどのような学生を求めているかが透けて見えてきます。
- 出題テーマの変遷から見る出題傾向 過去に出題されたテーマには、以下のようなものがあります。
- 「90年代の長期不況が経済、ビジネス、金融、雇用などにもたらした変化について」(平成21年度)「ITの活用が企業経営に与える影響について」(平成21年度)「非財務情報としてESG (環境・社会・ガバナンス) 情報が重要になってきている。その理由について」(平成29年度)「電気自動車や自動運転、シェアリングサービスの登場など、近年ものづくりやサービスのあり方に大きな変化が見られる。このような変化がわれわれの社会経済や生活に与える影響について、あなたの意見を述べなさい」(令和2年度)
- 合格のための学習戦略 このような現代的テーマに対応するためには、日頃からの情報収集と、それを知識として体系化する努力が不可欠です。
- ビジネス・経済ニュースに毎日触れる: まずは、新聞の経済・経営関連記事や、信頼できるビジネスニュースサイト(日経電子版、NewsPicks、東洋経済オンラインなど)に毎日目を通す習慣をつけましょう。大切なのは、ニュースをただ「知る」だけでなく、「なぜこの変化が起きているのか?」「この変化は社会にどのような影響を与えるのか?」という視点で、一歩引いて考える癖をつけることです。
- 基本的な経営・マーケティング用語を理解する: 小論文で頻出の「CSR(企業の社会的責任)」「ESG」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」「SDGs」「シェアリングエコノミー」といったキーワードは、必ず自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。大学教養レベルの経営学やマーケティングの入門書を1冊読んでおくと、思考の「幹」がしっかりするため、論理的な文章が書きやすくなります。
- 「自分ならどう考えるか」を軸に書く練習: 商学部の小論文では、多くの場合「あなたの意見を述べなさい」という形で、主体的な思考が求められます。過去問のテーマを使い、「自分はこの問題の根本的な原因は〇〇だと考える。なぜなら…」という形で、自分の意見を明確に提示し、客観的な事実や社会の動向を根拠として補強する、という構成で書く練習を繰り返しましょう。
商学部の試験は、あなた自身の「ビジネスへの関心の高さ」を大学にアピールする絶好の機会です。日々のニュースを追いかけながら、あなた自身の視点を磨いていってください。
2-5. 国際関係学部:「グローバルな課題」を自分事として考える思考力
「国際関係って、なんだか壮大で、何から勉強すればいいんだろう?」 「やっぱり英語が流暢に話せないと、合格は難しいのかな…?」
国際関係学部を目指す方の中には、語学力への不安を抱えている方も少なくないかもしれません。もちろん、語学力は重要なツールの一つです。しかし、日本大学国際関係学部の編入試験で本当に問われているのは、語学力そのものよりも、 複雑化する国際社会の課題を自分事として捉え、解決策を模索しようとする主体的な思考力 なのです。
試験科目:小論文
それを象徴しているのが、過去の小論文課題です。
- 出題形式とレベル感 国際関係学部の小論文は、特定のテーマについて、あなた自身の考えを論理的に述べることを求める形式です。例えば、過去には「 国際関係を学ぶ上で、言語コミュニケーション力と国際情勢の分析力はどちらも重要だが、SNSやWeb会議以外での直接的な国際交流が難しい現在、この二つのバランスをどのように保ちながら学んでいけば良いか 」という、まさに現代の状況を反映した問いが出題されました。この問いに答えるためには、机上の空論ではない、あなた自身の具体的な学習戦略を提示する必要があります。
- 合格のための学習戦略
- 「インプット」と「アウトプット」の学習サイクルを確立する: 小論文で提案できるよう、自分なりの学習サイクルを今から実践してみましょう。例えば、以下のようなサイクルが考えられます。
- 課題設定: 今週は「ウクライナ情勢」について学ぶ、と自分でテーマを決める。
- 多角的なインプット(情勢分析力): 日本のニュースだけでなく、BBC(英)、CNN(米)、アルジャジーラ(中東)など、様々な国の視点から報じられるニュース(Webサイトで十分です)を読み比べ、情報の偏りを意識する。
- 語彙のインプット(言語力): そこで出てきた “ceasefire”(停戦)や “sanction”(制裁)といった重要単語をリストアップし、意味を調べる。
- アウトプットの実践(言語力): オンライン英会話やSNSなどで、学んだ単語を使いながら、そのニュースについて「私はこう思う」と簡単な意見を発信してみる。
- あなただけの「学習ポートフォリオ」を作る: 上記のような学習を実践し、「私はこのようにして、情勢分析力と言語力のバランスを取っています」と、小論文で具体的に語れる実績を作りましょう。大学側が知りたいのは、空想のプランではなく、あなたが実際に行動し、試行錯誤した経験なのです。
- 基本的な国際関係の知識を押さえる: 「国家とは何か」「安全保障とは何か」「グローバリゼーションの光と影」といった、国際関係論の基本的な概念は、入門書を1冊読んで整理しておきましょう。これが思考の土台となります。
- 「インプット」と「アウトプット」の学習サイクルを確立する: 小論文で提案できるよう、自分なりの学習サイクルを今から実践してみましょう。例えば、以下のようなサイクルが考えられます。
国際関係学部が求めているのは、完成されたスーパーマンではありません。答えのない問いに対して、自分なりの方法で粘り強く学び続けられる、探求心にあふれた学生です。あなた自身の問題意識と、それを解決するための日々の小さな工夫こそが、合格を掴むための最も強力な武器となります。
2-6. 工学部:問われるのは「知識の正確さ」計算力が合否を分ける
「現在、理系の学部に在籍しているが、専門分野の方向性を変えたい」
「今の環境からステップアップしたいが、改めて大学レベルの試験となると不安が残る」
文系学部の小論文対策とは対照的に、工学部で問われるのは、非常に明確で客観的な「知識の正確性」と「計算力」です。自分の考えを述べる小論文とは異なり、与えられた問題を、数学や専門分野の法則に則って、いかに正確に解き切るかが合否を分けます。
これは、思考の柔軟性が問われる小論文が苦手な方や、コツコツと問題演習を積み重ねるのが得意な方にとっては、むしろ対策がしやすい試験と言えるかもしれません。工学部の試験は、筆記試験と面接で構成されています。
試験科目①:筆記試験(英語・数学)
筆記試験は、英語(60分・100点)と数学(60分・100点)で構成されています。どちらも「大学1年修了程度」のレベルが求められており、これは工学を学ぶ上での基礎体力が備わっているかを測るための試験です。
- 英語(大学1年修了程度)
大学1年修了程度の英語とは、単に高校英語の延長線上にあるだけでなく、理工系の基礎的な読解力を含むレベルと考えられます。工学系の学部では、専門分野の論文やテキストの多くが英語で書かれているため、それらを読み解くための素養が試されます。学習戦略:まずは、大学受験レベルの単語帳や文法書を完璧に復習し、文法・語彙の土台を固めましょう。その上で、科学技術系のニュースサイトや、大学教養課程で用いるような理工系の英語テキスト(PhysicsやCalculusの入門書など)の序文などを読み、専門的な用語や表現に慣れておくことが重要です。60分という時間内で長文を読み解く速読力も必要になるため、時間を計りながら演習を積むこともお勧めします。 - 数学(大学1年修了程度)
工学部の数学における「大学1年修了程度」とは、多くの場合、微分積分と線形代数を指します。これらは、土木、建築、機械、電気電子など、工学のあらゆる専門分野の基礎となる最重要科目です。学習戦略:対策に近道はありません。最も効果的なのは、大学教養レベルの微分積分・線形代数の教科書と問題集を徹底的に反復することです。公式をただ暗記するのではなく、「なぜその公式が成り立つのか」という導出過程を理解し、例題や章末問題を何も見ずに解けるようになるまで、何度も練習しましょう。理系科目の試験では、一つの計算ミスが致命的になることも少なくありません。普段から途中式を丁寧に書く癖をつけ、計算の正確性を高める努力を怠らないことが合格の鍵となります。
試験科目②:面接(口頭試問を含む)
工学部の面接は、5段階評価で行われ、単なる志望動機の確認だけでなく、「口頭試問」が含まれている点が最大の特徴です。この口頭試問では、「専門分野についての基礎的な内容」が問われます。
- 合格のための学習戦略面接官である教授陣は、あなたが「なぜ工学部で学びたいのか」という熱意と同時に、「編入後の授業についてこられるだけの基礎知識があるか」を見ています。
- 志望動機と学習計画の明確化:なぜ他の学部ではなく工学部なのか、そして工学部の中でもなぜその学科(例:土木工学科、機械工学科)を選んだのかを、これまでの自分の経験や将来の目標と結びつけて、論理的に説明できるように準備しましょう。
- 「専門分野の基礎」の徹底的な復習:口頭試問の対策として、志望する学科の「基礎的な内容」を必ず復習してください。例えば、機械工学科であれば「材料力学」「熱力学」「流体力学」「機械力学」の4大力学の基本的な概念や用語、建築学科であれば構造力学や建築史の初歩的な知識など、大学1~2年で学ぶであろう分野の教科書に目を通し、基本的な質問に自分の言葉で答えられるように準備しておく必要があります。
- 模擬面接の実施:自分の考えを口頭で説明する練習は不可欠です。大学の先生や、編入試験に精通したプロ講師に協力してもらい、「なぜ〇〇を学びたいのか」「△△(専門用語)について説明してください」といった実践的な質問に答える練習を繰り返しましょう。
第3章:学部選びに迷っているあなたへ|他大学との併願戦略

ここまで各学部の特徴を見てきて、「どの学部も魅力的だけど、結局自分はどこを受ければいいんだろう…」と、かえって迷ってしまった方もいるのではないでしょうか。
ご安心ください。その迷いは、あなたが真剣に編入を考えている証拠です。学部選びと併願戦略は、あなたの合格可能性を左右する、非常に重要なステップです。
この章では、日本大学を志望する方が、他の大学とどのように併願を組み立てていけばよいか、その考え方について解説します。
併願戦略の基本:「試験科目」の共通項で考える
まず、合格の可能性を少しでも高めるために、複数の大学・学部を併願することをお勧めします。ただし、大切なのは、やみくもに受験校を増やすことではありません。あなたの「得意な戦い方」を軸に、 試験科目に共通点のある学部を戦略的に組み合わせる ことが重要です。
例えば、「英語の長文読解」と「経済学の専門論文」の対策を進めている方が、全く対策の異なる「数学」や「法律小論文」が課される学部を併願するのは、学習の負担が大きくなりすぎてしまいます。
あなたの学習の軸(例:「英語」+「小論文」)を決め、そこから広げていくイメージを持ちましょう。
日東駒専(東洋・駒澤・専修)との併願
日本大学と同じ「日東駒専」グループの大学は、試験科目が比較的似ていることも多く、併願先の有力な候補となります。
- 例:日大 経済学部(英語、専門論文) と 東洋大学 経済学部(英語、小論文)
日大経済学部を目指す場合、英語の対策は必須です。東洋大学経済学部も英語(TOEIC)が課されますが、もう一科目は「小論文」であり、日大のような専門的な経済理論そのものを問うよりは、時事問題などに関する一般的な小論文であることが多いです。 - 戦略: 日大の専門論文対策をメインに進めつつ、東洋大学の過去問で小論文の傾向を確認し、並行して対策を進めます。英語の対策は共通して活かせます。
MARCH(法政・中央など)との併願
少しレベルを上げて、MARCHレベルの大学と併願する戦略もあります。試験科目が合致すれば、日大対策の延長線上で挑戦することが可能です。
- 例:日大 法学部(英語、小論文) と 法政大学 法学部(英語、小論文)
日大法学部は「英語」と「課題文読解型の小論文」です。法政大学法学部の編入試験も「英語」と「小論文」で構成される試験となっているため、併願は比較的容易だといえるでしょう。 - 戦略: 日大法学部対策で培う「課題文読解力」や「論理的思考力」は、法政大学の小論文対策にも大いに役立ちます。英語に関しても大部分は共通の対策が可能なので、無理なく両校の対策を進めていくことが可能です。
このように、ご自身の得意科目や現在の学習状況を軸に、試験科目の共通点と相違点をしっかりリサーチすることが、効率的な併願戦略の第一歩となります。しかし、併願戦略の立案のためには、日本大学だけでなく、編入試験に関する幅広い知識が不可欠です。編入試験自体の対策に十分に時間を割くためにも、一度編入試験に精通した第三者に相談することは効率的な編入試験対策のために有効だといえるでしょう。
\編入試験の併願戦略を策定したい方はこちら/
\公式LINEで豪華6大特典をプレゼント中!/
第4章:日本大学編入に合格するための共通対策

学部ごとの専門的な対策が見えてきたところで、次に取り組むべきは、 どの学部を受験する上でも共通して求められる対策 です。
筆記試験の対策が万全でも、ここで解説する「英語」「志望理由書」「面接」といった共通課題の準備が不十分だと、合格は遠のいてしまいます。一つひとつ、着実に準備を進めていきましょう。
1. 多くの学部で問われる「英語」の具体的な対策法
第1章の表で見た通り、日本大学の編入試験では、多くの文系学部で英語が必須科目となっています。専門科目の出来が同程度の受験生が並んだ時、最終的な合否を左右するのは、この英語の点数である可能性も十分にあります。
- 求められるレベルは「大学受験+α」
過去の傾向を分析すると、求められる英語力は、標準的な大学受験レベルから、少し発展的なレベルと位置づけられます。特に、経済学部や法学部の長文では、社会問題や学術的なテーマを扱った文章が出題されるため、背景知識や語彙力がなければ、時間内に正確に読み解くのは難しいかもしれません。 - 合格への近道は「基礎の徹底」
- 語彙: まずは、あなたが大学受験で使い込んだ単語帳(『システム英単語』『ターゲット1900』など)を復習することから始めましょう。9割以上の単語を即答できるレベルになったら、TOEFL対策の単語帳など、より学術的な単語が掲載されているものにステップアップするのが効率的です。
- 文法・構文: 難解な文法問題はほとんど出題されません。基本的な文法書・構文解釈の参考書を1冊用意し、SVOCを正確に振り分け、一文一文を正確に和訳する練習を繰り返しましょう。この地道な練習が、長文読解の精度を飛躍的に高めます。
- 長文読解: 語彙と構文の基礎が固まったら、1日1題、社会問題や関心のある分野の英文を読む習慣をつけましょう。
英語学習は、すぐに成果が出にくい分野です。しかし、裏を返けば、 毎日コツコツと続けた努力が、最も正直に結果として表れる科目 でもあります。毎日30分でも良いので、必ず英語に触れる時間を作ることが、合格への着実な一歩となります。
2. あなたという人間を伝える「志望理由書」の書き方
志望理由書は、単なる作文ではありません。あなたの情熱と論理性を大学側に伝えるための、筆記試験と同じくらい重要な「もう一つの試験」です。教授陣は、この書類を通して「なぜ、うちの大学でなければならないのか?」「この学生は、編入後に学びを深め、成長してくれるだろうか?」ということを見ています。
評価される志望理由書を作成するには、以下の3つのステップで思考を深めていきましょう。
- Step 1:自己分析(なぜ、自分は変わりたいのか?)
まずは、「なぜ編入したいのか」という原点を掘り下げます。「現在の大学・学部にどんな不満があるのか(ネガティブな理由だけでなく、ポジティブな動機に転換することが重要)」「何を学び、将来どうなりたいのか」を正直に書き出してみましょう。これが、あなたの物語の出発点となります。 - Step 2:大学・学部研究(なぜ、日本大学なのか?)
次に、その思いを遂げられる場所が「なぜ日本大学でなければならないのか」をリサーチします。大学の公式サイトを見るだけでは不十分です。シラバスを読み込み、「〇〇学部の△△教授の××という授業に強い関心がある」「□□というゼミで〜〜という研究がしたい」といったレベルまで具体的に落とし込むことで、あなたの本気度が伝わります。 - Step 3:物語を紡ぐ(過去・現在・未来を繋げる)
最後に、Step1とStep2を繋ぎ合わせ、あなただけの物語を完成させます。- 過去〜現在: 現在の大学での経験を通して、〇〇という課題意識を持つようになった。
- 課題: しかし、その課題を探求するには、現在の大学にはない△△という環境が必要だと感じている。
- 未来(日大で実現したいこと): 日本大学〇〇学部の□□という特色は、私の課題意識に完全に合致しており、△△教授の指導のもとで研究を深め、将来的には〜という形で社会に貢献したい。
この流れで構成することで、説得力のある志望理由書が完成します。テンプレートの丸写しや、他の大学との使い回しは簡単に見抜かれます。あなた自身の言葉で、あなたの物語を正直に綴ってください。
3. 面接で問われることと準備(実施学部向け)
面接を実施する学部では、書類だけでは分からない、あなたの「人柄」や「コミュニケーション能力」、「学習への熱意」が評価されます。多くの場合、聞かれることは以下の3つに集約されます。
- 志望理由書の内容の深掘り
- 「志望理由書に〇〇とありますが、これについてもう少し詳しく説明してください」
- 「なぜ、他の大学ではなく日本大学なのですか?」
- これまでの学びと、これからの学習計画
- 「現在の大学では、どの科目が一番印象に残っていますか?」
- 「編入後、どのような研究がしたいですか?」
- 将来のビジョン
- 「卒業後は、どのような道に進みたいと考えていますか?」
対策はシンプルです。 志望理由書に書いた内容を、自分の言葉で、さらに具体的に、熱意を込めて話せるように準備しておくこと です。
鏡の前で話す練習をしたり、可能であれば編入試験に精通したプロ講師 に模擬面接をしてもらったりと、必ず「声に出して話す」練習を繰り返しておきましょう。客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づかない癖や、より効果的な伝え方を発見できます。
第5章:スプリング利用者の合格体験記(日本大学 経済学部)
ここでは、実際にスプリング・オンライン家庭教師を利用し、日本大学 経済学部への3年次編入を果たした越沼さんの体験談をご紹介します。
合格者プロフィール:越沼さん(大東文化大学から編入)
- 編入先: 日本大学 経済学部
- 編入元: 大東文化大学
- スプリング利用期間: 約1年間
- 受講科目: 英語、小論文(専門科目)
編入を志した理由:「学ぶ環境を変えたい」
「元々、大学受験に失敗してしまっていて、(大東文化大学は)第1志望ではなかったので、学ぶ環境を変えたかったのが理由です。」
越沼さんは、大学受験での心残りを解消し、より良い環境で学びたいという強い思いから、編入試験への挑戦を決意しました。
スプリングを選んだ決め手:「通学」と「オンライン」の両立
編入試験に対応している塾や予備校をインターネットで調べる中で、最初にスプリング・オンライン家庭教師を見つけたという越沼さん。
「自分は家から遠い学校に通っていて、塾に通う時間があまり取れないので、自宅からオンラインで受講できるということにすごく魅力を感じました。」
在籍大学へは週4日ほど通学しており、多くの単位を取得しながらの受験勉強でした。そのため、通学のスキマ時間や自宅での学習を効率的にサポートしてくれるオンライン指導が、越沼さんのライフスタイルに最適だったと語ります。
1年間の学習と乗り越えた壁
スプリングでは約1年間、英語と専門科目の小論文を受講。
- 英語: 単語や文法など、基礎から学び直しました。「基礎をしっかりやっていたので、徐々に長文とかもどんどん読めるようになった」と、着実な成長を実感されていました。
- 小論文: 日大経済学部の小論文は、「社会問題のような問題」と「経済の専門的な問題」から選択する形式でした。越沼さんは「専門科目は、何度も小論文を書いて力をつけてきました」と振り返ります。
「今通っている大学での単位を取りながらオンラインでの授業も受けなければいけなかったので、その両立が大変でした。」
この大きな壁を、越沼さんは「空きコマを利用したり、電車通学の間に単語を覚えたりとか、スキマ時間を有効活用していました」と、地道な努力で乗り越えました。
合格の瞬間と勝因
「嬉しくて、家中を走り回っていました。」
見事、第一志望の日本大学 経済学部に合格。その勝因を伺うと、スプリングでの指導が大きな力になったことが分かります。
- 編入経験者による専門指導: 「実際に編入試験を経験されたことのある先生に専門科目の担当をしてもらったので、とてもありがたかったです。」
- 柔軟なスケジュール: 「学校の予定などに応じて授業時間の変更をしてくださったので、とてもありがたかったです。」
- 質の高い小論文指導: 「小論文の添削や、自分自身で書いた小論文をもう一度自分自身で考える時間を設けてくださり、それで力をつけていくことができました。」
- 的確な試験対策: 「本番でも解いたことのある内容と全く同じ問題が出て、すごい!もう笑みがこぼれてしまいました。」 週に10本近くの小論文を書いて練習を積んだ成果が、本番で発揮されました。
- 書類作成のサポート: 「(編入学後の)学習計画書なども書かなければならなかったので、先生方のアドバイスがとても役立ちました。」
後輩へのアドバイス
最後に、これから編入を目指す方へのアドバイスをいただきました。
「志望理由書の用意などに時間がかかったりしますし、専門科目などもすぐに力をつけていくことができるものではないので、できる限り早めに受講した方がいいと思いました。」
越沼さんにとって、スプリング・オンライン家庭教師は「自分を合格へと導いてくれた存在」だったと締めくくってくれました。
第6章:編入試験の「壁」を乗り越えるために

越沼さんの体験談、いかがでしたでしょうか。 彼の言葉からは、在籍大学の学業と両立しながら、強い意志で努力を続けた姿が伝わってきます。
この記事を読んでいるあなたも、「あとはやるだけだ」と感じているかもしれません。 しかし、私たちは多くの編入生をサポートしてきた専門家として、もう一つの現実もお伝えしたいと思います。
その「あとはやるだけ」というフェーズを、たった一人で乗り越えるのが、想像以上に難しい場合があるという現実です。
なぜ、多くの受験生が「独学」で悩んでしまうのか
編入試験は、情報が少なく、共に励まし合う仲間も見つけにくいため、孤独な戦いになりがちです。多くの意欲ある受験生が、以下のような壁にぶつかり、悩んでしまいます。
- 情報収集の限界: ネット上の匿名の体験談や古い情報に振り回され、間違った対策に貴重な時間を費やしてしまう。
- 客観的な評価の欠如: 越沼さんが「力がついているか実感しにくい」と語ったように、自分の書いた小論文や志望理由書が、本当に合格レベルに達しているのか、客観的に判断してくれる人がいない。
- モチベーションの維持: 思うように成績が伸びない時や、不安に襲われた時に、相談できる相手がおらず、最後まで走り抜く意志を保てなくなる。
あなたには、同じ思いをしてほしくありません。あなたの貴重な時間と情熱を、決して無駄にしてほしくないのです。
あなたの「挑戦」を「合格」に繋げるために
私たちスプリング・オンライン家庭教師は、そんなあなたの「孤独な戦い」を、専門知識と温かいサポートで「合格への二人三脚」に変えるお手伝いをしたいと考えています。
- 日大編入に合わせた「専門性」と「情報力」 この記事でご紹介したように、私たちは豊富なデータを基に、講師が日本大学の学部ごとの最新傾向を分析・熟知しています。
- あなただけの「オーダーメイドの学習計画」 あなたの現在の学力と志望学部、そして残された時間から逆算し、合格への効率的な学習計画をオーダーメイドで作成します。「何を」「いつまでに」「どこまでやればいいのか」が明確になるため、あなたは目の前の学習に集中できます。
- プロ講師による「マンツーマン指導」という安心感 越沼さんの体験談にもあったように、学習計画の管理はもちろん、小論文や志望理由書の質の高い添削、そして何より、あなたが不安な時のメンタル面のサポートまで。経験豊富なプロの講師が、常にあなたの隣で伴走します。
まとめ:次はあなたが合格を掴む番です

日本大学への編入は、単なる学歴のアップデートではありません。それは、大学生活の前半で見つけた「本当の自分」と、これからの人生を一致させるための、 最も主体的な自己投資 です。
合格のチャンスは、正しい情報を手に入れ、勇気を持って最初の一歩を踏み出した人の元にだけ訪れます。この記事が、あなたのその「一歩」になることを、心から願っています。
あなたの挑戦を、私たちは全力でサポートします。
もしあなたが少しでも「本気で日大に行きたい」と思っているなら、ぜひ一度、私たちの 無料相談会 にお越しください。あなたの現状を丁寧にお伺いし、合格までの具体的な道筋を一緒に描かせていただきます。