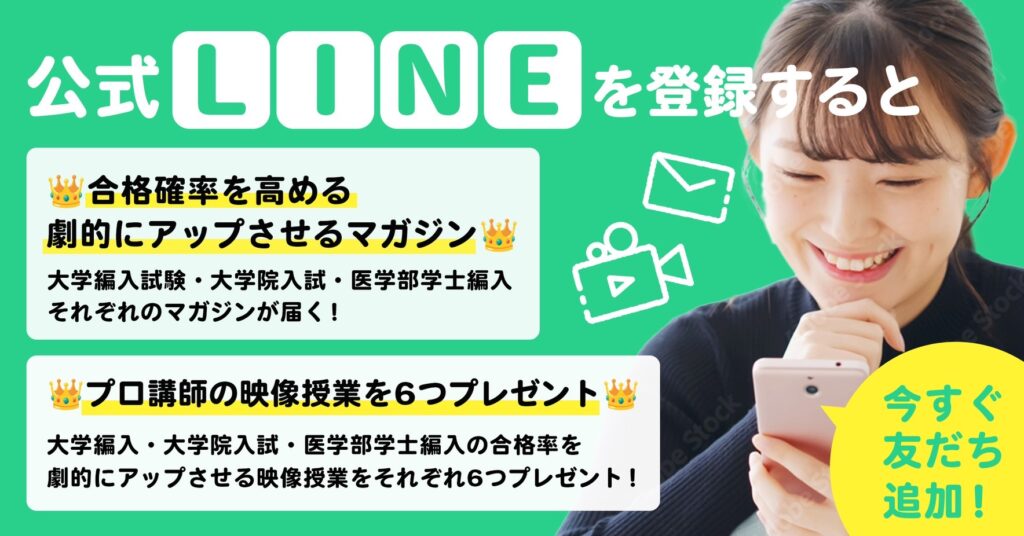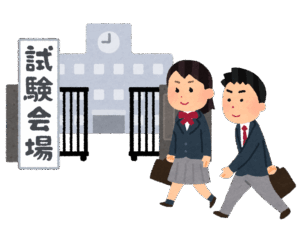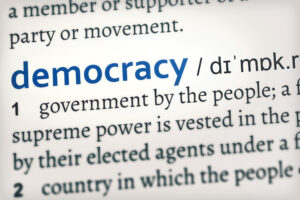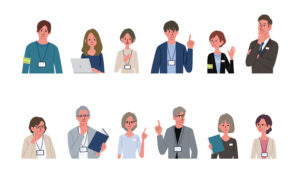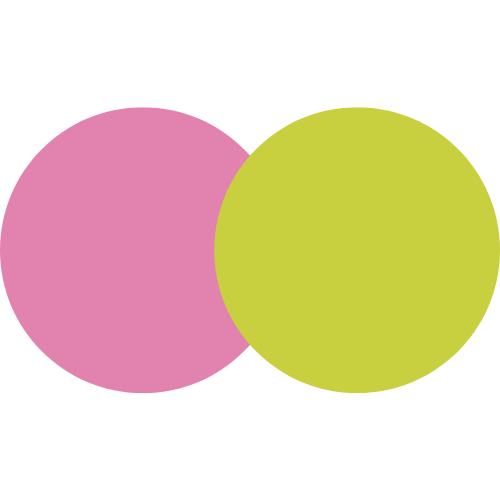ご質問やお問い合わせはお気軽に
法政大学法学部3年次編入を徹底解説!

スプリング・オンライン家庭教師では大学編入試験のプロ講師による無料相談を実施中!
大学編入試験のプロ講師が、「あなただけの最適な受験プラン」をご提案いたします。無理な勧誘などはございませんので、お気軽にご予約ください。
1. はじめに:編入試験を取り巻く現状と法政大学法学部の魅力
1-1. 大学編入試験の増加傾向
近年、大学編入試験を受ける学生は増加傾向にあります。学び直しやキャリアチェンジを目的とした編入だけでなく、より専門的な分野へ移行したい、あるいは大学ブランドを変更したいという理由で編入を選択する人も増えています。特に法学部は就職先の幅が広く、公務員や民間企業、さらには法曹界など多方面に進路を取れることから、常に高い人気を誇ります。
1-2. 法政大学法学部の魅力
法政大学は1880年に設立された「東京法学社」を源流とし、日本の私立大学の中でも長い歴史と伝統を持っています。首都圏有数の総合大学として、文系・理系を問わず多様な学部を擁しており、なかでも法学部は東京・市ヶ谷キャンパスに位置しているためアクセスも良く、学ぶ環境に恵まれています。
- MARCHの一角:明治・青山・立教・中央・法政の5大学を指す総称であり、首都圏での認知度と実績はトップクラス。
- 多彩なカリキュラム:法律学科・政治学科ともに充実した講義とゼミがあり、基礎から応用までしっかり学べる。
- 就職サポート:法曹、公務員、一般企業など、進路に応じたセミナーやキャリアセンターの支援が整備されている。
1-3. この記事の目的
本記事は、法政大学法学部3年次編入を検討する皆さんに向けて、試験の傾向と対策を詳しく解説するものです。特に、英語試験が存在する点、TOEICなどのスコア提出は不要である点、そして専門科目(法学・政治学)が論述式である点をしっかり押さえることが重要です。合格後のイメージや大学生活、キャリアの展望など、受験勉強のみならず入学後の情報も提供し、あなたの「編入して本当に良かった!」という未来をサポートします。
2. 法政大学法学3年次編入とは:仕組み・受験資格・基本情報
2-1. 編入試験の基本的な仕組み
大学編入試験は、短期大学・専門学校を卒業した人、あるいは大学で2年間(もしくはそれに準ずる期間)を修了した人を対象に、3年次から編入する機会を与える制度です。法政大学法学部の場合、3年次編入の他に2年次編入も募集しています。
2-2. 受験資格
- 短期大学卒業(見込み)者
在学中または卒業後すぐに受験できます。 - 専門学校卒業(見込み)者
2年制以上の専門学校で一定の授業時間・単位を修得していれば対象となるケースが多いです。 - 大学2年次修了(見込み)者
大学在籍中で2年間分の単位を取得していれば、同じ法学部でも他大学からでも受験可能。
※最終的な要件や募集枠は年度や学科によって変更される可能性があるので、必ず最新の募集要項で確認してください。
2-3. 募集人員と競争率
法政大学法学部の編入募集人員は比較的少数で、毎年変動します。年度によっては数名~十数名程度の枠となることもあるため、競争率は高めです。志望する学科(法律学科・政治学科)の募集枠や、他大学との併願状況を踏まえ、早めに対策を始めることが大切です。
2-4. 試験日程
11月中旬に編入試験が実施され、合格発表も年内~年明け早々に行われることが多いです。出願開始は夏前後からスタートすることもあるので、情報収集は早めに。英語や専門科目の対策には半年~1年の準備期間が理想的です。
3. 法政大学法学部の特徴:法律学科と政治学科の学び
法政大学法学部には「法律学科」と「政治学科」が設置されています。編入試験でも法律学科と政治学科で試験科目が異なるため、まずは各学科の学びの特徴を把握しましょう。
3-1. 法律学科
- 主要分野:憲法、民法、刑法、商法、行政法、国際法など
- 研究領域の多彩さ:国内法から国際法、判例研究から政策立案まで、幅広い分野をカバー。
- 将来の進路:弁護士、検察官、裁判官などの法曹、公務員、企業法務、金融機関、民間企業の管理職など。
3-2. 政治学科
- 主要分野:政治理論、国際政治、比較政治、行政学、地方自治、公共政策など
- 学びの特色:政治や社会問題を学際的に捉え、国内外の政治体制や時事問題について幅広く学ぶ。
- 将来の進路:国家公務員(総合職・一般職)、地方公務員、NPO・NGO、シンクタンク、ジャーナリズム、一般企業など。
3-3. 学科選択のポイント
- 法律を中心に学びたい場合は「法律学科」
- 政治制度や国際関係、行政に興味がある場合は「政治学科」
いずれの学科も法律や政治、社会の仕組みに深く携わりますが、扱う分野や将来のキャリア像が若干異なります。自分の興味や適性を見極めた上で学科を選択し、しっかり対策を練っていきましょう。

4. 法政大学法学部編入試験のメリット・デメリット
「編入」という選択肢は、普通の一般入試やAO入試とは異なる形で大学に入学するための制度です。ここでは、法政大学法学3年次編入を考える際のメリット・デメリットを整理します。
4-1. メリット
- ブランドとネットワーク
MARCHの一角である法政大学は、就職市場で一定の評価を得られます。またOB・OGネットワークも充実しており、人脈形成に有利。 - 高度な専門性
3年次に編入すると、法学や政治学の専門科目を集中的に学べるため、より深い知識・技能を身につけられます。 - 時間短縮
他大学への再入学や浪人と比較して、学年をあまり落とさずに(2年程度在籍後なら3年次合流)法政大学の学位を得ることが可能。
4-2. デメリット
- 競争率の高さ
編入募集枠は少なく、多くの志願者が集まるため合格難易度は上昇傾向。 - 単位認定の不確定性
編入後に前在籍校の単位をどこまで認定してもらえるかは大学の判断次第。想定より認定数が少ないと、卒業が延びる可能性もある。 - 試験の独自性
一般入試とは異なる出題形式(論述式+英語)に加え、学問領域もすでに大学レベル。受験勉強の仕方が分からないまま始めると苦戦しやすい。
編入は多大な労力を要する一方で、得られるリターンも大きい選択です。デメリットを理解し、計画的に準備すれば、憧れの法政大学法学部で充実した学生生活を送る道が開けます。
5. 試験概要:英語+専門科目(法律学科・政治学科)論述式
5-1. 英語試験の位置づけ
法政大学法学部の編入試験では、英語が必須科目として課されています。ただし、TOEICなどのスコア提出は不要で、あくまで大学独自の英語試験(筆記)を受験する形です。
- 出題形式:長文読解、文法・語彙問題、英作文などが中心。
- 難易度:大学2年次修了レベルを想定。高校卒業後も英語に触れてきたかどうかで差が出やすい。
5-2. 専門科目(論述式)
- 法律学科
出題範囲は憲法、民法総則、刑法総論などが中心。すべて論述式で出題されるため、条文や判例の知識を踏まえつつ論理的に答える能力が求められます。 - 政治学科
政治理論、比較政治、国際政治、行政学など政治学全般から出題。こちらも論述式が中心で、現代社会の課題を踏まえた時事的なテーマも登場する可能性大。
5-3. 小論文や面接はあるのか?
- 小論文:専門科目の論述式問題が実質的に小論文的要素を含んでいるため、別途小論文試験を実施しておりません。
- 面接試験:法政大学法学部の編入試験では、面接はありません。
5-4. 合否判定のポイント
- 英語と専門科目のバランス
どちらか一方だけ高得点でも合格が確定するわけではなく、総合的な評価によって決まります。 - 論述力
暗記だけではなく、問いに対して筋道立てた回答を文章で示せるかが最重要。 - 基礎知識の定着度
大学在籍経験を踏まえたレベルが問われるので、高校レベルからのキャッチアップだけでは不十分。
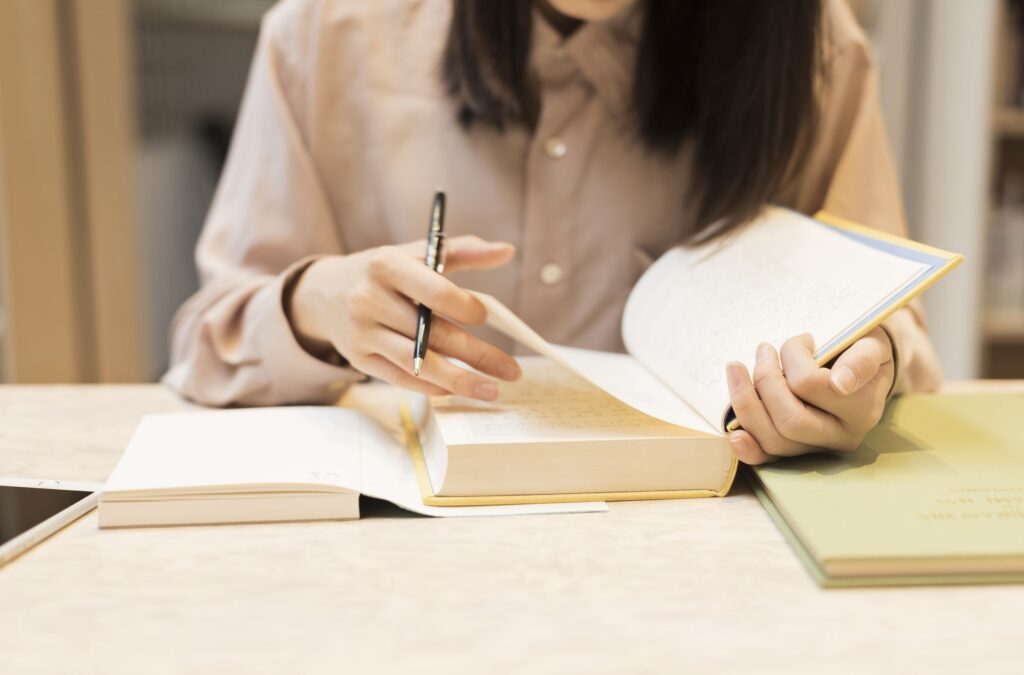
6. 英語対策:TOEIC不要でも侮れない!出題傾向と学習法
6-1. 法政大学法学部編入試験の英語の特徴
- TOEICスコアの提出は必要ない
その代わり、大学独自の英語筆記試験で総合的な英語力を測定します。 - 長文読解のウエイトが高い
法学部や政治学科の編入であることから、社会科学系のトピックが題材になることも。 - 文法・語彙問題も出題される
基本的な文法ルールや語彙力を問う設問があり、高校卒業レベル以上の知識が必要。
6-2. 学習ポイント
- 長文読解力の強化
- 毎日英文記事に触れる:CNN, BBC, The Japan Timesなどを読み、時事英語に慣れる。
- 速読+精読:英語の構造を正確に把握するため、精読を行いつつ読むスピードも鍛える。
- 文法・語彙の徹底復習
- 大学受験レベル(センター試験、共通テスト相当)の参考書を再度活用。
- 過去問演習や問題集でよく出る文法項目を重点的に押さえる。
6-3. おすすめの学習リソース
- 市販の大学編入英語対策問題集
編入試験に特化した参考書は限られていますが、一般的な大学受験用の長文問題集も活用可能。 - 新聞・雑誌の英語記事
政治・法律関連の英文を多く読むことで、試験だけでなく入学後のリーディング力も向上。 - 英作文添削サービス
独学ではミスに気づきにくいので、オンライン添削や予備校の講座を利用すると効果的です。
編入試験の英語は「TOEICスコアを出す必要がないから楽」というわけではありません。論理的に考えながら英文を読み書きする力が求められる点を意識し、地道なトレーニングを積みましょう。
7. 法律学科の専門科目対策:憲法・民法総則・刑法総論
法政大学法学部(法律学科)への3年次編入では、憲法・民法総則・刑法総論を中心とする論述式試験が行われます。ここでは、それぞれの科目対策を詳細に解説します。
7-1. 憲法
7-1-1. 出題範囲と重要テーマ
- 人権保障:表現の自由、信教の自由、学問の自由、財産権など
- 統治機構:国会・内閣・裁判所の権限、天皇制、地方自治など
- 判例学習:猿払事件、チャタレー事件、石に泳ぐ魚事件など有名判例を中心に論点を整理
7-1-2. 学習方法
- 基本書・判例集で体系理解
憲法の条文を確認しつつ、基本書で大枠を把握。判例集で実際のケースに基づく法的思考を身につける。 - 論述演習
憲法は「何が争点で、どのような法的利益が衝突しているか」を論理的に整理し、結論を導く力が必要。過去問や模擬問題を繰り返し解き、文章構成を訓練する。 - 現代の政治・社会問題との関連づけ
表現の自由や政教分離など、時事問題との絡みで問われる可能性も高い。ニュースを注視し、自分の意見をまとめる習慣をつけよう。
7-2. 民法総則
7-2-1. 出題範囲と重要テーマ
- 総則分野の基礎:人・物・法律行為・意思表示・代理・無効・取消・条件・期限・時効
- 契約に関する一般原則:契約自由の原則、私的自治など
- 判例・通説:民法は学説が多数存在するが、まずは通説(判例に準じたもの)を把握。
7-2-2. 学習方法
- 条文→趣旨→判例→学説の順で理解
民法は条文数が多いが、まずは重要条文の趣旨をしっかり抑え、関連判例で理解を深める。 - 事例問題演習
民法は事例形式(当事者間トラブルなど)で出題されることが多い。法的三段論法(規範定立→あてはめ→結論)を繰り返し練習する。 - 横断的に整理
総則だけでなく、物権編・債権編との関連を理解することが重要。編入試験での中心は総則だが、他の分野にも触れておくと論理展開がスムーズになる。
7-3. 刑法総論
7-3-1. 出題範囲と重要テーマ
- 犯罪論の基本構造:構成要件該当性、違法性、責任
- 因果関係、故意・過失、正当防衛・緊急避難、未遂犯・共犯など
- 判例学習:基本判例の理解が不可欠。
7-3-2. 学習方法
- 基本理論の体系把握
刑法は学説対立が多い分野だが、まずは一般的な通説と判例の立場を理解しよう。 - 事例問題演習
「行為者の行動が構成要件に該当するか?」「違法性阻却事由はあるか?」など、ステップごとに分析し、論述できるよう訓練。 - 論文形式でのアウトプット
刑法総論の問題は論述式が中心。答えが1つに定まらない論点もあるため、理由付けをしっかり示すことが評価される。
7-4. 共通の対策ポイント
- 法的三段論法のマスター
法律の論述では(1)法規範の定立→(2)事実とのあてはめ→(3)結論、というプロセスが基本。 - 判例・条文の引用
答案の中で条文や判例を適切に引用することで説得力が増す。ただし、無暗に名前や条文番号だけを並べるのではなく、その趣旨を説明できることが大切。 - 過去問や類似問題で慣れる
編入試験の過去問は限られているかもしれないが、他大学の編入試験問題や学部テキストの演習問題を利用して演習するのも効果的。

8. 政治学科の専門科目対策:政治学全般の論述問題を攻略する
法政大学法学部・政治学科の編入試験では、政治学の論述問題がメインとなります。法律学科とは異なる出題傾向のため、ここでは政治学対策のポイントを整理しましょう。
8-1. 出題範囲の概観
- 政治理論・政治思想:プラトン、アリストテレス、ロック、ルソー、マルクスなどの古典から現代政治理論まで
- 比較政治:議院内閣制、大統領制、多党制、二大政党制などの各国制度比較
- 国際政治・国際関係:主権国家体制、国際機関、冷戦構造、グローバリズムなど
- 行政学・公共政策:官僚制理論、地方自治、政策評価など
8-2. 学習方法
- 基礎理論のインプット
大学1~2年レベルの政治学概論や政治思想史のテキストを活用し、主要概念・主要理論を復習。 - 時事問題との関連
政治学は常に現代社会の動きと連動するため、新聞・ニュースの政治面を必ずチェックし、実例と理論を結びつける。 - 論述練習
テーマが「民主主義の課題」「グローバル化と国家主権」など抽象的になりがちな分、具体例やデータを援用しながら文章を展開する訓練が必要。
8-3. 論述で評価されるポイント
- 理論と現実の融合
政治学理論(マックス・ウェーバーの官僚制論など)を挙げつつ、現在の行政組織の問題点に言及するなど、理論と現実を結びつける視点。 - 複数の視点の検討
「メリット・デメリット」や「賛成・反対」の両面を提示した上で、自分の見解を述べる形が望ましい。 - 論理的な構成
序論(テーマの提示)→本論(分析・議論)→結論(まとめ・提言)の3部構成を踏まえて書くと読みやすい答案になる。
8-4. おすすめ教材
- 政治学概論書:複数の理論や政治システムを網羅的に扱う入門テキスト。
- 政治思想史:古典から近代・現代に至るまでの思想家の主張を整理できる書籍。
- 新聞・時事解説書:『読売新聞』『朝日新聞』等の社説、政治経済誌などで現代政治のテーマを学ぶ。
政治学科の試験では、法律学科のような厳密な条文解釈は求められないものの、社会科学的視点と論理的文章力が必須となります。柔軟な思考力を養い、時事ネタに敏感になっておきましょう。
9. 論述式試験を乗り切るための文章力強化術
法政大学法学3年次編入の専門科目では、法律学科・政治学科いずれも論述式での回答が要求されます。ここでは、論述力を高めるための具体的な方法をご紹介します。
9-1. 文章構成の基本
- 序論:問題提起、結論や論点の提示
- 本論:根拠・事例の提示、論点の深堀り
- 結論:要点のまとめ、今後の展望・意義など
論述問題でもこの三部構成を意識するだけで、読み手に分かりやすい答案を書きやすくなります。
9-2. 法的三段論法/社会科学的分析
- 法律学科の場合:法的三段論法(規範定立→あてはめ→結論)をベースに、条文・判例を用いながら論証する。
- 政治学科の場合:理論的枠組みや事例研究を踏まえ、複数の視点を検討してから自分の立場を示す。
9-3. 誤字脱字・用語の正確性
- チェックリストを作る:答案を書き終えたら、「誤字脱字」「用語の使い方」「主語と述語の対応」など必ず見直す。
- 専門用語の定義:漫然と用語を使うのではなく、論述の中で必要に応じて定義づけを行うと、評価が高まりやすい。
9-4. 日常的なトレーニング
- 新聞の社説要約:政治的・社会的テーマについて筆者の主張をまとめ、自分の意見を付け加える練習。
- 模擬答案作成:過去問や問題集を使い、時間を計って実際に文章を完成させる。
- 添削を受ける:友人や指導者に読んでもらい、論理展開や表現のわかりやすさをチェック。
論述試験で高得点を狙うには、論理的思考力+書く技術+知識量の3要素が不可欠です。知識だけでなく、文章構成力や表現力を総合的に磨きましょう。
10. 過去問の活用法:合格を近づける実践的トレーニング
10-1. 過去問入手方法
- 法政大学の公式サイトや入試課:年度によっては編入試験の過去問が公開されている。
- 大学生協やオークションサイトなど:在学生・卒業生の提供による過去問が入手可能なケースも。
- 他大学編入試験問題集:法政大学の過去問が見つからない場合、類似レベルの私大法学部・政治学科の編入試験問題を参考にする。
10-2. 過去問の使い方
- 実際の試験時間で解く
時計を用意し、本番さながらの環境で解答を書く。時間配分の練習に効果的。 - 解答例・添削を用意する
自分一人で採点すると客観性が損なわれるため、できれば指導者や先輩にアドバイスをもらう。 - 出題傾向を分析
憲法なら人権分野が多いのか、政治学なら国際政治のテーマが出題されがちか、など傾向を掴み効率的に勉強計画を立てる。
10-3. 類題演習の重要性
過去問だけでは出題パターンが限られる場合もあるため、受験レベルに近い他大学の編入試験問題や、司法試験・公務員試験の入門レベル問題集などを活用して幅広い演習を積むのが理想的です。論述式回答の練習量が成否を分けるとも言えます。
11. 合格後をイメージ:編入後の単位認定・履修計画・卒業要件
11-1. 単位認定の流れ
編入合格後、前在籍校で修得した科目のシラバスと成績証明書を提出し、法政大学でどの単位が認められるかが審査されます。結果はあくまで大学側の判断によりますが、類似性の高い科目(例:他大学の憲法Iと法政大学の憲法総論)が認定対象になりやすいです。
11-2. 履修計画の組み立て方
- 必修科目の確認:法律学科・政治学科それぞれに必修科目が設定されている場合が多い。認定されなかった必修科目は改めて履修する必要がある。
- 卒業要件単位数の把握:一般的には124単位程度を大学全体で必要とするが、編入時点でどれだけ単位を認めてもらえるかが重要。
- ゼミ・卒論のタイミング:法学部では3~4年次のゼミ活動が充実しており、卒業論文を書くゼミもある。編入生がゼミにスムーズに入るためには、早めの情報収集が欠かせない。
11-3. 卒業までのスケジュール
- 3年次前期~:必修科目や基礎演習を中心に履修。ゼミを選択する場合は各学期の募集をチェック。
- 3年次後期~4年次:専門演習(ゼミ)や卒業研究を本格化させつつ、就職活動や大学院受験の準備も並行して行う。
- 4年次:卒業要件を満たせば、他の学生と同様に卒業可能。単位が不足する場合は追加で履修する必要もある。
編入後の単位認定結果によっては、スケジュールがタイトになることもあります。特に公務員試験や法科大学院進学を検討する方は、逆算して履修計画を立てることが成功の鍵となるでしょう。
12. 法政大学法学部の学びとキャリア:ゼミ・就職・大学院進学
12-1. ゼミ(演習授業)の重要性
法政大学法学部では、多彩なゼミが開講されています。法律学科なら憲法判例研究ゼミ、刑法判例ゼミ、民事法ゼミなど、政治学科なら国際関係ゼミ、地方行政ゼミ、政治思想ゼミなど興味に合わせて選択可能。
- 少人数制で議論を深める:教員や仲間とディスカッションを重ねることで思考力・表現力を磨く。
- 就活・進学へのアピール:ゼミでの研究内容はエントリーシートや面接での大きな武器になる。
12-2. 就職支援とキャリアパス
- 企業就職:法学部の知識は企業の法務部門や総務、人事などで強みとなる。政治学科も時事問題の分析力やコミュニケーション力が評価されやすい。
- 公務員:行政職・警察・消防など地方公務員のほか、国家公務員総合職を目指す学生も多い。大学では公務員試験対策講座を開講していることがある。
- 法曹:弁護士、検察官、裁判官を目指す場合は法科大学院(ロースクール)進学が一般的。法政大学法科大学院への内部進学制度を利用する学生もいる。
12-3. 大学院進学
- 法科大学院(ロースクール)
法律学科卒業後、司法試験を目指すために進学。編入生でもカリキュラムをこなし、優秀な成績を収めれば合格可能。 - 大学院(政治学研究科・公共政策分野など)
政治学科の学生や、よりアカデミックな研究を希望する学生が大学院へ進む道もある。
法政大学のキャンパスは都心に位置し、企業や官公庁へのアクセスが良好。また、OB・OGネットワークやキャリアセンターのサポートを活用すれば、編入生でも十分に希望の進路を切り開けます。
13. 編入試験合格に向けた時間管理と学習スケジュール
13-1. 目標設定と逆算思考
編入試験は秋頃に実施されるケースが多いため、遅くとも春先から本格的に対策を始めるのが理想です。例えば10月1日が試験日なら、少なくとも6ヶ月前(3~4月)から計画を立てましょう。
13-2. サンプルスケジュール
~試験6ヶ月前
- 英語:文法・語彙の復習、長文読解を週1~2題ペースで着実に。
- 専門科目:憲法・民法総則・刑法総論(または政治学概論)を入門書でざっくり学習。判例や主要理論を押さえる。
試験3~4ヶ月前
- 過去問・類似問題演習:本格的に論述形式の答案作成練習を開始。
- 英作文・リーディング:試験時間を意識して実践的に解く練習を強化。
- 弱点克服:特に苦手分野(民法の代理や刑法の因果関係など)を重点的に学習。
試験1~2ヶ月前
- 総仕上げ:過去問の再演習、時事英語やニュースを取り込み、論述の完成度を上げる。
- 模擬試験形式のシミュレーション:時間を測りながら一連の科目を解く練習。
試験直前
- 暗記項目の最終確認:重要判例名、条文番号、政治理論の主要キーワードなど。
- 体調管理:睡眠不足や体調不良は致命的。無理な詰め込みは避け、精神面も整える。
13-3. 勉強時間の確保
在籍校の授業やアルバイトと両立しながらの編入試験勉強は大変です。朝型の学習や通学時間の活用など、細切れ時間を積極的に使いましょう。週末にまとめて勉強するよりも、毎日少しずつ継続する方が効果的です。

14. モチベーション維持のコツ:挫折しない勉強法
編入試験の準備は、大学やアルバイトとの両立が難しく、モチベーションを保つのが大変と感じる方も多いでしょう。ここでは、最後までやり抜くための工夫を紹介します。
14-1. 目的意識の再確認
- なぜ法政大学法学部に編入したいのか?
将来のキャリアや学びたい分野を具体的にイメージし、目標を言語化しておく。 - 合格後のメリット
MARCHブランド、都心キャンパス、充実したゼミ生活など、自分にとって魅力的な要素を明確にしておく。
14-2. 学習記録・進捗管理
- タスク管理アプリや手帳
1日の学習時間や達成項目を記録。視覚的に進捗を把握するとやる気が続く。 - 週間目標・月間目標
週単位・月単位で達成すべきゴールを細かく設定する。例:「今週末までに刑法総論の正当防衛を完璧に理解する」など。
14-3. 周囲のサポートを得る
- 家族や友人に宣言
編入試験を受けることを公言することで、自分を追い込む。 - 仲間と情報共有
同じ編入試験を目指す友人やSNSコミュニティを活用し、励まし合いながら勉強を続ける。
14-4. ストレス対策・リフレッシュ
- 適度な運動:散歩やジョギングで血行を促し、頭をスッキリさせる。
- 趣味の時間:完全に勉強を忘れてリラックスする時間も必要。
- 睡眠管理:質の良い睡眠は記憶定着にも大きく影響するため、徹夜は厳禁。
モチベーションが下がる原因は多種多様ですが、定期的に目標を再確認し、学習成果を可視化することで乗り切りやすくなります。「受験勉強は自分の人生を豊かにするプロセス」と捉え、前向きに取り組みましょう。
15. 編入受験生のQ&A:よくある悩みを一挙解決
ここでは、法政大学法学3年次編入を検討中の受験生からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 「TOEICスコアは本当に不要?英語試験はどんな難易度?」
A. TOEICなどのスコア提出は不要です。ただし筆記試験での英語力はしっかり問われるため、大学2年次修了レベル程度の文法力と長文読解力を身につける必要があります。難易度は共通テスト~中堅私大入試程度と考えておくと良いでしょう。
Q2. 「専門科目はどこまで勉強すればいい?高校の知識じゃ足りませんか?」
A. 編入試験は大学レベルの専門知識が出題されるため、高校範囲だけでは十分ではありません。法律学科なら憲法・民法総則・刑法総論、政治学科なら政治理論・国際政治などを大学初級~中級レベルで学んでおく必要があります。
Q3. 「面接や小論文はないのですか?」
A. 現時点の情報では、法政大学法学部の編入試験に面接や小論文は課されていません。論述式の専門試験と英語試験のみが実施されます。ただし、各年度で制度変更があり得るので、必ず最新の募集要項を確認してください。
Q4. 「編入後、すぐに友達ができるか不安です……」
A. 編入生は少数派ですが、ゼミやサークル、アルバイトを通じて交流の機会は十分にあります。また、編入生同士のコミュニティがある場合もあり、情報共有や悩み相談が可能です。
Q5. 「就職活動で不利になることはありませんか?」
A. 一般的には、編入生だからという理由で不利になるわけではありません。むしろ編入前の経験や大学名が変わることによる人脈拡大などがプラスに働くケースも多々あります。就活は個々の活動内容と実力が評価されるため、編入であることを有効にアピールする戦略も大切です。
Q6. 「他大学の法学部から編入するメリットは何ですか?」
A. 法政大学法学部ならではのカリキュラムやゼミ、OB・OGネットワーク、就職支援などを享受できる点が大きなメリットです。また、首都圏を中心にMARCHブランドの知名度は高く、将来的なキャリア形成にもプラスに働きます。
16. まとめ:法政大学法学3年次編入を成功させる鍵
長文にわたって解説してきましたが、最後に法政大学法学3年次編入を成功に導くためのポイントを簡潔にまとめます。
- 試験の正確な把握
- 英語(TOEIC不要だが筆記は必須)
- 専門科目は論述式(法律学科:憲法・民法総則・刑法総論、政治学科:政治学全般)
- 面接や小論文は基本的になし
- 論述対策を最優先に
- 条文や判例、政治理論の知識を正確に身につける
- 三部構成(序論・本論・結論)や法的三段論法を意識した文章力の養成
- 英語は苦手意識を払拭し、長文読解と英作文を強化
- 時事的テーマに触れ、社会科学系の英語表現に慣れる
- 文法・語彙の基礎固めも継続する
- 過去問・模擬問題をフル活用
- 時間を計って本番さながらに解く
- 解答例や添削を受け、自分の弱点を把握して修正
- 情報収集と計画的な学習
- 年度ごとの募集要項や試験日程を早めにチェック
- 編入合格後の単位認定やゼミ選びにも関心を持ち、大学生活をイメージ
- モチベーションを維持し、最後まで諦めない
- 目標を明確化し、進捗を見える化
- ストレス対策や体調管理にも配慮しながら、計画的に勉強時間を確保する
法政大学法学部は伝統と実績を兼ね備え、都心という好立地で学べる非常に魅力的な環境です。編入試験は決して楽な道ではありませんが、しっかり対策すれば合格の可能性は十分にあります。そして、合格後はゼミやサークル活動、就職活動など充実したキャンパスライフが待っているでしょう。
本記事を通じて、あなたが法政大学法学3年次編入に一歩近づき、実り多い大学生活・キャリアを築く手助けとなれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。心から応援しています!
おわりに
いかがだったでしょうか。
スプリング・オンライン家庭教師には、法政大学法学部の編入学試験で受験生を合格に導いた講師も多数在籍しています。受験生一人ひとりに合った最適な講師の指導で最短の合格を導きます。
大学編入は大学を変える最後の機会です。法政大学法学部をはじめとした難関大学の合格を目指すなら、ぜひ一度無料相談ください。
★無料相談はいつでも受付中!
★お問い合わせは公式HPもしくは公式LINEよりご連絡ください。
【公式HP】https://spring-online.jp
【公式LINE】https://lin.ee/hIY76pU
全国の受験生と繋がれる完全無料の匿名サロンはこちら:【大学編入】経済・経営・商学部

◎過去問解説動画や映像授業はこちら!(スプリングオンライン編入予備校)
スプリング・オンライン家庭教師HP:https://spring-online.jp/
スプリング・オンライン編入予備校HP:https://elearning.spring-online.jp/
YouTubeホーム:https://www.youtube.com/channel/UC50UbsiY7HNGAyxVbz0mLiw
\公式LINEで豪華6大特典をプレゼント中!/