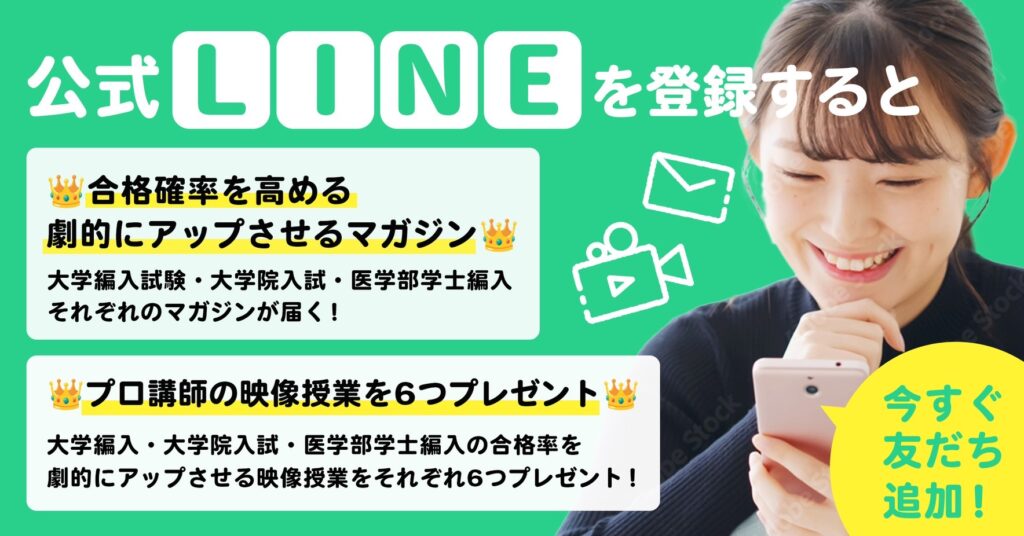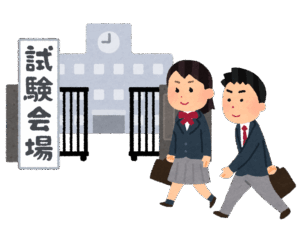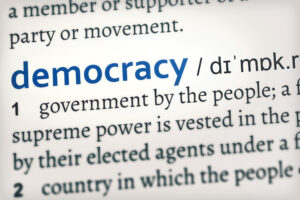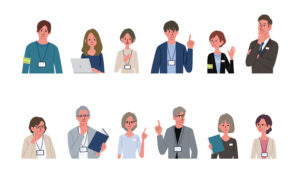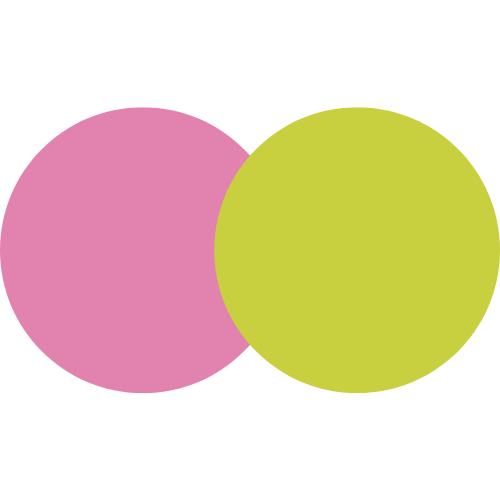ご質問やお問い合わせはお気軽に
大学編入の勉強はいつから始めるべき?
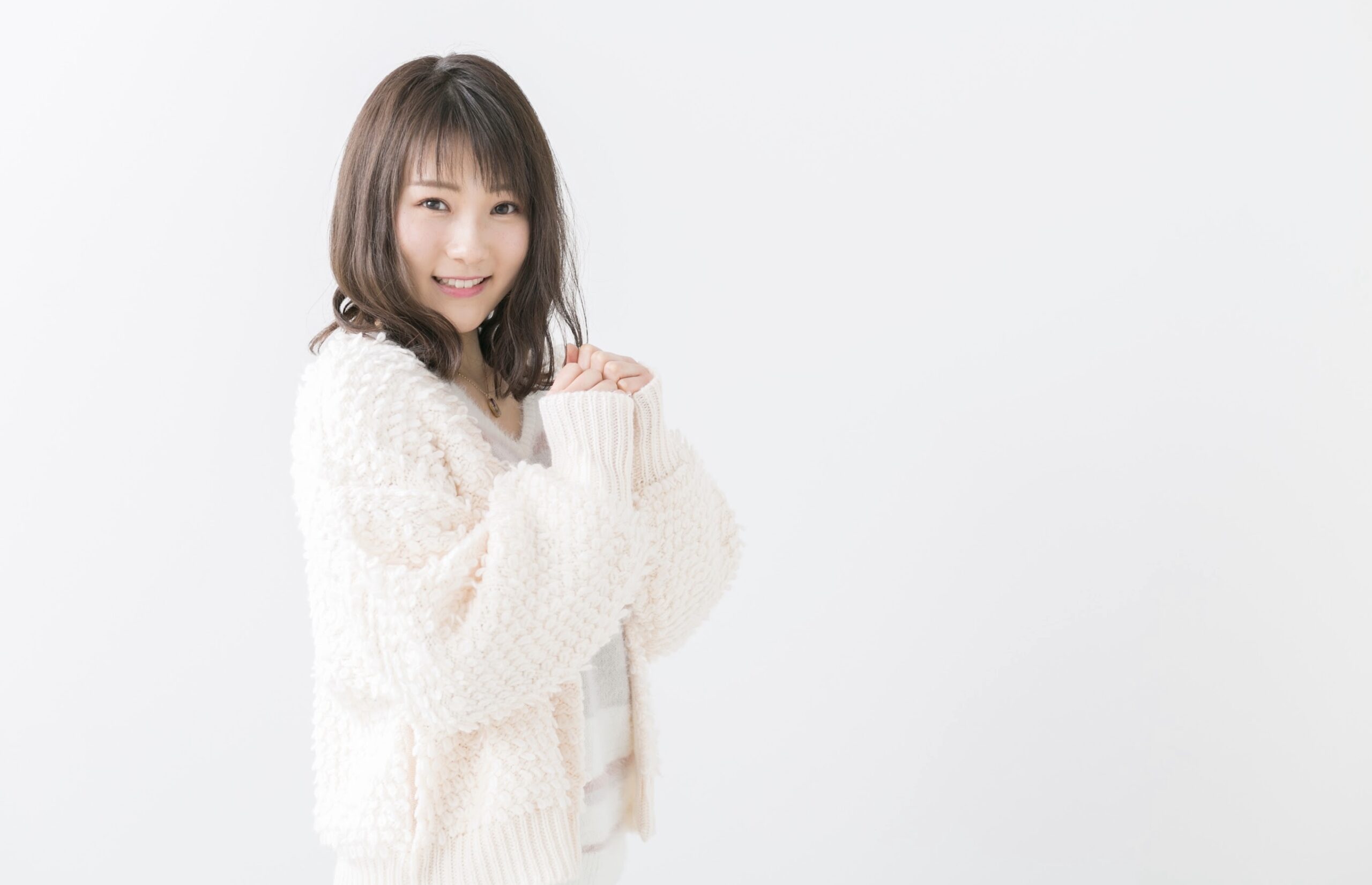
スプリング・オンライン家庭教師では大学編入試験のプロ講師による無料相談を実施中!
大学編入試験のプロ講師が、「あなただけの最適な受験プラン」をご提案いたします。無理な勧誘などはございませんので、お気軽にご予約ください。
【完全版】大学編入試験はいつから始めるべきか?
〜成功するための最適スケジュールと“合格の秘訣”を徹底解説〜
「今の大学が合わないかも…」「将来の就職に向けて、より専門的な学問を学びたい」「難関大で学び直し、キャリアアップしたい」といった理由から、大学編入を検討する方は少なくありません。しかし、いざ編入を考え始めても、
- 編入試験対策はいつから始めればいいの?
- どんな対策をすれば合格に近づくの?
- そもそも編入って、どんなメリット・デメリットがあるの?
といった疑問が次々に湧いてくるのではないでしょうか。
そこで本記事では、「大学編入 いつから」をテーマに、編入試験の最適な準備開始時期や合格までの具体的ロードマップ、編入がもたらすメリット・デメリットまでを深堀り解説します。編入成功者・不合格者のリアルな体験談や、今すぐ実践できるスケジュール例を加え、読み終えた瞬間から行動に移せるよう構成していますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
1. 大学編入とは?基本制度と一般入試との違い
1.1 大学編入の定義と目的
大学編入とは、他の大学・短期大学・専門学校などで一定の単位を取得した人が、別の大学の2年次または3年次から学ぶ制度を指します。取得済みの単位が認められることで、1年生から再スタートするよりも効率的に学士を取得できる点が特徴です。
- 短大卒業後、専門学校卒業後に編入を目指す方も多い
- 在籍中の大学から転籍する形で3年次に編入する例も一般的
1.2 一般入試との比較:募集枠・試験科目・合否基準
- 募集枠の少なさ:一般入試の募集定員に比べ、編入枠は数名〜数十名と非常に限られる。
- 試験内容の違い:英語・専門科目・小論文・面接が重視されやすい。大学によってはTOEFLやIELTSのスコア提出が必須の場合も。
- 合否基準:学力だけでなく、志望理由書や面接を通じて「編入後にしっかり学び続けられる資質」が評価される。
1.3 2年次編入と3年次編入の違い
- 2年次編入:学部のカリキュラムを比較的余裕をもって追えるが、そのぶん単位認定で不足が多いケースも。
- 3年次編入:短大卒・専門卒からの編入が多い。卒業までの期間が短くなるが、専門科目が一気に始まるため、基礎ができていないと苦戦しやすい。
2. 大学編入を考える背景と理由:あなたはどのタイプ?
2.1 今の大学が合わない・興味が変化した
高校生のときに設定した進路・学部が、実際に入学してから「思っていた内容と違う」「やりたいことが変わった」と感じることは珍しくありません。この場合、転学部という選択肢もありますが、希望の学部が同じ大学にない・転学部制度が整っていないなどの理由から、他大学の編入を選ぶ方も多いです。
2.2 キャリアアップや専門性追求を目指す
将来的に大学院へ進学したい、より高度な研究環境で学びたい、ブランド力の高い大学に所属したい、などの理由から編入を決意するケースも増えています。特に国公立大の理系学部や著名私大の文系学部へ編入して専門知識を深め、就職活動や研究キャリアを有利に進めたいという思いが背景にあるようです。
2.3 学費面や家庭事情など、ライフスタイルの変化
家計の事情や家庭環境の変化で、一人暮らしを続けられなくなったり、逆に地元を離れて学びたいと考えたりする人もいます。編入なら1〜2年生の単位が一部認定されるため、1年生から入り直すよりも時間と費用を抑えられるメリットがあります。

3. 大学編入試験はいつから始めるべき?最適なスケジュール感
3.1 試験実施時期を押さえよう(国公立・私立の違い)
多くの理系学部では夏〜秋(6〜10月頃)に編入試験を実施するところが多い一方、文系学部では秋〜冬(10〜12月頃)に試験が行われるケースも。早い大学では6月や7月に出願が締め切られることもあり、1年前から情報収集を始めておくと安心です。
3.2 “1年前”からの準備が理想的とされる理由
- 英語力の強化:単語・文法・読解力などは短期間では伸びづらい
- 専門科目の復習:大学1〜2年レベルの内容を一通り復習する必要がある
- 書類準備・面接対策:志望理由書や自己推薦書は推敲を重ねるほど完成度が上がる
こうした複数のタスクを同時進行するためには、どうしても半年以上の時間が必要になります。特に英語を苦手とする人ほど、早め早めの対策が功を奏します。
3.3 半年前でも間に合う?それでも急げば合格できる条件
「気づいたら試験まで半年しかない…」という人でも、以下の条件を満たせば合格の可能性は十分あります。
- 英語や専門科目にある程度のアドバンテージがある(既に得意、または普段の学習で触れている)
- モチベーションが高く、一気に学習時間を確保できる環境(部活・アルバイトなどを調整できる)
- 勉強法を熟知し、効率的に進めるサポート(予備校やオンライン講座)の活用が可能
ただし、1日でもスタートが遅れると巻き返しが難しくなるため、「やると決めたらすぐ行動に移す」意識が重要です。
4. まずは情報収集から!志望校選定で失敗しないコツ
4.1 大学公式サイトと募集要項の読み解き方
志望校を絞る際は、まず大学公式サイトにある「編入学試験要項」「過去の入試データ」「募集要項PDF」などを入手し、出願条件や試験科目、配点を確認しましょう。特に以下の点を重点的にチェックします。
- 必要単位数:何年在籍・○単位以上取得が出願条件なのか
- 試験形態:英語筆記、小論文、面接、TOEFLスコア提出など
- 出願期間と試験日:他大学との併願可能性やスケジュールの重複を見極める
4.2 シラバス・カリキュラム比較で「本当に学びたい分野」を見極める
編入はゴールではなく、編入後に自分が学問を深めたい意欲を持てるかが非常に大切です。大学公式サイトで各学部・学科のシラバス(授業概要)を見比べ、履修できる科目や教授の専門分野を確認することで、自分の興味・目標に合った大学を選択しましょう。
4.3 過去問・編入予備校・SNSコミュニティの活用術
- 過去問:大学生協やインターネット通販で手に入る場合がある。可能なら5年分程度を入手して分析。
- 編入予備校:編入試験に特化した講座や模試が用意されており、情報量が豊富。費用はかかるが、時間を買うという意味で検討の価値がある。
- SNS・オンラインコミュニティ:TwitterやLINEオープンチャット、Discordなどで「編入試験」をテーマに情報交換しているグループがある。先輩受験者の体験談をリアルに収集できる。
5. 【超重要】編入英語対策と専門科目攻略法
5.1 編入英語の特徴:大学受験英語との違い
編入英語は、長文読解と英作文がメインになる場合が多く、一般入試よりもアカデミックな文章を取り扱うケースがあります。また、大学によってはTOEICやTOEFL・IELTSのスコア提出を求めるところも。
- 読解素材:論文調の文章や時事問題を扱った英文など
- 英作文:自分の意見を論理的に展開できるかが問われる
効率的な英語学習法
- 単語力強化:TOEFL/IELTS用の単語帳やニュース記事を活用
- 文法と構文:1冊の文法書を繰り返し→例題を実際に使ってみる
- 長文読解:過去問だけでなく、科学雑誌や新聞の英文記事も日常的に読む
- 英作文・要約練習:書いた文章を第三者に添削してもらうと効果大
5.2 専門科目は学部2年レベルがベース:過去問分析がカギ
理系なら微分積分・線形代数・物理など、文系ならミクロ経済学・マクロ経済学・心理学理論・社会学理論など、2年次までの基礎科目が中心となることが多いです。
- 過去問を入手し、どの単元が頻出かマッピングして対策優先度を決める
- 参考書の選び方:大学1〜2年次向けの教科書や演習書がベース。難関大の場合はさらに応用的な論文や専門書への理解が必要なケースも。
5.3 小論文・面接対策:論理展開・自己分析・時事ネタの活かし方
小論文では、「あなたが編入したい理由と将来像」「社会問題に対する見解」などが問われやすいです。常に時事ニュースや関連分野の最新トピックをインプットし、自分なりの考えを論理的にまとめられるよう訓練しましょう。
面接では、志望理由やこれまでの学業成果、将来のビジョンなどが質問されるため、自己分析と大学の特徴理解が重要になります。

6. 編入合格までのロードマップ:1年前・半年前・直前期の具体例
6.1 【1年前】目標設定&基礎固めの黄金期
- 情報収集&志望校リストアップ
- 大学公式サイト、過去問、編入予備校のパンフレットなどを調べる
- 英語基礎固め
- 単語帳・文法書を一通り復習、読解問題に慣れる
- 大学1〜2年次の授業復習
- 大学や短大・専門学校で取った講義ノートや教科書を再点検
ポイント
- この時期に自分の得意・苦手科目をはっきりさせ、学習計画を立てる。
- 志望理由書や研究テーマの構想を始めておくと、後々書類作成がスムーズになる。
6.2 【半年前】過去問演習&応用力強化の集中期
- 過去問を解く・分析する
- まずは時間を測り、本番さながらに解いてみる→自己採点→解説や教科書で復習
- 小論文・面接の準備
- 志望理由書のドラフト作成→添削→修正
- 面接想定質問をリスト化し、口頭で練習
- 英語の速読力・英作文力アップ
- 時間を区切った速読演習&エッセイ練習
ポイント
- 自己分析を深め、面接で話せるエピソードを整理する。
- 弱点科目はこのタイミングで克服し、本番までにレベルを引き上げる。
6.3 【直前期】仕上げフェーズの勉強法と体調管理
- 模試・模擬面接
- 編入予備校や大学のキャリアセンターを活用し、実践的な練習を行う
- 過去問の再復習
- 新しい問題集に手を出しすぎず、過去問を再度復習してミスを徹底排除
- 体調管理・メンタルケア
- 睡眠・食事を整え、試験当日にベストを尽くせるようコンディションを調整
ポイント
- ここまで積み上げた知識を“最終確認”し、余裕をもって試験当日に臨む。
- 面接練習は録音・録画して客観的にチェックすると効果的。
7. 成功体験談&失敗体験談から学ぶ“合格を勝ち取る秘訣”
7.1 早期スタートで難関大合格:Aさんのストーリー
Aさんは地方の私大に在籍しながら、1年次終わりから「自分は本当は経済学をより深く学びたい」と強く感じ、2年次編入を目指して準備を開始。英語はTOEFL対策を並行して行い、専門科目の経済理論は大学教科書に加え過去問を分析。1年前から始めたことで、夏休みに過去問を8年分解き込み、志望理由書も数回の添削を経て完成。結果として、第一志望の難関国公立大学に合格を果たしました。
7.2 ギリギリ対策であと一歩届かなかったBさんの後悔
Bさんは大学2年の秋頃に急に思い立ち、3年次編入を受験するも、残り2ヶ月しか準備期間がありませんでした。英語はなんとか形にできたものの、専門科目の範囲が広くて過去問分析が不十分。さらに面接対策も自己流でまとまらず、本命の大学に不合格。もう少し早く決断していれば…と痛感したそうです。
7.3 編入後の学習負担と乗り越え方:成功者が語るリアルな大学生活
編入に成功したCさんは「最初は同期との専門知識格差に戸惑った」と語ります。3年次スタートで周囲が既に学んでいた科目を自力で補う必要があり、最初の1〜2ヶ月は必死だったそうです。しかし、ゼミやグループワーク、教授への質問を積極的に活用し、2学期には十分追いつけたとのこと。
早めに助けを求める行動力が、編入後の学習負担を乗り越える鍵になるといいます。
8. 忙しい大学生・社会人でもできる編入対策:時短・効率化テクニック
8.1 スケジュール管理アプリ&タスク分解で“見える化”
- GoogleカレンダーやNotionなどを使い、1日の勉強タスクを明確化
- 「英単語30分」「専門科目の過去問1回分」など細かく区切って達成感を高める
- 週末に“前週の振り返り”と“翌週の計画”を立てる
8.2 通勤・通学中のスキマ時間活用法
- 英単語アプリ(mikan、Ankiなど)で毎日コツコツ暗記
- リスニング学習:英語ニュースや講義のポッドキャストを聴き、耳を慣らす
- スマホでPDF閲覧:編入予備校のテキストや電子書籍を移動時間にチェック
8.3 週末のまとめ勉強&オンラインツールの併用
平日は短時間学習が中心でも、週末に過去問演習や小論文執筆などまとまったタスクを片付ける。オンライン講義やYouTubeの解説動画を活用して、理解の浅い箇所を一気に補強するのもおすすめです。

9. 編入後に得られるメリット&覚悟しておくべきデメリット
9.1 編入で実現する学問的成長と人脈拡大
- 専門性の飛躍的向上:自分が本当に興味を持てる分野を学べる喜びは大きい
- 新たな学友や教授との出会い:編入生同士のコミュニティやゼミ活動で、人脈が大きく広がる
- 就職・大学院進学にもプラスに働く:学びたい分野を深めるほど将来の選択肢が増える
9.2 卒業時期が遅れるリスクと単位認定の壁
- 単位認定:大学間でカリキュラムが異なるため、思ったほど単位が認められない場合がある
- 卒業延期:最大で半年〜1年ほど卒業時期が後ろ倒しになる可能性も
- 再履修コスト:実験・実習科目が多い理系では、再履修の負担が大きい
9.3 先に知っておきたい就職活動への影響
企業によっては「編入で留年したの?」と疑問を抱かれることも。ただし、面接で「自分の意志で再挑戦し、専門分野を深く学んできた」とポジティブに語れれば、むしろ主体性や探究心として好意的に受け取ってもらえるケースが多いです。
10. 編入以外の選択肢も検討しよう:転学部・休学・再受験との比較
10.1 大学内で転学部できるなら?メリットと課題
大学によっては転学部制度が用意されており、受験のハードルが編入よりも低い場合があります。一方で「希望の学部がない」「定員が少なく競争率が高い」などの課題もあるため、事前にしっかり調査が必要です。
10.2 休学して留学orインターンシップ:可能性を広げる方法
「いきなり編入試験を目指すより、まずは1年間休学して海外留学やインターンで経験を積み、自分のやりたい分野を見極める」という方法もあります。休学期間中に英語力を飛躍的に伸ばせれば、編入試験にも圧倒的に有利になるでしょう。
10.3 一度卒業してからの再受験という選択肢
在籍中の大学を一度卒業してから、別の大学を新入生として受験し直す方法もあります。年齢的な問題や時間的ロスは大きいですが、どうしても入りたい学部・大学があり、編入枠が極端に少ない場合に選択肢となることも。
11. 費用・生活面のシミュレーション:学費・奨学金・引っ越し費用など
11.1 編入試験の受験料・交通費・教材費はどれくらい?
編入試験の受験料は1校あたり2〜3万円程度が一般的。複数校を併願するなら、それだけ出費は増えます。また、過去問・参考書・予備校費用や受験当日の交通費・宿泊費なども考慮すると、10万円以上かかるケースもあるので、早めに資金計画を立てましょう。
11.2 国公立 vs 私立:学費格差と奨学金制度
- 国公立大学:年間授業料は約50〜60万円程度
- 私立大学:文系で100万円前後、理系だとさらに高くなるケースも
日本学生支援機構の奨学金や自治体の奨学金、大学独自の奨学金制度を調べ、利用可能かチェックしておくと◎。
11.3 遠方の大学に編入する場合の住居・生活費
都心部の私立大学に編入する場合、家賃相場が現在より大幅に上がる可能性があります。実家から通える大学を選べば学費以外の負担を抑えられる場合もあるので、経済面と学習目的のバランスを検討しましょう。
12. 【チェックリスト】編入を最終決断する前に確認すべき7項目
- 編入の目的・ゴールが明確か
- 「なぜ今の大学ではダメなのか」「編入後に何を学びたいのか」が言語化できるか
- 出願資格を満たしているか
- 在籍期間・修得単位数・成績要件(GPA)など
- 志望校の情報は十分か
- 試験科目、配点、過去問、教授やゼミの研究分野を把握しているか
- 学費・生活費のシミュレーションは完了したか
- 国公立か私立か、引っ越しの有無や奨学金利用を含めた検討
- 家族や周囲の理解を得られるか
- 精神的・経済的なサポートは期待できるか
- 転学部や休学、再受験との比較は済んでいるか
- 編入がベストな選択であると納得できるか
- 試験までのスケジュールに無理はないか
- あとどれだけ時間があり、どこまで対策を積めるか

13. 【補足】オンライン授業時代の編入対策事情
13.1 オンライン面接・オンライン試験への備え
近年、一部の大学でオンライン面接を導入するケースが増えています。通信環境やカメラ・マイクの確認、照明や背景のセッティングを入念にチェックしましょう。
13.2 学部・学科によっては実験実習の制限も?
コロナ禍で一部の理系学部の実験科目がオンライン化されるなど、カリキュラムが変則的になっている場合があります。志望校の最新情報を常に追いかけ、編入後の研究活動に支障がないか確認しておく必要があります。
13.3 SNS・ネットワークをフル活用して情報をゲット
大学のオープンキャンパスや説明会がオンライン開催になっていることも多いため、自宅から参加できるメリットを活かし、複数大学のイベントに参加して比較検討すると良いでしょう。
14. まとめ:大学編入はいつから始める?今がベストタイミング!
14.1 1年前からの計画が王道、でもやる気があればまだ間に合う
「大学編入 いつから始めるべき?」という疑問に対して、理想は1年前からの着手です。英語と専門科目、小論文・面接に十分時間をかけられ、書類の完成度も高められるからです。ただし、半年を切っていても、本気で集中すれば挽回可能なケースもあります。
重要なのは、「まだ間に合うのか?」と立ち止まるよりも、「今すぐできる対策は何か?」を見つけて走り始めること。
14.2 情報収集と基礎固めで合格可能性はグッと高まる
- 情報収集:募集要項、過去問、編入予備校、SNSなどを駆使して網羅的に行う
- 基礎固め:英語の単語・文法・読解、専門科目のコア部分を着実に理解する
- 志望理由の明確化:書類や面接で強い説得力を発揮できるよう、目的意識を高める
この3つを徹底すれば、あなたの合格可能性は格段にアップします。
14.3 “行動開始”こそが未来を切り開く第一歩
迷いは誰にでもあります。しかし、行動を先延ばしにすると、そのぶんスタートダッシュの優位性を失うことに。まずは一冊の英単語帳を買う、大学公式サイトの募集要項をダウンロードする、編入経験者に話を聞いてみる――こうした“小さな一歩”こそが、大きな成果に繋がっていくのです。
15. あとがき:編入は人生の新たなスタートライン
ここまで、「大学編入 いつから」という最大の疑問を軸に、編入試験の概要や学習計画、合格のための具体的なポイントを徹底的にご紹介しました。
編入は一見、遠回りに思えるかもしれません。しかし、本当に学びたいことを見つけ、そこに全力で取り組める環境へと飛び込む経験は、あなたの人生を大きく変える可能性を秘めています。
- 自分が納得できる大学・学部で学び直すこと
- キャリアアップや専門性を磨くチャンスを得ること
- 自分で選んだ道を突き進む強い意志が育つこと
どれも簡単な道のりではありませんが、その先には充実感と可能性が広がっています。今の迷いや不安を打ち消すのは、情報を得ることと行動を起こすことしかありません。「よし、やってみよう」と決心するその瞬間が、あなたの未来を明るくする大きな一歩です。
本記事があなたの編入ライフを後押しし、最高の結果につながることを心から願っています。これからあなたの“学びの再スタート”を切り拓いていきましょう。応援しています!
【執筆後記:さらに一歩踏み出したい方へ】
- まずはスケジュールを立案し、今日から勉強を始める
- 志望校の先輩や編入予備校の無料相談に行ってみる
こうしたシンプルなアクションから、未来はどんどん変わっていきます。「大学編入はいつから?」の答えは、「今すぐ!」。ぜひ、本記事を参考に行動を開始し、合格を勝ち取ってください。あなたの成功を心から応援しています。
大学のリカレント教育プログラムについては、こちらの記事も参考にしてください。
参考:社会人の学び直しにおすすめの大学16選!メリット・デメリットも解説| Elephant Career(エレファントキャリア)
おわりに
いかがだったでしょうか。
スプリング・オンライン家庭教師には、法政大学法学部の編入学試験で受験生を合格に導いた講師も多数在籍しています。受験生一人ひとりに合った最適な講師の指導で最短の合格を導きます。
大学編入は大学を変える最後の機会です。法政大学法学部をはじめとした難関大学の合格を目指すなら、ぜひ一度無料相談ください。
★無料相談はいつでも受付中!
★お問い合わせは公式HPもしくは公式LINEよりご連絡ください。
【公式HP】https://spring-online.jp
【公式LINE】https://lin.ee/hIY76pU
全国の受験生と繋がれる完全無料の匿名サロンはこちら:【大学編入】経済・経営・商学部

◎過去問解説動画や映像授業はこちら!(スプリングオンライン編入予備校)
スプリング・オンライン家庭教師HP:https://spring-online.jp/
スプリング・オンライン編入予備校HP:https://elearning.spring-online.jp/
YouTubeホーム:https://www.youtube.com/channel/UC50UbsiY7HNGAyxVbz0mLiw
\公式LINEで豪華6大特典をプレゼント中!/